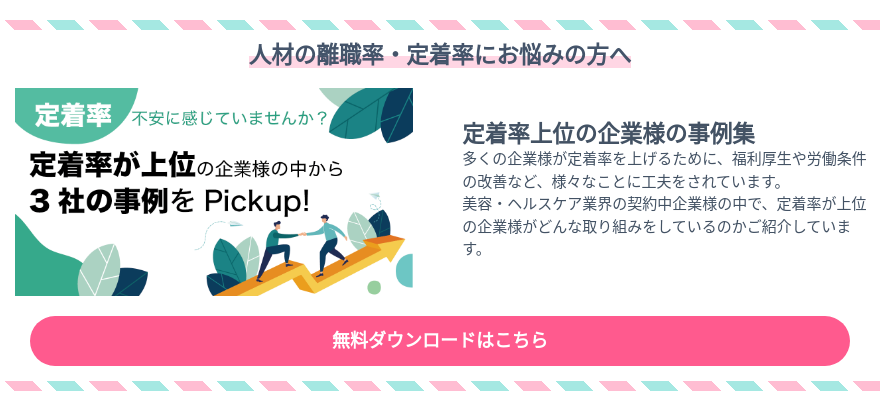欠員補充とは、組織内で空いたポジションを埋めるために、新たな人材を採用することです。近年、労働力人口の減少や転職者の増加といった社会的な背景から、多くの企業がこの課題に直面しているのではないでしょうか。
そこで本記事では、欠員補充について言葉の意味や言い換えを整理した上で、原因、企業への影響、効果的な人材確保戦略を紹介します。また、欠員補充後に重要となるオンボーディングについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
欠員補充とは
欠員補充とは、従業員の退職や異動、長期休職などで生じた組織内の空きポジションを埋めるために、新たな人材を採用することです。すでに存在する役割や職位の働きを維持する目的で行われます。
欠員が発生すると、生産性や業務効率の低下、残った従業員のモチベーション低下といった問題につながります。そのため、組織運営の安定性を保つには、迅速な欠員補充が欠かせません。
欠員補充の言い換え表現
欠員補充の言い換え表現を以下で紹介します。使用場面に応じてより適した表現を用いましょう。
- 後任採用
前任者が退職や異動した後に、そのポジションを引き継ぐ人材を採用することです。
- 補充採用
欠員に伴い、必要な人材を採用することです。
- 穴埋め採用
組織内に生じたポジションの「空き=穴」を埋めるための採用を表す口語的な表現です。
- 人材補填
不足している人材を埋め合わせることを意味します。「補填」は主に金銭的な文脈で使われますが、ここでは人材に適用されています。
- 人員補充
不足している人員を補うことを意味する一般的な表現です。欠員補充と比べると、役職や職位を特定しないニュアンスが強まります。
欠員が発生する原因とシチュエーション
欠員が発生する原因とシチュエーションについて、「自発的離職」「非自発的離職」「予期せぬ欠員」の3パターンで解説します。
自発的離職
自発的離職は、従業員が自らの意思で退職を選択するパターンです。具体的には、以下のようなシチュエーションが挙げられます。
- キャリアアップを目指しての転職
- ワークライフバランスを改善するための転職
- より良い給与や待遇を求めての転職
- 職場環境や人間関係に不満を感じての退職
- 出産や育児を行うための退職
- 親族の介護を行うための退職
- 配偶者の海外転勤に伴う退職
なお総務省の労働力調査によると、自発的離職者は月平均で75万人(2023年)です。次項目の非自発的離職者の43万人と比べて約1.7倍多く、欠員が生じる主な原因といえます。
非自発的離職
非自発的離職は、主に企業側の事情により従業員が退職するパターンです。具体的には、以下のようなシチュエーションが挙げられます。
- 定年退職や契約満了による退職
- 組織再編による退職
- 職務不適合による解雇(普通解雇)
先と同様の労働力調査によると、非自発的離職者の月平均43万人(2023年)のうち、定年または契約満了による退職は18万人、企業の都合による退職は25万人でした。
予期せぬ欠員
自発的離職と非自発的離職以外にも、予期せぬ原因により欠員が生じるパターンがあります。具体的には、以下のような場合です。
- 病気による休職や退職
- 突然の事故による死亡
- 職務上の不正行為発覚による懲戒解雇
他2つのパターンと比べると稀ですが、発生すれば欠員を引き起こします。
欠員が与える企業への影響
欠員が与える企業への影響は多岐にわたります。
例えば、残業増加のような業務効率低下や従業員の意欲低下、更なる離職者の発生などを引き起こすことが、労働白書(厚生労働省)で指摘されています。
▼人手不足による職場環境への影響

そこで以下では、欠員が企業へ与える主要な影響について、具体的に紹介します。
影響1:従業員の生産性・業務効率の低下
欠員が発生すると、空いたポジションの業務を他の従業員がカバーしなければなりません。
追加業務の発生により通常業務に割くリソースが減少し、総合的な生産性は低下します。
特に業務が属人化していた場合には、残された従業員が手探りで遂行しなければならず、業務効率の低下は免れません。専門性や経験を要する業務の担当者が欠けた場合も同様です。
影響2:残存従業員のモチベーション低下と労働環境の悪化
欠員状態が続く限り、残存する従業員に負担がかかり続けます。多くのケースで、追加の業務や役割が割り当てられ、オーバーワークが発生しやすくなります。
こうした状況では、従業員が業務に対してストレスを感じるだけでなく、職場全体のモチベーションを低下させます。モチベーション低下は労働環境の悪化につながり、連鎖的な欠員を引き起こしかねません。
残された授業員のモチベーションおよび健全な労働環境を維持するためにも、欠員の迅速な対応が不可欠です。
影響3:顧客サービスの質の低下とブランディングへの悪影響
欠員により負担が増すと業務をこなすのに手一杯となり、顧客サービスの質が低下します。例えば、顧客対応を担う部門で欠員が発生すれば、問い合わせ対応やサポートが遅れ、顧客満足度が低下するリスクがあります。
また、サービスの質が下がると、企業のイメージやブランディングにも悪影響を及ぼします。特に顧客との接点が多い業種では、こうした影響が顕著に表れ、顧客離れや信頼の損失が懸念されます。
影響4:売上の減少および採用コストの増大
影響1〜3の結果として、売上の減少や採用コストの増大を引き起こします。欠員の影響で顧客対応が遅れたり、サービスの提供が滞ったりすると、顧客満足度の低下から売上減少につながります。
さらに、欠員補充を行うためには採用コストの増加も避けられません。具体的には、求人広告の出稿や人材紹介会社の利用、面接や教育にかかる時間や人件費などを要します。
以上のような悪影響が積み重なると経営が悪化し、人手不足に起因する倒産を招きかねません。帝国データバンクの調査によると、従業員の退職や採用難などを原因とした倒産の件数は、2024年度上半期(4〜9月)で163件であり、過去最多を大幅に更新した2023年度を上回るペースで推移しています。

こうしたデータからも、欠員が企業に与える影響の深刻さが分かります。経営の安定化を図るためには、人材確保戦略を講じて早期に欠員を補うことが重要です。
欠員発生時の効果的な補充の手順
欠員発生時の効果的な補充の手順を、以下4つのステップで紹介します。
1.仕事内容の分析と人材要件の定義
欠員を補充する際は、まず空いたポジションの役割と責任を再確認し、必要なスキルや経験を明確にしましょう。単なる補充ではなく、業務の効率化や改善の機会として職務の内容や範囲を見直すとよいでしょう。
その上で、新たな人材に求める条件を言語化し、人材要件を定義します。人材要件を定義する際には、能力・スキル面だけでなく企業文化との適合性も考慮する必要があります。企業文化にマッチした人材を採用すれば、長期的な活躍を期待できるのはもちろん、組織の一体感向上にもつながるためです。
以上により、後のステップをスムーズに進めるための基盤を整えます。
2.採用計画の策定
次に具体的な採用計画を策定します。採用計画には、採用スケジュール、採用チームの編成、採用予算の策定が含まれます。欠員補充の緊急度や予算、必要なリソースを考慮して現実的なプランを立てましょう。
また採用チームについては、人事部門だけでなく、該当ポジションの上司や関連部署のメンバーを編成し、それぞれの役割を明確化するとスムーズに推進可能です。
また、採用活動には、求人広告費や人件費など様々なコストを要します。予算の上限を設定し、以降のステップを踏まえて効率的なリソース配分を検討しましょう。
3.内部人材の活用検討
ステップ1で要件を決め、ステップ2で採用計画を立てたら、一旦は内部人材を活用する可能性を検討します。既存の従業員のなかに、欠員が発生したポジションを引き継げる人材はいないでしょうか。
社内での配置転換や昇進などにより、即戦力の欠員補充が可能となるケースがあります。即戦力とまでいかずとも、研修やリスキリング機会の提供を経てポジションを担える人材であれば対象となり得ます。
内部人材で欠員を補充できると、業務の引き継ぎがスムーズであり、採用コストも削減可能です。また、従業員のキャリアアップやモチベーション向上にもつながるでしょう。
4.新規採用活動の開始
内部人材の活用が難しい場合、各採用媒体を用いた新規採用活動を開始します。
求人サイトを活用する場合は、求人情報を公開して応募をスタートさせます。その後、書類選考、適性検査、面接などを通じて、定義した人材要件にマッチする候補者を選定しましょう。
先述した通り、能力・スキル面とあわせて候補者と組織との文化的な相性も考慮し、長期的な活躍が期待できる人材を見極めるのが重要です。
また、空きポジションおよび自社にマッチした人材を早期に採用するためには、自社が属する業界に特化した採用媒体を活用するのが有効です。
例えば「リジョブ」の場合、美容・ヘルスケア業界特化の人材が多く登録しており、総会員数は55万人に及びます。低コストを実現しやすい採用成果報酬ウェイト型のため、求める人材を高いコストパフォーマンスで採用できる可能性が高い点も特徴です。
まずは下記サイトをご覧の上、お問い合わせフォームから気軽にご相談ください。
関連リンク
欠員補充をしやすくなる人材確保戦略
欠員補充をしやすくなる人材確保戦略を、4つ紹介します。
1.デジタル採用ツールの活用
現代の採用活動では、デジタルツールの活用が欠かせません。具体的には、以下のようなツールを活用すれば選考プロセスを効率化でき、迅速な欠員補充が可能です。
AIを活用した候補者スクリーニング
AIが人材要件に当てはまる候補者を自動で選定してくれます。担当者が検索や確認、選定を行うよりも格段に早く行える上、見落としなどの人為的なミスも起こりません。
オンラインアセスメントツール
候補者の適性や能力を測るために、オンラインでの適性検査やスキルテストの実施も有効です。実施および受験の両負担を軽減でき、欠員補充に向けてスムーズな対応が可能となります。
オンライン見学や面接
オンライン見学や面接は時間と場所に縛られないため、遠隔地に住む候補者の参加ハードルが低くなります。企業側の準備にかかる負担も軽減されます。
オンラインでサロン見学をした後に、面接を受けました。営業中にサロン見学をさせてもらったおかげで、リアルなお店の雰囲気を感じることができましたし、私からの質問にも細かく答えてもらえたので、不安なく試験に臨むことができました
引用:モアリジョブ|美容室「THE DAY」美容師・アシスタント 花さん
2.ブランディングの強化
ブランディング強化により候補者の関心を引きつけていれば、欠員が発生した際にも応募が集まりやすくなります。具体的には、以下のような取り組みが挙げられます。
企業文化や価値観の発信
自社の企業文化や価値観をオープンに発信すれば、共感する候補者が集まりやすくなり、ミスマッチの予防にも効果的です。例えば、CSR活動や社内制度、福利厚生についてなど、自社の独自性が反映された内容が挙げられます。
SNSを通じた情報発信
SNSを活用して企業の日常や活動を発信することも、ブランディングの一環として有効です。SNS上で企業の存在感を高め、候補者との接点を増やすことで、より多くの人材が興味を持ってくれます。
Z世代を対象とした就職活動時のSNS活用に関する調査では、回答者の6割以上がSNS上の企業情報によって入社意欲が高まったと答えています。このデータからも、SNSによるブランディングの有効性を理解できます。
▼SNS上の企業情報を見て選考や入社の意欲度は上がりましたか?

従業員体験談の紹介
採用媒体などを通じた従業員体験談の紹介は、自社が大切にする価値感や仕事のやりがいを伝える手段として有効です。よりリアルな視点から自社の魅力を理解してもらえる機会となります。
また、先と同様の調査で企業にオンライン上でどのような情報を発信してほしいかを聞いた結果は、下記の通りでした。
▼企業に対してオンライン上でどのような情報を発信してほしいですか?(複数回答)

この結果を踏まえると、「従業員体験談の紹介」に「1日の仕事の流れ」「社内の人間関係・職場の雰囲気」「仕事のやりがい」が伝わる内容を盛り込むのがよいでしょう。
3.柔軟な雇用形態の提供
柔軟な雇用形態の提供により、採用の間口を広げ、幅広い候補者にアプローチしやすくなります。具体的には、以下のような取り組みが有効です。
リモートワークの検討
勤務地にとらわれない働き方の実現により、地方や海外在住の人材も含め、多様な候補者に対応できます。ワークライフバランスを重視する候補者へのアピールポイントにもなります。
なおパーソルキャリア株式会社の調査によると、転職を検討する際にリモートワークの可否が応募の意向に影響すると答えた人は約6割でした。
▼転職を検討する際にリモートワーク・テレワークを実施しているかどうかは、応募の意向に影響しますか

フレックスタイム制度の導入
働く時間帯を柔軟化すると、候補者のライフスタイルに合った働き方を提案でき、定着率の向上にもつながります。この制度を導入していれば、欠員時も幅広い人材からの応募を期待できます。
実働時間8hのフレックス制を取り入れています。「拘束時間が長い」「土日休めない」を理由に美容師を辞めてしまう人をたくさん見てきたので、そこに自由を持たせられるフレックス制を導入すれば、応募も増えるんじゃないかなと。
引用:モアリジョブ|美容室「Vesper」オーナー 齊藤 良さん
業務委託や時短勤務の活用
業務委託契約や短時間勤務も活用し、専門性の高いスキルを持つ人材を確保しやすくしましょう。フルタイム以外の働き方を提供すれば、育児中や介護中の候補者にもアプローチが可能です。
フルタイム勤務は10時から18時ですが、パートタイムでしたら1日3時間以上、お子さんや介護などの事情があれば時短勤務も可能です。
一般的なサロンは拘束時間が長いので、家族と一緒に過ごす時間がなかなか取れない、育児と仕事の両立ができなくて辞めざるをえないといった問題に直面する方が多いですよね。でも、ここなら仕事も家庭も、無理なく両立できます。
引用:モアリジョブ|株式会社C&P 営業部 マネジャー 横浜 輝史さん
4.そもそも従業員が定着しやすい環境づくりを
欠員が発生する度に人材を補充するのではなく、そもそも従業員が定着しやすい職場環境を整えましょう。そのためには、まず退職に至る理由を把握する必要があります。
エン・ジャパン株式会社の調査によると、「会社に伝えなかった本当の退職理由」で最も多いのは、人間関係が悪い(46%)であり、給与が低い(34%)、会社の将来性に不安を感じた(23%)と続きます。
▼会社に伝えなかった本当の退職理由を教えてください。(複数回答可)

こうした結果を踏まえて、定着を促すために以下のような取り組みを行うと良いでしょう。
個別面談の実施
部門や部署、店舗といった単位でリーダーが各メンバーと個別面談を定期的に実施し、各従業員が抱える課題の解消を図ります。業務や人間関係などの課題が深刻化する前に見つかり、早期解決につながるため、職場への信頼感と安心感が高まります。
働きやすさとしては、やっぱり人間関係がすごく大切なので、コミュニケーションを重視して施策をうっています。
例えば自分の技術の進捗や抱えている悩みなどを出せる場として、役職のあるメンバーとの1on1ミーティングを全スタッフが毎月行います。その精度を上げるために、役職メンバーには講師を入れたコーチングの勉強会もしているんです。
引用:モアリジョブ|美容室「FILMS」代表 若林紀元さん
公正な報酬と福利厚生制度の整備
職務内容や成果に応じた適切な報酬体系と、充実した福利厚生制度を整備すれば、従業員の満足度が向上し、欠員リスクが軽減されます。
昨今の働き方改革により、働き方や雇用の在り方を見直すサロンが増え、今や福利厚生が整っているところは当たり前の時代。美容師として活躍はしたいけれどプライベートも大事にしたい気持ちから、サロン選びに対してシビアな目を持つようになったと感じています。
引用:モアリジョブ|美容室「Violet」本部長 藤橋 孝さん
キャリア開発機会の提供
各従業員が自社でキャリアを積み重ねて、自らの成長を実感できる機会を提供すれば、定着率向上を期待できます。
具体的には、各ポジションに求められるスキルや昇進の機会を示した「キャリアパス」の明示や、定期的な「スキルアップ研修」の実施などが有効です。
欠員補充ができたら行うべきオンボーディング
欠員補充ができたら行うべき「オンボーディング」について解説します。
オンボーディングとは
オンボーディングとは、新しく採用された人材が職場や業務に円滑に適応できるようにサポートするプロセスを指します。単に業務の引き継ぎだけでなく、独り立ちや企業文化への適応を支援して組織への定着化を図るため、企業と従業員の両者にとって重要です。
オンボーディングの準備と進め方
オンボーディングを成功させるためには、準備が欠かせません。事前にカリキュラムを設計し、メンターの配置、進捗の確認、フォローアップなど、従業員がスムーズに職場に適応できる仕組みを整備することで、新規採用者が早期に活躍できる土台を築けます。
以下では、準備を含めた具体的な進め方を解説します。
1.オンボーディングカリキュラムの設計
新規採用者が初日から順を追って業務を覚え、スムーズに実務に取り組めるよう、あらかじめオンボーディングのカリキュラムを設計しておきます。
カリキュラムには、初日のオリエンテーションから始まり、基本的な業務フローやツールの使い方、具体的な業務へのステップアップまで、一連の流れが含まれます。
これにより、新規採用者が迷わずに業務を遂行できる体制を構築でき、早期の独り立ちを可能にします。
2.メンター制度の導入
新規採用者が困ったときにすぐ相談できるよう、経験豊富な先輩社員がメンターとしてマンツーマンでサポートする体制を整えます。
業務を熟知した従業員の指導やアドバイスによって、新規採用者のスムーズな業務習得を促します。入社直後だけでなく、数週間から数カ月にわたる継続的なフォローアップを行い、新規採用者が自信を持って業務に臨めるよう支援します。さらにメンターは日々の業務だけでなく、長期的なキャリア形成の相談相手としての役割も担います。
またメンター制度は、新規採用者(メンティ)の成長はもちろん、指導・サポートに当たる先輩社員(メンター)の育成意識向上にもつながることが、厚生労働省の調査で示されています。

3.メンターの選抜・割り当て
メンターとして割り当てる人材の選定も重要です。単にマネジメントを行えるだけでなく、将来のリーダー候補として期待される若手や中堅社員にもメンターを任せれば、コーチングやフィードバックスキルの向上を図れます。
4.オンボーディングの実施・振り返り
準備したカリキュラムに基づき、オンボーディングの実施に移ります。実務を通じて必要なスキルを学びつつ、新規採用者が疑問点や課題を解決できるようにメンターがサポートします。
また、オンボーディングの「振り返り」には、以下2つのステップがあります。
- 毎日の振り返り
新規採用者とメンターで1日の業務を振り返り、理解度や課題を共有する時間を設けます。これにより、次のステップへスムーズに進めます。
- カリキュラム全体の振り返り
オンボーディング終了後に、メンターや人事担当者がカリキュラムの効果を評価し、次回に向けた改善点を洗い出します。これにより、より効果的なオンボーディング体制が整います。
5.実施内容の報告・継続的な支援
オンボーディングは新規採用の初期段階で終わりではなく、その後の継続的な支援が大切です。
オンボーディング終了後も、定期的に新規採用者との面談やフィードバックの場を設け、「困ったときには相談できる」といった心理的安全性を確保しましょう。こうした継続的な支援体制が新規採用者の成長を後押しし、職場への長期的な定着を促進します。
まとめ
欠員補充は、組織の空きポジションを迅速かつ効果的に埋めるための重要な取り組みです。本記事では定義を示した上で、欠員発生の原因と企業への影響、効果的な人材確保の手順について解説しました。
欠員補充について理解すべき重要ポイントは、次のとおりです。
- 欠員を放置すれば、生産性低下や従業員のモチベーション低下、顧客サービスの質の低下などを引き起こしてしまう
- 欠員補充は、仕事内容の分析、採用計画の策定、内部人材の活用検討、新規採用活動の開始の4ステップで行う
- 欠員を補充するための人材確保戦略としては、デジタル採用ツールの活用、企業ブランディングの強化、柔軟な雇用形態の提供、従業員が定着しやすい環境づくりが効果的
- オンボーディングを成功させるには、カリキュラム設計やメンター制度の導入、実施の振り返り、継続的な支援が重要
今後も人材不足や売り手市場が続くなか、企業にとって欠員補充は不可欠な取り組みです。効果的な人材確保戦略により迅速かつ適切な補充を行い、自社の安定的な成長につなげましょう。

- 執筆者情報
- 高橋祐哉(Takahashi Yuya)