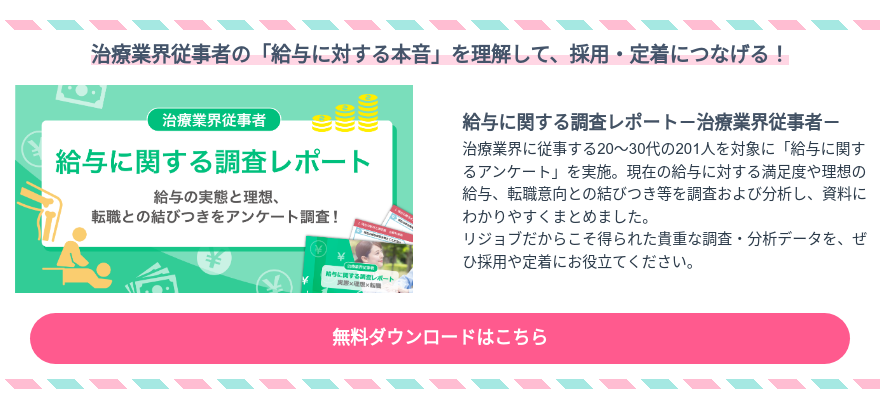整骨院の経営において、従業員の労働環境を適切に整えることは、スタッフの定着率向上や顧客満足度の向上につながります。
ただ一方で、労働基準法を十分に理解せずに運営すると、長時間労働や未払い残業といったトラブルが発生し、労働基準監督署の指導対象となるリスクもあります。
そこで本記事では、整骨院の経営者が知っておくべき労働基準法の基本事項や、違反やトラブルを避けるためのポイントを詳しく解説します。適切な労務管理を実践し、スタッフが安心して働ける環境を整え、院の安定経営につなげましょう。
そもそも労働基準法とは?整骨院の経営側が知っておくべき基本事項
労働基準法は、すべての労働者が適切な労働条件のもとで働けるように定められた法律です。整骨院も例外ではなく、雇用する施術スタッフや受付スタッフの労働環境を整えるため、法令遵守が求められます。
ここでは、整骨院の経営者として最低限知っておくべき労働基準法の基本事項について解説します。
労働時間は「1日8時間・週40時間以内」が原則だが特例もある
労働基準法では、労働時間の上限を「1日8時間・週40時間以内」と定めています。これを超えて従業員を働かせる場合は、時間外労働として扱われ、割増賃金を支払う必要があります。
ただし、整骨院のような「小規模な医療・サービス業」では、特例措置対象事業場に該当する可能性があり、その場合は「週44時間まで」の労働が認められます。この特例が適用されるのは、従業員が10人未満の事業場に限られます。
たとえば、以下のような勤務体制が可能です。
- 週6勤務:月曜日~金曜日までは8時間勤務、土曜日は半日勤務で4時間
- 週5勤務:月曜日~木曜日までは9時間勤務、金曜日のみ8時間勤務
なお、Zenken株式会社の調査によると、柔道整復師の1日あたりの平均勤務時間は、以下の通りでした。対象は「柔道整復師の国家資格保有者で柔道整復師の仕事をしている」と回答した20歳以上〜65歳以下の男女164名です。
▼柔道整復師の1日あたりの平均勤務時間

上記データでは「8〜9時間未満(46.6%)」が一番多いものの、10時間以上と回答した方の割合をあわせると24.2%に及びます。
いずれにしても長時間労働が常態化するとスタッフの負担が増すと、離職率の上昇につながることもあるため、無理なシフトにならないよう注意が欠かせません。
休憩は「勤務6時間で45分以上・8時間で60分以上」
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を与えなければならないと定められています。
しかし、整骨院では患者の予約が詰まっていたり、施術の合間に事務作業を行ったりするため、まとまった休憩時間を取りにくいケースもあるでしょう。
このため、以下の点に注意しながら休憩を確保するのが重要です。
- 休憩時間は「業務から完全に解放される時間」でなければならない
→ 施術合間の待機時間や受付対応可能な時間は、休憩時間にカウントされない
- 休憩時間を分割して取る場合は、スタッフの負担が軽減されるよう配慮する
→ 予約の合間に小刻みに休憩を取る場合は、合計で規定時間を満たすことが必要
休憩を適切に確保すれば、スタッフの疲労軽減やパフォーマンス向上にもつながります。
有給休暇は「継続勤務6か月かつ出勤8割以上」で必ず与える
労働基準法では、雇用開始から6か月が経過し、その間の出勤率が8割以上であれば、最低10日間の有給休暇を付与しなければならないと定められています。
また、2019年の法改正により、有給休暇が年間10日以上付与される従業員には、最低5日間の取得が義務化されました。これに違反すると、経営者に罰則(最大30万円の罰金)が科される可能性があります。
整骨院では、施術スタッフが固定の患者を担当しているケースも多いため、有給休暇を取得しづらい雰囲気が生まれがちです。
そのため事前に休暇希望を聞いて調整する計画的なシフト管理や、交代制で取得させるなどの工夫が求められます。詳しくは「整骨院の労働基準法における違反・トラブルを避けるポイント」にて解説します。
時間外労働の賃金は「2割5分以上」
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせる場合や法定休日に働かせる場合、割増賃金を支払う義務があります。
|
労働の種類 |
基本賃金の増加割合 |
|
時間外労働(残業) |
基本賃金の25%以上 |
|
休日労働(法定休日に勤務) |
基本賃金の35%以上 |
|
深夜労働(22時~翌5時) |
基本賃金の25%以上(残業と重なる場合は50%) |
整骨院では、施術時間が長引いたり、予約が詰まっていたりして残業が発生しやすいですが、こうした場合でも適切な賃金を支払わなければなりません。
また、時間外労働を行う場合は、「36協定(時間外・休日労働に関する協定)」を労働基準監督署に届け出る必要がある点にも注意しましょう。
違反すると、未払い賃金の支払い義務が生じるだけでなく、労働基準監督署の指導対象となる可能性があるため、適切な労務管理の徹底が不可欠です。「36協定」は次の項目で詳しく紹介します。
整骨院の労働基準法における違反・トラブルを避けるポイント
整骨院の労働基準法における違反・トラブルを避けるためのポイントを、6つ紹介します。
「36協定」を結んで遵守する|施術後の残務処理も要注意
先に触れた通り、整骨院では施術時間が長引いたり、患者対応のために勤務終了後もカルテ整理や後片付けをしたりする場面も多く、知らず知らずのうちに法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えてしまうケースが少なくありません。
労働基準法では、時間外労働を行う場合「36(サブロク)協定」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。36協定がない状態で残業をさせると違法となり、罰則が科される可能性があるのです。
また、施術後の事務作業や片付けが実質的に「業務」とみなされる場合、それも労働時間に含まれるため注意が必要です。適切な勤怠管理を行い、残業時間が発生する場合は36協定の範囲内に収めるようにしましょう。
厚生労働省が公表している以下の資料では、36協定届のポイントや記載例などを確認できますので、参考にしてください。
未払い残業代を防ぐために適切な勤怠管理を行う
整骨院においても、残業代未払いに関するトラブルが散見されます。
たとえば「施術の準備・片付け」「研修・勉強会」「ミーティング」などが業務時間に含まれるかどうかが曖昧になりやすく、知らないうちに未払い残業が発生しているケースも少なくありません。
適切な勤怠管理を行うために、以下の対策を取りましょう。
- タイムカードや勤怠管理システムを導入し、正確な労働時間を記録する
- 残業が必要な場合は、事前申請制にすることで無駄な残業を防ぐ
- 研修やミーティングの時間も労働時間としてカウントし、適正な賃金を支払う
未払い残業代が発覚すると、さかのぼって2年分(2020年4月以降は3年分)支払う義務が発生するため、しっかりと対策を行うことが重要です。
有給休暇が年10日以上付与する場合は「年5日取得が必須」
労働基準法の改正により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者は、最低5日間の取得が義務化されています。これは整骨院にも適用されるため、「有給を自由に取らせているから問題ない」という考え方は通用しません。
整骨院では、予約制であることから「休みが取りづらい」という現場の声もあがりがちですが、以下のような工夫で対応できます。
- 事前に有給取得計画を立てる(計画年休制度の活用)
- シフトを調整し、交代制で取得する
- 忙しい時期を避けて、閑散期にまとめて取得する
有給休暇を適切に管理し、違反とならないよう注意しましょう。
労働条件通知書(雇用契約書)を必ず交付する
労働基準法では労働条件通知書(雇用契約書)を交付することが義務付けられています。これを怠ると、トラブルが発生した際に「言った・言わない」の問題になり、院側が不利になるリスクもあります。
労働条件通知書には、最低限以下の内容を明記しましょう。
- 労働契約の期間(有期・無期)
- 就業場所・業務内容
- 労働時間・休憩・休日
- 賃金(基本給・手当・支払日)
- 退職に関する事項(解雇の条件など)
特に、試用期間や固定残業代(みなし残業)の有無などは、後からトラブルになりやすいため、明確に記載しておくのが重要ポイントです。
内容のヌケモレが心配な場合は、厚生労働省が公開している労働条件通知書を用いるのが、より確実でしょう。
1人でも労働者を雇ったら労働保険は加入必須|施術中のケガと法的責任
整骨院を経営するうえで、1人でも従業員を雇ったら「労災保険」と「雇用保険」への加入が義務となります。これを怠ると、万が一の事故や労働災害が発生した際に、院側が全額自己負担しなければなりません。
整骨院では、施術中に「患者の体を支えた際に腰を痛めた」「施術機器でケガをした」といった事故が発生する可能性があります。これらのケースは労災保険の対象となるため、適切に対応できるよう事前に加入手続きを行っておくのが重要です。
また、万が一の事故に備えて、損害賠償責任保険(施術者向け)にも加入しておけば、患者への補償トラブルも防げます。
整骨院もパワハラ・セクハラ防止対策は必須
整骨院の現場では、院長や先輩施術者からの指導が行き過ぎてパワハラとみなされるケースも生じかねません。また、患者との距離が近いため、スタッフ間だけでなく患者からのセクハラ問題にも注意が必要です。
▼整骨院で発生しやすいハラスメント例
- パワハラ:厳しい指導のつもりが「人格否定」「長時間の説教」と捉えられる
- セクハラ:スタッフ同士の不適切な発言、患者からの執拗なボディタッチやプライベートな詮索
- マタハラ:妊娠・出産を理由に不利益な扱いをする
▼防止策として整骨院が取るべき対策
- 就業規則にハラスメント禁止を明記する
- 従業員向けのハラスメント研修を実施する
- 相談窓口を設け、早期対応できる体制を整える
特に、パワハラ・セクハラ対策は、2022年4月から中小企業にも義務化されており、整骨院も例外ではありません。未然に防ぐための取り組みを徹底しましょう。
整骨院が労働基準法を遵守しつつ顧客・従業員の満足度を高めるポイント
労働基準法を遵守することは決してリスクを避けるためだけのネガティブな取り組みではありません。ここでは、整骨院が労働基準法を遵守しつつ顧客・従業員の満足度を高めるポイントを5つ、一部事例を交えながら紹介します。
シフト制の導入による柔軟な経営・運営の実現
整骨院では施術の予約状況や患者の来院時間が日によって異なるため、固定シフトではなく柔軟なシフト制を導入すれば、従業員の負担を軽減しつつ効率的な運営が可能となります。
たとえば、曜日や時間帯ごとにスタッフを分けたり、週ごとの希望シフトを取り入れたりすることで、ワークライフバランスを考慮しつつ人員配置を最適化できます。また、突発的な欠勤や予約変更にも対応しやすくなり、顧客満足度の向上にもつながります。
勤務地を固定せずにシフト制にしたことで、日曜日も診療できるようになったんです。営業日を増やすことで来院数は順調に増えていきました。
(中略)4院のうちの2院を日曜日も稼働させました。院長先生は変わらないけど、他の先生は所属の院以外にも勤務します。
引用:モアリジョブ|のぞみ整骨院グループ代表 橋口望さん
研修制度の充実化で施術に不可欠な知識とスキルを習得
施術の質を高めるためには、従業員のスキルアップが欠かせません。研修制度を整備し、解剖学や生理学といった基礎知識のほか、新しい施術技術や機器の使い方などを学べる環境を提供することで、従業員の成長を支援できます。
新人研修を充実させ早期離職を防ぎ、その後もフォローアップ研修を定期的に実施すれば施術の品質向上だけでなく、採用力の強化にもつながります。
また以下の事例では、各研修を営業時間内に実施することで、時間外労働が発生しにくい環境も実現しています。
研修には、かなり力を入れています。新入社員に対しては、入社後の1カ月間をまるまる研修期間に充てていまして、学校のような形で座学と実技のカリキュラムを細かく組んでいますし、その後も適宜フォローアップ研修を行っています。全員が対象となる研修は、営業時間内に行うのが基本です。
引用:モアリジョブ|株式会社マーサメディカル 求人担当 鈴木彩夏さん
時間外労働や休暇取得の見直しで自社の魅力や定着率を向上
整骨院では、患者対応が長引いたり施術後の事務作業が増えたりして、時間外労働が発生しやすくなります。そのため、予約管理を徹底したうえで、施術時間の適正化を図り、無駄な残業を防ぐことが重要です。
また、労働基準法に基づき、有給休暇の取得を促進すれば、従業員が働きやすい環境を整えられます。働きやすい職場環境は、スタッフの定着率を向上させ、採用面でも魅力的な要素となります。
魅力の1つとしては、働きやすさの部分です。残業が少なく、決まった時間に帰れるし、お休みもちゃんと確保されている点を魅力に感じました。そのときはまだ結婚も出産もしていなかったのですが、いずれそういうこともあるだろうと思っていたので、転職活動をする際にとくに意識して見ていたポイントでした。
引用:モアリジョブ|株式会社フレアス 直営教育支援部 技術支援課 係長/鍼灸マッサージ師 神里子さん
給与体系の見直しで採用力やモチベーションを改善
治療業界に従事している20〜30代の201人を対象にしたリジョブの調査によると、現在の給与・給与体系に対して「かなり満⾜・やや満⾜」と回答した人は38%でした。一方で「やや不満・かなり不満」と回答した人は62%であり、不満に感じている⼈の⽅が多いことが明らかとなっています。

整骨院の給与体系は、月給固定制のほか歩合制を導入するケースも見られますが、いずれにしても適正な評価基準を設けることが重要です。たとえば、売上に応じたインセンティブ制度を導入したり、技術力や経験に応じた昇給制度を設けたりすれば、従業員のモチベーション向上を期待できるでしょう。
以下の資料では、上記データのほか、「不満な理由」「理想の給与」「転職と給与の関係」といった有効かつ貴重なデータをまとめていますので、ぜひ無料ダウンロードの上、参考にしてください。
ストレスチェックの実施でメンタルヘルスを支援
施術者は長時間の立ち仕事や患者対応による精神的な負担により、ストレスを抱えやすい職業といえます。加えて職場環境や人間関係によるストレスは、業務のパフォーマンスや離職率にも影響を与えるため、メンタルヘルス対策が重要です。
労働安全衛生法の改正により、従業員50人以上の事業所では「ストレスチェック」の実施が義務化されています。
整骨院でも、従業員の健康管理の一環として、50人未満の事業所であっても自主的にストレスチェックを導入するのが望ましいでしょう。
ストレスチェックを通じて従業員の心理的負担を把握し、必要に応じて産業医やカウンセラーとの面談を実施すると、メンタルヘルスの維持・向上につながります。
また、職場内でのコミュニケーションを活性化し、ストレスを軽減できる環境づくりを進めるのも大切です。
たとえば、定期的な面談を実施し、従業員が悩みを相談しやすい雰囲気をつくる、休憩スペースを整備するなど、小さな取り組みが働きやすい職場環境の構築につながります。
まとめ
整骨院の運営において、労働基準法の遵守は従業員の働きやすさを確保し、経営の安定にもつながります。特に以下のポイントを押さえておくことが重要です。
- 労働時間と休憩の適正管理:週40時間の原則や特例を理解し、長時間労働を防ぐためのシフト管理を行う
- 有給休暇の適切な付与:6カ月以上勤務し、出勤率8割以上の従業員には最低10日の有給休暇を付与する義務がある
- 時間外労働の割増賃金の支払い:残業・休日労働・深夜労働には法定の割増率を適用し、36協定を締結する
- 勤怠管理の徹底:タイムカードや勤怠管理システムを活用し、未払い残業が発生しないよう管理する
労働基準法を遵守し、従業員の満足度を高めれば、結果的に顧客満足度の向上にもつながるでしょう。

- 執筆者情報
- 高橋祐哉(Takahashi Yuya)