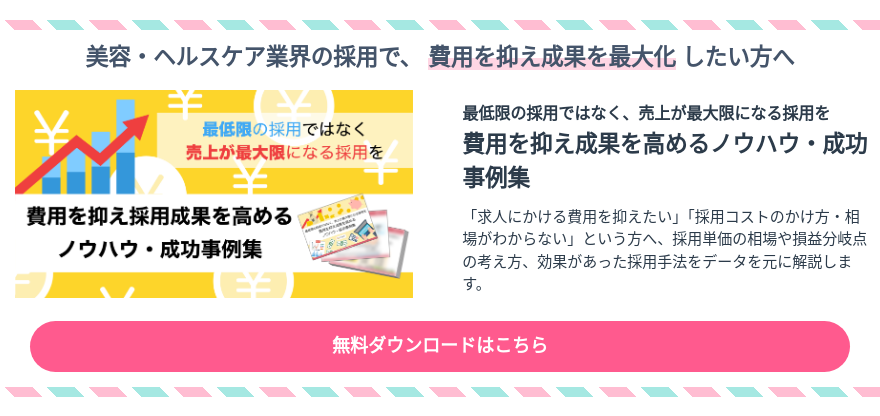「採用にかける費用を見直したい」と考えている採用担当者も多いのではないでしょうか?近年、少子高齢化や労働人口の減少で採用競争が激化しており、今後も続くと予想されています。結果として、採用単価は増加傾向です。
採用単価は、企業経営に大きな影響を及ぼします。そのため採用単価にかかるコストの見直しが必要です。本記事では採用単価とコストのバランス、職種ごとのデータをみながら改善方法を紹介します。
採用単価とは
採用にかかるコストは、適切な管理が求められます。まずは現在かかっている採用単価を把握しましょう。
以下では、採用単価の計算式や単価とコストの違いなどを解説します。
採用単価の定義と計算式
採用単価とは、1人の従業員の採用にかかる費用の合計です。たとえば同時に5人を採用する場合、かかった採用費用を人数(5人)で割った1人あたりの費用が採用単価になります。
1人あたりの採用コストの採用単価は、次の計算式で算出できます。
採用単価=(内部コスト+外部コスト)÷採用人数
採用単価を知ることにより、正確な1人あたりの採用にかかる平均コストが分かります。
採用コストとの違い
採用単価と採用コストは似ていますが、正確には違う定義になります。
- 採用単価とは1人の採用にかかる費用
- 採用コストとは採用活動にかかった費用の総額
たとえば5人の採用に500万円のコストがかかった場合と、3人の採用に360万円かかった場合では5人の採用の方がコストが高く感じるかもしれません。しかし採用単価でみれば、5人では1人の採用に100万円、3人では120万円となり後者の方がコストが高くなります。
採用コストに含まれる項目
採用コストは、社内で発生する内部費用と外部で発生する外部費用の2種類に分けられます。以下では、それぞれを具体例とあわせて紹介します。
内部費用(内部コスト)
内部費用とは、企業が人材を採用する際に、社内で発生する費用です。採用担当者は求人広告の作成、応募者との連絡、面接日程のスケジュールの作成など、業務内容は多岐にわたります。また選考や面接の人件費もかかり内部コストに大きく影響します。
|
内部費用の具体例 |
・採用担当者の人件費 ・応募者や内定者への交通費や宿泊費の支給 ・リファラル採用のインセンティブ |
企業が応募者や内定者への交通費や宿泊費の支給を一部負担、または全額負担することがあり、特に遠方から来社する場合は高額になるかもしれません。
外部費用(外部コスト)
外部費用とは、企業が人材を雇用する際に社外の業者やサービスに支払う費用です。
|
外部費用の具体例 |
・求人媒体の掲載費 ・パンフレットの制作費 ・企業説明会の費用 |
まず求人媒体の掲載は多くの求職者にリーチでき、採用活動を有利に進められます。ただ一般的な求人媒体は高額の場合があり、効果的な求人メディアの選定、予算に応じたプランの検討が必要です。
そのため、各業界に特化した求人メディアを選べば、ターゲットとなる求職者にリーチしやすく、結果としてコスト削減につながるでしょう。
次に、採用パンフレットは求職者へ企業のイメージやビジョンを明確にアピールできるツールです。パンフレット製作は目的やターゲット層、デザイン、印刷方法などが含まれ15〜80万円が相場です。
そして企業説明会は、一度に多くの求職者と直接コミュニケーションを取れる場です。また希望していない求職者にもアピールできる重要な機会です。会場費や資料作成費などを含めて数十万円かかる見込みです。
採用単価が経営に与える影響
経営において採用単価は重要な指標です。では具体的にどのような影響を与えるのでしょうか?
以下3つの観点で解説します。
採用単価は人材投資の効率性を左右する
採用単価は、人材確保にかかるコストを示すだけでなく、「人件費に見合う成果を得られているか」という投資効率の判断材料になります。採用にかけた費用と、その人材が生み出す利益とのバランスを確認することで、無駄な投資を避けられるでしょう。
また、採用単価は流動性が高く、業種や企業規模によっても大きく異なるため、継続的にモニタリングすることが重要です。
採用単価は事業フェーズに応じて変動する
事業の成長段階によって、採用単価には大きな差が生まれます。
たとえば、創業期や成長期は、優秀な人材を確保するために高い報酬や待遇を用意する必要があり、採用単価は高くなりがちです。一方で、安定期・拡大期になると組織体制が整い、採用効率が向上するため、採用単価は相対的に下がる傾向があります。
このように事業フェーズを見極め、「売上げ」「利益」「従業員1人あたり」の生産性などと連動させて採用戦略を設計することが求められます。
採用単価の高騰は財務体質にも影響する
採用単価の上昇は、企業の損益計算書(PL)や財務指標に直接影響します。採用コストは販売管理費(販管費)として計上されるため、採用単価が高まれば、営業利益率の低下を招く可能性があります。
さらに、採用した人材の離職率が高いと、再採用や教育にかかるコストも重なり、財務負担が一層増加します。採用単価だけでなく、定着率や育成コストとのバランスも含めて管理すれば、経営の安定化を図れるでしょう。
採用単価を把握するメリット
採用単価を適切に把握、管理すると経営に大きなメリットがあります。ここでは採用単価を把握するメリットを解説します。
メリット1:採用活動の「費用対効果」を見える化できる
採用単価が高額でも、長期的に大きな利益をもたらす人材なら適切な投資です。逆に採用単価が低額でも、早期退職が多ければ投資効率が悪くなります。費用対効果を把握して、適切な採用活動を行いましょう。
メリット2:業界平均や過去との比較ができる
採用単価は流動性が高く、業界や規模により変化します。定期的に自社の採用単価を業界平均や過去の数値と比較することで、現在の採用コストの適正性が分かります。また採用市場のトレンドの分析ができ、採用対策の強化につながるでしょう。
メリット3:人材の質を保つのに最適な採用単価を把握できる
個人の能力やスキル、経験は人材の質は業績に大きく影響します。一概にはいえませんが、採用単価を抑えすぎると人材の質や定着率が下がる恐れがあり、結果として教育にかけるコストが上昇する可能性があります。それを防ぐために、質を落とさない採用単価の基準を自社で構築しましょう。
採用単価の相場:業種・規模別の平均データ紹介
ここでは採用単価を検討できるように相場、業種、規模別の平均データを紹介します。
全国平均と職種別の目安
新卒採用と中途採用の全国平均は以下の通りです。
|
新卒採用 |
93.6万円 |
|
中途採用 |
103.3万円 |
新卒採用より、中途採用の方が採用単価は高めです。特に専門スキルや特殊資格の人材を獲得する場合、高額になる場合があります。
また、求人広告費の職種別の採用単価の平均は以下の通りです。
|
職種名 |
2022年 |
2023年 |
|
販売・フード・アミューズメント |
36.2万円 |
27.3万円 |
|
美容・ブライダル・ホテル・交通 |
23.8万円 |
26.4万円 |
|
医療・福祉 |
30.5万円 |
28.4万円 |
参考:マイナビ「中途採用状況調査2024年版(2023実績)」
採用者1人当たりの職種別求人広告費は平均約20万円〜30万円台で推移しています。
企業規模別・雇用形態別の目安
企業規模別の採用単価の平均は以下の通りです。
|
従業員数 |
平均 |
|
3~50名 |
86.7万円 |
|
51~300名 |
299万円 |
|
301~1000名 |
550.4万円 |
|
1001名以上 |
1290.5万円 |
参考:マイナビ「中途採用状況調査2024年版(2023実績)」
企業規模により採用単価は大きく異なります。自社にあわせた採用計画が求められます。
雇用形態別の目安の採用単価は以下の通りです。
|
新卒採用 |
93.6万円 |
|
中途採用 |
103.3万円 |
|
アルバイト・パート |
7万円 |
参考:マイナビ「就職白書2020年」
参考:マイナビバイト「マイナビバイト通信」
業種別の傾向と目安
業種別により採用単価も異なりますが、毎年増加傾向にあります。
|
業種 |
費用 |
|---|---|
|
サービス・レジャー |
438.3万円 |
|
医療・福祉・介護 |
262.8万円 |
|
不動産・建設・設備・住宅関連 |
539.2万円 |
|
公的機関 |
534.2万円 |
参考:マイナビ「中途採用状況調査2024年版(2023実績)」
採用単価が高くなってしまう要因
ここでは影響の大きい要因として考えられる3つをご紹介します。
要因1:採用チャネルの選び方と費用構造
採用チャネルとは、企業が求職者にアプローチする際に使用する手段や媒体を指します。これは就職、転職に向けて活動している求職者だけでなく、まだ具体的に活動していない潜在層も対象です。
採用チャネルは大きく3つに分けられます。
- 公募型(求人広告・企業サイト)
- 人材紹介(人材紹介会社・就職エージェント)
- ダイレクトリクルーティング(スカウト型・SNS)
採用単価が高いと感じる場合は、活用しているチャネルの実績を分析しましょう。チャネルの分析により無駄な支出が分かり、改善点が把握できます。
要因2:ポジション・職種・地域性
採用単価はポジション・職種・地域性により変動があります。
経験豊富な人材や専門スキルは、採用市場での競争が激しく採用単価が高額になります。逆に未経験歓迎のポジションや比較的採用しやすい職種は、採用単価が低くなる傾向です。
また職種ごとに異なり、需要の高い職種は高額になる可能性があります。例としてITエンジニア、企画・医療・介護関係などが挙げられ、特定の業界や企業規模によっても採用単価は変化します。
なお、採用単価は地域でも異なり、東京などの都市圏は競争が激しく採用単価が高くなる傾向です。一方、地方では採用単価が抑えられる可能性がありますが、人口減少の地域では採用ターゲットの確保が難しい場合も考えられます。
要因3:企業の知名度やブランド力
採用単価と知名度は、採用活動にも影響を及ぼします。知名度が高い企業やブランド力が高い企業は多くの求職者から注目され応募数が増えやすく、優秀な人材が集まりやすい傾向です。
一方で知名度が低い企業は、応募者を増やすために、より多くの費用をかけて求人広告を出したり、人材紹介会社を利用したりする必要があります。その結果、採用単価が高くなる傾向です。ただし、最近はSNSなど無料のプラットホームを活用して採用単価を抑えて優秀な人材を獲得している企業もあり、自社に合った採用活動をする必要があります。
採用単価を改善するための具体的な方法
高いと感じる採用コストを抑えるためにはどのような削減をすればよいでしょうか?
ここでは削減する7つのポイントを解説していきます。
1.採用チャネルの費用対効果を見直す
活用している採用チャネルにかかるコストを算出し効果測定を行います。
測定方法はそれぞれのチャネルの応募数・採用数・費用を把握し、CPA(1応募当たりの単価)やCPS(1採用あたりの単価)で評価します。また業種別に採用コストには違いがあり、把握したうえで適切な採用活動をしてください。
▼2018年度新卒採用および中途採用1人あたりの平均採用コスト
|
業種別 |
新卒採用 |
中途採用 |
|
建設業 |
69.4万円 |
97.8万円 |
|
製造業 |
69.7万円 |
102.3万円 |
|
流通業 |
67.7万円 |
55.5万円 |
|
金融業 |
84.8万円 |
58.2万円 |
|
サービス・情報業 |
78.1万円 |
86.8万円 |
参考:株式会社リクルート 就職みらい研究所「就職白書2019」
各チャネルを比較し、採用コストに対して得られる採用数や質の良さも考慮してください。また専門の業界に特化して求人媒体もあり、そちらを活用すると短時間で必要とする人材とマッチングできる可能性が高くなります。
2.コンテンツ型採用マーケティングの強化
人材不足により採用活動の難易度が上がっており、競合との差別化には職場の魅力を伝える情報発信が必要です。その方法として会社の雰囲気や働き方、社員の声などを見せるコンテンツの発信がおすすめです。
コンテンツの発信のポイントは以下になります。
- 魅力的なコンテンツの作成
企業の文化、働き方、社員の声、キャリアパスなどを伝える記事や動画制作
- 多様な配信チャネルの活用
SNSや自社サイト、求人媒体を活用します。ただの情報掲載にならないように、閲覧するユーザーを育成してファン化する「育成型リード獲得」へのチャネルに転換しましょう。
このように採用ターゲットのアプローチが強化され、採用コストの最適化と優秀な人材の確保につながります。
Londの場合、いろいろな採用媒体にも登録はしていますが、申し込みの比率は僕が運用しているInstagramが大きいです。とくに新卒採用に関しては、外部の採用媒体には掲載しておらず、Instagramと美容学校からの紹介からしか取っていません。
引用:モアリジョブ|株式会社Lond ゼネラルマネージャー/リクルーター 関根孝文さん
3.ダイレクトリクルーティングを利用する
企業が直接、求職者へアプローチする採用方法をダイレクトリクルーティングといいます。労働人口が減少し有効求人倍率が高まっている現在、有効な方法です。採用したい人材に直接アプローチできるため、攻めの採用活動が可能です。また人材紹介は採用コストが割高になる傾向ですが、比べてダイレクトリクルーティングは費用を抑えられます。
また求人ページや採用ページに、採用ターゲットが検索しそうなキーワードを配置してください。必要な内部リンクを設置すると、サイト全体の構成が整理されSEO対策になります。
昨今はパソコンよりスマートフォンからのアクセスが増えています。さまざまなデバイスでも閲覧できるようにレスポンシブデザインを取り入れることや、スマホから公式LINEへの連携もコンバージョン改善に効果が見込まれます。
求職者の人たちに出会う接点を、とにかくたくさん作りました。求人サイトやSNSはもちろん、美容学校や学生とのつながり、自社のブランディングなど数多くの手を打っています。受け身の採用ではなく、攻めの採用という感じでしょうか。
引用:モアリジョブ|OjOmano 倉田晋吾さん
4.リファラル採用をする
リファラル採用は、既存の社員や関係者から信頼できる人材を紹介してもらう採用方法です。紹介者の信頼を背景に応募者の質が高くなる傾向にあり、通常の採用よりもマッチング率が上がり定着率の向上につながるでしょう。また応募者の情報も事前に把握できるため、面接までのプロセスも早くなります。
成功させるポイントは以下になります。
- インセンティブ制度の導入
採用者1人につき10万円の報奨金などがあります。
- 社員とのコミュニケーション
社員に採用活動の目的や募集要項を共有して積極的に紹介を促します。
- 社員満足度の向上
働きやすい環境作りをして、紹介意欲を引き出します。
- 採用基準の明確化
紹介候補者の条件や期待値を具体的に示します。
リファラル採用はコスト削減だけでなく、信頼性や定着率向上につながる方法です。運用までに制度運用をしっかり精査しましょう。
5.ペルソナ設計と応募前の情報提供で歩留まりを改善する
ペルソナ設計は採用活動を円滑に行うために必要な材料です。ペルソナ設計は採用活動のターゲティングが向上し、無駄なリソースや時間を削減できます。
ペルソナ設計のポイントは以下の通りです。
- 職務経歴やスキルセット
- 価値観や志向性
- 働き方の希望(リモート勤務、柔軟な勤務時間など)
- 期待するキャリアパス
- 趣味やライフスタイル
ペルソナが決まったら求人広告に反映させましょう。それによりペルソナに合致した求職者が応募するため、選考の効率化と質の向上が見込まれます。
応募前の情報提供は、求職者が応募を決める前に企業に対する理解を深められます。企業のビジョンや求めるスキル、働き方の事例などを伝えると応募者は自分との適合性を判断しやすくなり、採用のミスマッチの減少につながります。
6.選考プロセスの効率化とオンライン化
選考プロセスの効率化は、採用活動にかかる時間やコスト削減につながります。そのためには、採用における各段階を見直す必要があり、オンライン化できる部分は切り替えましょう。選考プロセスの効率化のポイントは以下の通りです。
- 書類選考の自動化
採用管理システムを活用して、履歴書や職務経歴書の自動スクリーニングを行えば、人手不足による審査時間を短縮できます。その他業界に特化した求人媒体なら求職者の資格やスキルなどが容易に把握でき、円滑に審査できるでしょう。
- 選考フローの分析
現在の選考フローを詳細に分析し、不要な面接や書類選考があれば見直します。
- オンライン面接の活用
対面面接の代わりにビデオ会議ツールを利用すれば、交通費や会場費のコスト削減や時間効率化も可能です。またATSツールを活用すれば、応募者の情報管理、面接スケジュールの調整、応募者への連絡などを自動化・管理できます。
このように選考プロセスの効率化とオンライン化はコスト削減につながります。ただし応募者の質の維持も大切になりますので、必要に応じて対面面接と組み合わせて運用しましょう。
7.採用活動のKPI設定とPDCA運用
採用単価を管理するには、採用活動におけるKPIの設計が必須です。KPI(重要事業評価指標)は採用活動の成果や進捗を計るための指標です。KPIの設定は、採用活動の効果を把握し改善点を見つけやすくなります。
KPI設定に必要な項目は以下の通りです。
- 応募者数
- 面接率
- CPA(1応募単価)
- CTR(広告クリック率)
- 内定承諾率
- 定着率
KPIを設定したら、一定のサイクルで運用して結果を求めていきましょう。ここでは運用の基本となるPDCA運用を解説します。
- Plan(計画)
KPI設定や採用戦略や施策の立案 -
D
o(実行)
計画に基づき採用活動を実施 - Check(評価)
実績データを収集・分析し、KPIと比較
目標達成や課題点を把握 - Act(改善)
問題点や課題に対して改善策を修正・最適化
次回の採用に向けて計画を修正・最適化
このKPI設計とPDCAサイクルを繰り返すことで、成果に向けた効率化と質向上を図ります。
採用単価を削減した事例
採用単価の削減に成功した企業は、どのような施策を行っているのでしょうか。
これまで解説した方法を活用した事例をご紹介します。
事例1:リファラル採用の活用で採用単価3分の1削減
株式会社ザ・キッドは、従業員を採用の当事者として参加させて、社内外の信頼できる人脈を自社に紹介するリファラル採用を取り入れています。インセンティブは、スタイリストの紹介で入社した場合、入社して3カ月後に5万円、半年後に5万円、1年後に5万円と、小刻みに支給、また入社に至らなくてもAmazonギフトをプレゼントしています。
1年弱の取り組みで、230名が紹介活動を実施し、32名の応募があり、応募からの決定率は65.6%です。採用単価は10万円で、他チャネルの1/3になっています。
参考:マイシリーズ
事例2:採用サイトの強化で採用コスト10分の1削減
株式会社ユーティルは採用サイトの強化を通して成功した事例です。スタッフが企業のミッション・バリューについて感じている内容を、採用サイトの記事コンテンツで発信しています。その結果、インサイドセールスの職種で公開後1週間で応募があり入社が決定しました。採用コストも約10%削減できました。
参考:hypex
事例3:SNSや採用サイトの活用で採用コスト年間300万円削減
株式会社八百鮮は年間1000万円かかっていた採用コストを、SNSや採用サイトの効果的な活用により年間300万円まで削減することに成功しました。企業理念を前面に打ち出し、スタッフの入社の背景などのインタビュー記事を掲載しています。その結果、応募者の共感を獲得し、半年で12名の採用を実現しています。
参考:ノンデスク
知っておきたい採用単価とELTVとROIの関係性
採用単価を深く理解して企業を発展させるためには、ELTVとROIを理解しましょう。ここでは採用単価とELTVとROIとの関係性を解説していきます。
ELTV(従業員生涯価値)はLTVの応用
LTV(Life Time Value)とは、顧客生涯価値の略で、一人の顧客が取引開始から終了するまでの間に、企業にもたらす利益の総額を表します。一方で、ELTV(Employee Lifetime Value)とは従業員生涯価値の略で、従業員が会社に在籍している期間全体で生み出す価値の総量を表します。
採用単価とのバランスでROIを測る
ROI(Return On Investment)とは投資利益率といわれ、採用単価とのバランスが重要です。ELTVには採用のために費やした1人当たりの採用コストがマイナスの値として加算されます。結果として算出される値がプラスであれば、その従業員は採用コスト以上の価値を生み出しているといえます。
ROIは次の計算式で算出できます。
ROI = ELTV ÷ 採用単価
単価を下げすぎるリスクにも注意
低単価の採用はコスト削減には効果的ですが、リスクが伴う可能性があります。低単価での採用は以下のリスクが生じる可能性が考えられます。
- 人材の質の低下
- 離職率の増加
- 研修・育成コストの増加
- ブランドイメージの低下
- 長期的なパフォーマンスの低下
失敗しないためにもコストと人材の質や定着率のバランスを考慮し、長期的にみて採用戦略を立てましょう。
まとめ
本記事を総括すると次の通りです。
- 採用単価は経営の意思決定に直結する
- 採用単価を数値化は改善しやすい
- 採用単価 × ELTV × 定着率で考える
このように、まずは自社の採用単価を算出し現状を把握しましょう。

- 執筆者情報
- 田仲ダイ(Tanaka Dai)