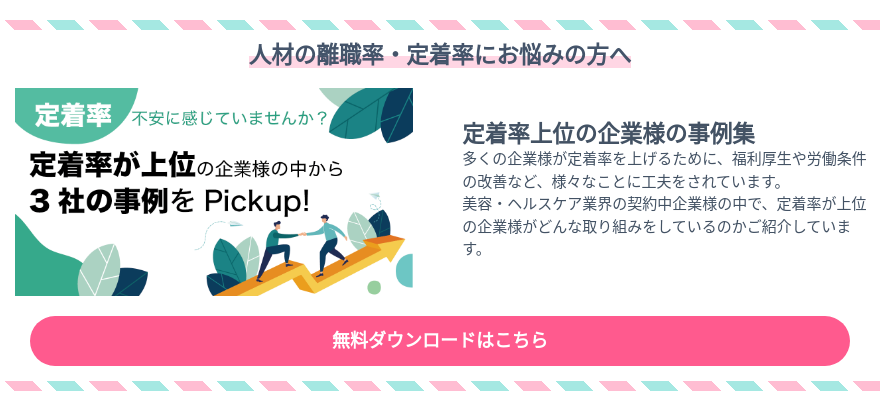定着率の計算方法がわからず悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
店舗経営や人事に関わっていると、従業員の定着率が課題となるケースも珍しくありません。定着率は、従業員がどの程度組織に在籍するかを示す指標であり、離職率の低さを表しています。
定着率を高めれば、採用・育成コストの削減と生産性向上にもつながるため、企業にとってメリットが多いです。
本記事では、定着率の計算方法を平均値を含めて解説します。定着率を高めるメリットや取り組み事例もあわせて解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
現状の定着率を計算して、より従業員が長く働きたい職場へ改善しましょう。
定着率とは
定着率とは、入社した従業員が一定期間を経過した後に、どの程度在籍しているかを示した数値です。従業員が働きやすい職場ほど定着率が高くなり、すぐに離職する職場は低くなる傾向にあります。
定着率は、組織の働きやすさを表す指標でもあり、数値が低い場合は管理体制や教育制度・報酬面を見直す必要があります。
定着率が低い場合は、従業員がすぐに離職してしまい、社内にノウハウや人材が定着せず、組織力が育ちません。さらに、新たな人材を雇用するコストや育成する手間がかかり、従業員のエンゲージメントも低下するので定着率を高める施策が必要です。
定着率は、企業の「ブラック度」を測る指標としても用いられており、数値が低いほどブラック企業と判断されやすくなります。反対に数値が高ければ、長く働きやすい優良なホワイト企業と見なされます。
定着率と離職率の違い
定着率と離職率は混同されやすい用語ですが、下記のような違いがあります。
|
違い |
定着率 |
離職率 |
|
意味 |
一定期間、在籍している従業員の割合 |
一定期間で離職した従業員の割合 |
|
数値が高い場合 |
従業員が長く在籍しやすい |
従業員が早期に辞めやすい |
|
数値が低い場合 |
従業員が早期に辞めやすい |
従業員が辞めにくい |
定着率と離職率は、正負の関係です。定着率が高いと離職率が低くなり、定着率が低いと離職率が高くなる仕組みです。
定着率と離職率を足すと100%になるので、下記の計算方法で離職率を求められます。
|
離職率(%)=(一定期間中の離職人数÷元の従業員数)×100 |
|
離職率(%)=100-定着率 |
定着率がわかれば、簡単に離職率を計算できます。定着率が不明な場合は、一定期間中に離職した人数を元の従業員数で割って、割合を求めましょう。
定着率の計算方法
定着率の計算方法は、次のとおりです。
|
定着率(%)=(一定期間後の在籍従業員数÷一定期間開始時に入社した従業員数)×100 |
|
定着率(%)=100-離職率 |
たとえば、50人の従業員が入社して、1年後に40人が在籍している場合の定着率は80%です。なお、正確な数値を求めるには、一定期間中に途中入社した従業員を在籍従業員数に含めないよう注意してください。途中入社した従業員を含む正確な定着率を求めたい場合は、次の計算方法を実施しましょう。
|
定着率(%)=(X年前の入社人数-X年間の離職人数)÷X年前の入社人数×100 |
なお、定着率が80%の場合は離職率が20%になり、どちらかを求めれば双方の数値を計算できます。定着率を計算する際は、対象期間を絞り込んで何人の従業員が残っているか割合を求めれば、数値を算出できます。
算出タイミング
定着率を算出するタイミングは、年単位が一般的です。多くの企業は、有価証券報告書など年単位で売上げや従業員数を算出するため、年度始まりの4月に定着率を計算するケースが多いです。企業によっては、年度始まりを1月や10月などの決算期に合わせて定着率を計算するケースもあります。
なお、新入社員の定着率を算出する場合などは、3年・5年・10年などの長期間で計算するケースも珍しくありません。人材の入れ替わりが激しい業種や職種では、1年より短期間で定着率を算出することもあり、企業の採用戦略や求めたい理由によって対象期間が変動します。
定着率の現状
自社の定着率を計算する前に、国内の平均値を把握しておきましょう。平均値を比較すれば、自社の定着率が客観的に高いのか低いのか判断できます。
定着率の現状を把握するために、下記の項目ごとの平均値を確認しておきましょう。
- 日本全体の平均
- 就労形態別
- 産業別
- 新卒者
なお、定着率の現状を確認するために、厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概況」を参考に数値を計算しています。参考元の調査結果には定着率が記載されていないので、「100-離職率=定着率」の計算方法で定着率を算出しました。
日本全体の平均
厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、日本全体の定着率平均値は84.6%でした。
▼日本全体の入職率・転職率の推移

令和元年の定着率が84.4%、令和2年以降も85%前後であることをふまえると、コロナ禍の影響は少ない様子です。ただし、令和5年の離職率・入職率は近年のなかでは右肩上がりに増えており、人材の流動が活発化しています。。
なお、男女別の推移では令和5年度の定着率は、男性15.7%・女性12.7%でした。
▼性別入職率・転職率の推移

例年女性のほうが男性より入職率・転職率が高い傾向にあり、結婚や育児による離職やパートタイムでの入職などが数値差に関係していると推察されます。
就労形態別
厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、正規・非正規雇用それぞれの定着率は次のとおりでした。
▼就労形態別入職率・転職率の推移

|
就労形態 |
定着率 |
離職率 |
|
正規雇用(一般) |
87.9% |
12.1% |
|
非正規雇用(パート) |
76.2% |
23.8% |
正規雇用と非正規雇用では、離職率が約2倍ほど違います。正規雇用は長期雇用が前提の就業形態であるのに対して、非正規雇用は短期間で辞めるケースも多く、離職率が高い傾向にあります。
産業別
厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、産業別の定着率は次のとおりでした。
▼産業別入職率・転職率(一般)
.jpg?width=667&height=452&name=4_%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%88%A5%E5%85%A5%E8%81%B7%E7%8E%87%E3%83%BB%E8%BB%A2%E8%81%B7%E7%8E%87(%E4%B8%80%E8%88%AC).jpg)
▼産業別入職率・転職率(パート)
.jpg?width=602&height=403&name=5_%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%88%A5%E5%85%A5%E8%81%B7%E7%8E%87%E3%83%BB%E8%BB%A2%E8%81%B7%E7%8E%87(%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88).jpg)
▼産業別の定着率(100-離職率)
|
就業形態 |
正規雇用(一般) |
非正規雇用(パート) |
|
産業計 |
87.9% |
76.2% |
|
建設業 |
89.7% |
94.4% |
|
製造業 |
91.3% |
83.7% |
|
電気・ガス・熱供給・水道業 |
90.6% |
73.9% |
|
宿泊業、飲食サービス業 |
81.8% |
69.1% |
|
生活関連サービス業、娯楽業 |
79.2% |
63.1% |
正規・非正規雇用ともに建設業や製造業は定着率が高く、サービス業全般は離職率が高い傾向にあります。業種や職種によって離職率は異なるので、自社の定着率を計算する際は業界の平均値と比較することが大切です。
新卒者
厚生労働省の「新規学卒就職者の離職状況」によると、学歴別の離職率・定着率は次のとおりでした。
▼学歴別の離職率


|
令和2年度新卒者の離職状況 |
定着率 |
離職率 |
|
中卒 |
69.0% |
31.0% |
|
高卒 |
85.0% |
15.0% |
|
短大卒 |
83.8% |
16.2% |
|
大卒 |
89.4% |
10.6% |
新卒者の離職率は例年中卒ほど高く、大卒は低い傾向にあります。大卒は将来的な管理職や幹部候補として採用されるケースも多く、基本給や待遇が中卒や高卒より高いため、定着率が安定しているのでしょう。
また、大卒は大手企業に入社しているケースも多く、安定した職場で長期的に働きたい人材が多いことも定着率が高い要因のひとつです。
定着率を高めるメリット
定着率が重視される理由は、高めることで次のようなメリットが得られるからです。
- 採用・教育のコスト削減
- 従業員の意欲向上
- 生産性および業績の向上
- 採用力の向上
- サービス品質や顧客満足度の向上
定着率の高さは、従業員にとって働きやすく、長期的に就業したい職場である証拠です。そのため、定着率を高めれば従業員が長く就業し、組織力を強化できます。
それぞれのメリットを確認して、定着率を高めるべきか検討してください。
採用・教育のコスト削減
定着率を高めれば、新しい人材を採用する必要がなくなり、採用・教育のコストを削減できます。離職率が高い場合は、労働力を確保するために新しい人材を採用・教育しなければなりません。
人材の採用には、数十万〜数百万円のコストがかかるため、企業にとって大きな出費です。就職みらい研究所が公表した「就職白書2020」によると、人材採用にかかる平均コストは次のとおりでした。
|
採用手法 |
人材1人あたりの平均採用コスト |
|
新卒採用 |
93.6万円 |
|
中途採用 |
103.3万円 |
人材募集にかかる広告費や人件費、セミナーや説明会の開催費など、さまざまな採用コストが発生します。さらに人材を育成するためにかかる費用も多種多様であり、すぐに離職されては高額な採用・教育コストが無駄になってしまうのです。
定着率を高めれば、採用・教育コストを削減するだけでなく、優秀な人材の流出も防げるので組織力の強化にもつながります。競合優位性を確保するためにも、定着率を高める施策が必要です。
従業員の意欲向上
定着率が低い職場では、従業員のモチベーションも低下してしまいます。仲の良い同僚や先輩社員が離職すると、「自分もこの職場に残ってよいのか」と転職を悩んでしまうのです。
一方で定着率を高めれば、従業員の意欲を向上させて社内エンゲージメントも高められるので、離職防止につながります。厚生労働省が実施した「働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する調査」によると、同僚の離転職が少ない職場ほど、働きやすさや働きがいを感じやすい結果が判明しました。
▼同僚の離転職が少ない場合の働きやすさ・働きがい

従業員の意欲が向上すれば、離職を防止するだけでなく生産性や利益の向上につながります。従業員同士のつながりを強化し、組織力の向上を図るためにも定着率を高めましょう。
生産性および業績の向上
定着率が向上すれば、従業員のモチベーションが高まり、生産性と業績も向上します。なぜなら、定着率が高い職場は、熟練の知識・スキルを持った従業員が増え、1人ひとりがモチベーションを高く持って仕事に取り組むからです。
新入社員よりベテラン社員のほうが労働生産性が高く、モチベーションの高い従業員は生産性が高く、結果的に組織の業績向上に貢献するのです。厚生労働省が実施した「ワーク・エンゲイジメントと個人の労働生産性について」によると、エンゲージメントスコアが高い従業員ほど労働生産性の向上を実感しています。
▼ワーク・エンゲージメント・スコアと個人の労働生産性に関する認識

企業が従業員を大切に扱えば、従業員のモチベーションが向上して、生産性・業績もアップします。業績を向上させたい企業は、定着率を高めて従業員の労働生産性を向上させましょう。
採用力の向上
定着率が高い企業は、ホワイト企業のイメージがつき、採用力が向上します。離職率の高い職場は、従業員がすぐに辞めるイメージからブラック企業の印象が強く、採用難に陥る可能性があります。
対して、定着率が高い職場は、居心地が良く働きやすい環境だと判断され、応募率が高まるのです。競合他社より定着率が高い場合は、同業種の企業と比較して長く働きやすい印象がつくので、優秀な人材を採用できるチャンスが拡がります。
優秀な人材を確保して組織力の向上につなげるために、定着率を高めましょう。
サービス品質や顧客満足度の向上
従業員満足度・顧客満足度・企業収益が作用し合ってポジティブな影響を与えることを、「サービス・プロフィット・チェーン」と呼び、定着率を高めればこれら3つの要素を好循環できます。
▼サービス・プロフィット・チェーンのイメージ図

定着率が高い状態は、従業員満足度も高く顧客満足度を向上させられます。結果として、業績向上にもつながるため、組織内外のどちらにも良い影響を与えるのです。
顧客からすると、定期的に担当者が変わる取引先より、同じ担当者が長く対応してくれるほうが安心して注文・依頼できます。新入社員よりベテラン社員のほうがサービス品質が高く、顧客満足度も向上させられるため、企業イメージやブランドに良い影響を与えられます。
定着率を上げる方法
定着率を上げる方法として、下記の施策が効果的です。
- 採用のミスマッチをなくす
- 評価制度をつくり、運用・見直しを行う
- 柔軟な働き方の制度を作る
- 社内のコミュニケーションを円滑にする
- 給与・福利厚生を充実させる
- キャリアサポートを充実させる
それぞれ具体的な施策を紹介するので、定着率を向上させる際の参考にしてください。
採用のミスマッチをなくす
そもそも採用する人材にミスマッチがあれば、入社後に離職される可能性が高まります。定着率を高めるには、採用のミスマッチをなくす必要があり、採用計画の見直しが求められます。
採用のミスマッチをなくすには、下記のような施策が効果的です。
- 採用するペルソナを明確化する
- SNSやホームページを通じた情報発信
- セミナーや説明会の開催
- インターンシップの活用
採用担当者ごとに採用基準があいまいにならないよう、ペルソナを明確化しておくことが大切です。さらに、SNSやホームページを通じて職場の雰囲気や企業風土を発信し、求人票にも詳細な情報を記載しておきましょう。
応募率がどれだけ高くても、離職率が高いと採用・教育コストが無駄に増えるだけです。セミナーや説明会、インターンシップを開催して、採用担当者と求職者双方が入社前に適性を判断できれば、採用後のミスマッチを防げます。
評価制度をつくり、運用・見直しを行う
従業員のモチベーションが低下すると離職率の増加につながるので、評価制度の改善と適切な運用が必要です。評価基準が不透明な状態では、従業員が正当に評価されているかわからず、企業に対して不信感を抱く原因になります。
評価制度をつくり、運用・見直しを行う際には、下記のような施策を導入しましょう。
- 社内表彰制度
- インセンティブ制度
- 昇給・昇格基準の明確化
- 公平な評価基準の公表
- 等級ごとの給料額を公表
社内表彰制度やインセンティブ制度のように、評価が目に見える報酬で還元されると、従業員のモチベーションを向上させられます。さらに、昇給・昇格基準や等級ごとの給料基準、公平な評価基準を公表しておけば、人事評価に対する不信感を払拭できます。
従業員が納得できる形で評価すれば、他社と現状の待遇を客観的に比較できるので、転職を思いとどまらせることが可能です。
柔軟な働き方の制度を作る
ワークライフバランスが重要視されている現代で、柔軟な働き方ができる職場は、従業員にとって働きやすいものです。厚生労働省が公表した「ワーク・ライフ・バランス推進のための取組と離職率の関係性」に関する調査では、下記のような施策に取り組んだ企業は、離職率が低下しました。
▼離職率が低下した企業における各施策の実施率

- アンケート調査の実施などによる実態面の把握
- 業務プロセスの見直し(組織間・従業員間の業務配分のムラを解消するなど)
- 休暇・急な早退等が必要な際、従業員間で融通し合えるよう、十分な人員数を配置
- 休暇が必要な際、従業員間で融通し合えるよう、中期的な休暇予定を従業員間で見える化する
- 休暇・急な早退等を申請しやすい職場雰囲気の醸成
- 有給休暇を取得する必要のある下限を設定する
- 残業時間に上限を設定する
- まとまった日数での休暇取得の奨励
- ノー残業日の設定
- 長時間勤務労働者やその上司等に対する指導・助言
- 残業させず、有給休暇取得を促す上司が評価されるような仕組みを導入する
- 労働時間管理、有給休暇取得、健康確保に係る、管理職向けの研修・意識啓発
- 労働時間管理、有給休暇取得、健康確保に係る、非管理職向けの研修・意識啓発
- 経営トップからの呼び掛けや経営戦略化による意識啓発
- 部門間の取組状況の見える化・情報共有
- 短時間勤務制度やフレックスタイム制度等、より柔軟な労働時間制度を導入・推進
- 時間単位、半日単位など柔軟な有給取得制度の導入・推進
- テレワーク等の柔軟な働き方の導入・推進
- 育児休業制度や介護休業制度の利用促進
- 企業内に託児所を併設
テレワーク制度やフレックスタイム制度、育児休暇制度に介護休暇制度などワークライフバランスを実現させる取り組みは、離職率の防止につながります。休暇制度や柔軟な働き方だけでなく、管理者からの呼びかけや業務プロセスの見直しなど、従業員が働きやすい職場づくりにつながる施策は離職を防止できます。
社内のコミュニケーションを円滑にする
社内のコミュニケーションを円滑化すれば、従業員同士のつながりが強化され、定着率を向上させられます。従業員同士の関係性が希薄な場合は、転職や離職を検討した際に現在の職場に留まる理由が少なく、そのまま離職してしまう可能性が高いです。
しかし、従業員同士の関係性が強固な場合は、離職を検討した際も相談できる同僚や先輩社員が多く、離職を踏みとどまる可能性があります。
社内のコミュニケーションを活性化すると、相談や協力を求めた際に気軽な声かけができるため、精神的に追い込まれる心配がありません。厚生労働省が実施した「雇用管理が働きやすさに与える影響について」の調査では、職場の人間関係やコミュニケーションを円滑化している職場ほど、働きやすいと回答されていました。
▼働きやすい企業における実施率

- 人事評価に関する公正性・納得性の向上
- 本人の希望を踏まえた配属、配置転換
- 業務遂行に伴う裁量権の拡大
- 優秀な人材の抜擢・登用
- 優秀な人材の正社員への登用
- いわゆる正社員と限定正社員との間での相互転換の柔軟化
- 能力・成果等に見合った昇進や賃金アップ
- 能力開発機会の充実や従業員の自己啓発への支援
- 労働時間の短縮や働き方の柔軟化
- 採用時に職務内容を文書で明確化
- 長時間労働対策やメンタルヘルス対策
- 有給休暇の取得促進
- 職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化
- 仕事と育児との両立支援
- 仕事と介護との両立支援
- 仕事と病気治療との両立支援
- 育児・介護・病気治療等により離職された方への復職支援
- 従業員間の不合理な待遇格差の解消(男女間、正規・非正規間など)
- 経営戦略情報、部門・職場での目標の共有化、浸透促進
- 副業・兼業の推進
なお、社内のコミュニケーションを円滑化する施策として、下記が効果的です。
- 社内SNSやチャットツールの導入
- 社内報による情報共有
- サンクスカードの導入
- 1on1ミーティングの実施
- 社内イベントやオリエンテーションの開催
- 社員食堂やカフェの設立
- ミーティングスペースの開放
- シャッフルランチの実施
- フリーアドレスの実施
部署間を超えて多種多様な人材とコミュニケーションを取れる環境づくりが、定着率の向上につながります。誰とでも気軽にコミュニケーションを取れるアットホームな職場であれば、従業員が働きやすく定着率が高まります。
給与・福利厚生を充実させる
定着率を高めるには、従業員は他の企業ではなく「この職場で働き続けたい」と思える待遇を提示する方法が効果的です。給与・福利厚生を充実させれば、転職や離職を思いとどまり、現職で働き続ける理由を増やせます。
大手転職サイトのdodaが2023年7月~2024年6月の転職者に調査した「転職理由ランキング」によると、転職理由として「給与が低い・昇給が見込めない」がもっとも多かったです。

給与や福利厚生が充実していると、不満があっても「他の職場より待遇が良いから」と我慢できます。さらに、給与や福利厚生はやりがいやライフワークバランスの実現につながるので、従業員のモチベーションを向上させられます。
給与・福利厚生を充実させるための施策として、下記が効果的です。
- インセンティブ制度の導入
- 定期昇給制度の見直し
- 役職手当の見直し
- 給与体系の透明化
- 独自の健康支援制度の導入
- 健康診断・人間ドックの支援
- 育児・介護支援制度の導入
- 住宅手当・家賃補助の充実
- リモートワークやフレックスタイム制度の導入
従業員満足度調査を実施し、意見を反映して給与・福利厚生の見直しを行い、定着率を向上させましょう。
キャリアサポートを充実させる
法政大学と労働政策研究・研修機構の共同研究「企業調査による人材定着率の新卒・中途比較」によると、キャリアサポートが充実している企業ほど、離職率が低い傾向にあります。
▼各キャリア支援制度の実施状況と離職率
|
新卒に実施した施策/離職率 |
5%未満 |
5~10%未満 |
10~20%未満 |
20~30%未満 |
30%以上 |
|
インターンシップ制度 |
42.86% |
22.69% |
20.17% |
6.72% |
7.56% |
|
メンター制度 |
53.92% |
23.53% |
16.67% |
3.92% |
1.96% |
|
キャリアアドバイザー制度 |
60.61% |
18.18% |
15.15% |
3.03% |
3.03% |
|
MBO(目標管理制度) |
49.66% |
23.45% |
17.24% |
5.52% |
4.14% |
|
360度評価 |
50.00% |
20.59% |
16.18% |
11.76% |
1.47% |
従業員は、「この企業にいても将来性がない」と判断した場合に離職を検討するケースがあります。企業の業績や給与だけでなく、自身の成長を実感できない場合は、他社へ転職する従業員も少なくありません。
そのため、下記のようなキャリアサポートを充実させて、離職防止に努めましょう。
- キャリアコンサルティング面談
- メンター制度
- 社内キャリアセミナー
- スキルアップ研修
- 異動希望制度
- 社外留学・研修派遣
- キャリア自己申告制度
- 社内公募制度
- キャリアチェンジ制度
- 資格取得支援制度
定着率向上への取り組み事例
定着率向上を目指すなら、他社の成功事例を参考にしましょう。
なおここで紹介する4つの事例は、厚生労働省が人材確保対策に関するページに掲載の事例集で紹介されていたものを参考にしました。同ページに掲載の事例集は定期的に更新されるため、最新のものを参照するのもおすすめです。
ホテル業:J社
J社は、宿泊業・飲食業特有の入職率・離職率の高さが課題でした。従業員の早期離職と重要な労働力であったフリーターの減少に伴い、人手不足に悩まされていました。
そこで、入社した人材をいかに定着させるかを注力し、入社3カ月以内の離職を防止する目的でメンター制度を導入しています。ホテルはシフト業がメインなので、固定のメンターを配置することが難しく、時間帯の合う先輩社員が新人のメンターになる仕組みで、コミュニケーションを活性化させました。
さらに継続的な支援を行うために、入社から3カ月間は交換レポートを導入し、自己評価や研修内容に対するフィードバックを実施したのです。
メンター制度を導入してから、先輩社員の意識が改革され、新人社員だけでなく既存社員への関心が強くなりました。ホテル内の雰囲気が明るくなっただけでなく、離職率の低下にもつながった成功事例です。
外食産業:F社
F社では、20代若手社員と店舗管理者の離職が課題でした。離職率の低下を目指すため、誰しもがやりがいを持って働けるように、人事処遇を改変しました。
まずは社員群制度を改変し、働き手の選択肢を増やし、個人のライフスタイルに合わせた働き方を実現しています。次に賃金制度と評価制度を見直すことで待遇面を改善し、適切な評価を受けられる人事体制を整えることで、従業員が納得して働ける職場づくりを目指しました。
役職が増設され昇格基準が明確になったことで、仕事への意欲を高めた従業員が増えて離職率を低下させました。また、待遇面や働き方の選択肢を改変したことで、定着率が向上しています。
一般小売業:E社
E社では、新卒者の定着率が低く、職場環境の改善や働き方改革の導入を検討していました。まず改善した点は、部下と上司の双方にとって負担となっていた、目標設定・評価シートの簡略化です。
目標設定・評価シートの記載項目が多く、本来であれば面談に費やしたい時間を確保できず、上下間のコミュニケーションが希薄になっていました。そこでシートの内容を簡略化し、上司と部下がコミュニケーションを取る機会を確保し、職場の活性化を目指しました。
煩雑化する事務作業に追われて、形骸化していた目標設定・評価を、上司と部下がコミュニケーションを取りながら見つめ直すことで、従業員間の意識が改革されています。また、適切にコミュニケーションを取る時間が確保されたことにより、新卒者のケアや育成を適切に行うよう職場風土が改善されました。
レジャー業界:H社
H社は、テーマパークで働くアルバイトを確保できず、人材不足に悩まされていました。特にイベント時の人材不足は深刻で、地理的な条件も相まって、募集をかけても簡単には人材を確保できなかったのです。
そこで、人材確保の方法を見直し、下記の施策を導入しました。
- 登録型アルバイト制度
- 全国的インターンシップ制度
登録型アルバイト制度では、毎週のように開催されるイベントに向けて、スポットで働ける制度です。週末だけ働きたい学生や主婦を募集し、イベント時の労働力を確保しました。
地元を中心に募集していたインターン生は、対象を全国に拡大し、テーマパークの繁忙期である冬休みや夏休みには寮で住み込みながら働いてもらっています。
2つの取り組みにより、イベント時の労働力を確保し、インターンの受け入れ数が大幅に増えました。
まとめ
定着率の計算方法に関するノウハウは、次のとおりです。
- 「(一定期間後の在籍従業員数÷一定期間開始時に入社した従業員数)×100」か「100-離職率」で定着率を求められる
- 定着率の平均値は、業種や職種によって異なる
- 定着率が高いと、生産性・企業イメージ・顧客満足度が向上するためメリットが多い
- 定着率を高めるには、採用や評価制度・従業員の待遇に働き方などを見直す必要がある
- 従業員に長く働きたいと思わせる組織づくりが定着率向上につながる
本記事で紹介した、定着率を高める方法と取り組み事例を参考に、従業員と顧客から愛される組織づくりを行いましょう。

- 執筆者情報
- 山藤 寛司(Santo Hiroshi)