近年、多くの業界で「人手不足」が深刻化しており、「採用活動をしても人が集まらない」「従業員の離職が続いている」「どう対策すればいいのか分からない」という声が後を絶ちません。
厚生労働省の調査 によれば、全業種平均有効求人倍率は約1.2倍(令和7年6月時点)。求職者1人に対して1件以上の求人がある状態で、労働力確保が容易ではないことは明らかです。
こうした人手不足の背景には、少子高齢化による生産年齢人口の減少、都市部への人口集中、離職率の上昇、業務効率の悪化など複数の要因が重なっています。
そこで本記事では、人手不足の現状と要因を整理したうえで、企業が取るべき具体的な対策や事例をわかりやすく紹介します。今後の採用・定着戦略を見直すヒントを得られるので、ぜひ参考にしてください。
人手不足問題とは
そもそも人手不足問題とは、企業の求人数が求職者数を上回り、労働力の確保が難しくなる状況を指します。これは単に一部の業種に限らず、社会全体の構造的な課題として深刻化している問題です。
2025年8月時点で、全業種の有効求人倍率は約1.2倍で求人数が求職者数を上回る状況です。さらにコロナ禍以降は企業活動も活発になり、人手不足が以前よりも顕著になりました。
業種によっては、人手不足が進んで採用が難航している企業も見られるようです。ここでは、人手不足問題について詳しく解説します。
全業種の有効求人倍率は約1.2倍
厚生労働省の調査 によると、令和6年以降は有効求人倍率が約1.2〜1.3倍の間で推移しています。

微減は見られるものの依然として求職者数よりも求人数が多い状況は続いており、求人倍率が1.0倍を下回っていた平成24年度よりも人手不足になりやすい状況といえます。
人手不足の傾向の強い業種
厚生労働省が公開した有効求人倍率 をもとに、人手不足の傾向が強い業種の具体例を挙げると次のとおりです。ここでは厚生労働省による職業の分類上で、有効求人倍率が2.0倍以上を示したものを挙げています(令和7年6月時点)。
|
業種 |
有効求人倍率 |
|---|---|
|
保安職業従事者(警察官や消防士 等) |
5.84倍 |
|
建設・採掘従事者 |
4.87倍 |
|
サービス職業従事者 |
2.67倍 |
|
輸送・機械運転従事者 |
2.08倍 |
とりわけ「建設・採掘従事者」のうち、特に有効求人倍率が高いのは「建設躯体工事従事者(7.59倍)」「土木作業従事者(5.76倍)」でした。
同様に「サービス職業従事者」の場合は、美容師や調理師などが属する「生活衛生サービス職業従事者(3.05倍)」、看護助手や看護補助者が属する「保健医療サービス職業従事者(27.9倍)」などが高い倍率を示しています。
人手不足の要因は?
労働政策研究・研修機構の調査によると、人材獲得が困難になっていることが最大の人手不足の要因でした。
▼人手が不足している理由

そのほかの要因として、従業員の離職や業務効率の悪さに関連する要因が人手不足につながっているようです。上記のデータをもとに、人手不足の要因について重要なものから順に説明します。
要因1:即戦力人材の採用が難しい
採用の難しさについては、とくに即戦力となるキャリア人材の採用難易度が高いようです。 BIZREACHの調査 によると、キャリア採用の難易度が上がっていると回答している会社が7割以上に上ることがわかりました。

即戦力人材を採用できないと、必要なポジションの欠員をすぐに埋めることができず、人手不足状態を招きます。また教育前提のポテンシャル採用に切り替えるにしても、人員が不足するなかで教育体制を整えるのは容易ではありません。
要因2:離職率が高い
厚生労働省の調査 によると、離職率の高い業界は宿泊業や飲食業、美容師やエステなどの生活関連サービス業です。
▼産業別入職率・離職率(一般労働者)
.png?width=875&height=566&name=4_%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%88%A5%E5%85%A5%E8%81%B7%E7%8E%87%E3%83%BB%E9%9B%A2%E8%81%B7%E7%8E%87(%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85).png)
同調査 によると、前職を辞めた個人的理由の上位は以下の通りであり、給与や職場の人間関係、労働時間・休日等を含む労働条件の悪さなどが要因として挙げられています。
▼前職を辞めた個人的理由上位5つ:男女別(※その他を除く)
|
順位 |
男性 |
割合 |
女性 |
割合 |
|
1 |
給与等収入が少なかった |
10.1% |
労働時間、休日等の労働条件が悪かった |
12.8% |
|
2 |
職場の人間関係が好ましくなかった |
9.0% |
職場の人間関係が好ましくなかった |
11.7% |
|
3 |
労働時間、休日等の労働条件が悪かった |
8.6% |
給与等収入が少なかった |
8.3% |
|
4 |
会社の将来が不安だった |
7.4% |
会社の将来が不安だった |
5.1% |
|
5 |
仕事の内容に興味をもてなかった |
4.4% |
能力・個性・資格を活かせなかった |
3.7% |
※「 厚生労働省|令和6年雇用動向調査結果の概況 」を基に作成
要因3:業務効率が悪い
ITやAI、機械設備の導入が進まないと業務効率が悪化して、人手不足を実感しやすくなります。
総務省が4か国の企業を対象にデジタル化の取組状況について調査したところ、日本ではデジタル化に関連する取り組みを未実施と回答した割合が約50%(※)となり、海外に比べて推進が遅れていることが明らかとなりました。
※「実施していない、今後実施を検討(10.6%)」、「実施していない、今後も予定なし(39.7%)」の合計
▼デジタル化の取組状況(各国比較)
.png?width=792&height=365&name=5_%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%8C%96%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84%E7%8A%B6%E6%B3%81(%E5%90%84%E5%9B%BD%E6%AF%94%E8%BC%83).png)
また、業務効率が悪いと従業員の負担拡大や長時間労働につながる恐れがあります。従業員の待遇面にも関わるため、業務効率の是正は人手不足を解消するうえで重要な取り組みのひとつといえるでしょう。
政府が提唱する「働き方改革」の一環としても、業務効率の改善が勧められています。
企業にとっては、長時間労働を是正し、処遇の改善を図るためには、業務効率の改善を行うとともに、省力化投資を増加させる必要があり、働き方改革はそうした動きを促進することが期待される。同時に、労働者にとっては、処遇の改善や長時間労働の是正は働くこと自体のモチベーションを高めるとともに、自己啓発を含めた能力開発を行うインセンティブを高めると考えられる。
要因4:少子高齢化・労働力人口の減少
人手不足の背景には、少子高齢化と労働力人口の減少という避けられない構造的な問題があります。
厚生労働省「高齢社会白書」 によると、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年の8,716万人をピークに減少が続き、2024年には7,373万人まで減少しました。さらに、2030年には7,076万人、2050年には5,540万人程度にまで縮小すると推計されています。
▼生産年齢人口等の推移

このように働く世代そのものの減少が進むなか、各企業は採用可能な母数自体が年々減少するという現実に直面しています。とくに地方や中小企業では、若年層の都市部流出や高齢化が重なり、人材確保が一層困難な状況です。
企業としては、こうした状況を踏まえて自社で行える対策や工夫により、人手不足を予防・解消しなければなりません。
人手不足への代表的な対策方法と取り組み方
人手不足への代表的な対策について次の3つを紹介します。
- スタッフの採用率を上げる
- スタッフの離職率を下げる
- 業務の効率化を図る
それぞれについて具体的な取り組み方を解説します。
対策1:スタッフの採用率を上げる
スタッフの採用率を上げるためには、まずは採用ターゲットを集客して、必要な人材の応募につなげるようにすることが大切です。ここでは、採用率を上げるためのポイントを解説します。人材採用を成功させるための方法について、さらに詳しく知りたい場合は、次の記事も参考にしてください。
採用方法を検討する
まずは自社に適した採用方法を選定して、求める人材をなるべく多く集められるようにしましょう。
利用者数で考えると、求人情報サイトは有効な選択肢のひとつです。 リクルートの調査 によると、求職者が利用する情報源は求人情報サイトが最も多い結果でした。
▼最近1年間に仕事を探すときに、どのような情報源を利用しましたか

採用数を増やすためには、まずは求職者の多くが利用する媒体を利用して求職者にアプローチし、応募者数を増やすことを目指しましょう。
さらに人材の質を重視して、自社によりマッチした人材を集めたい場合は、「特化型求人サイト」がおすすめです。
特化型求人サイトは、特定の分野に集中してアプローチすることを目的にしているため、サイトを利用する求職者も高い技術力を備えている傾向にあります。加えて、企業側も求職者側も同じ業界・分野に属するためマッチングが成立しやすいのです。
実際に、美容・リラクゼーション分野で働く専門人材は、美容系専門の特化型求人サイトを一般の求人サイトよりも優先して利用する傾向にあります。その傾向は、「(株)リクルート ホットペッパービューティーアカデミー 美容就業実態調査2025 」からもわかります。
▼転職時に用いた仕事の探し方

求職者のニーズを理解する
マイナビのキャリアリサーチLabの調査によると、ノルマがきつそうな会社は避けられる傾向にあります。
▼行きたくない会社

逆に考えると、ノルマがきつくない職場は求職者のニーズに合致する可能性があります。ノルマを設けていない場合は、それを求職者にアピールするとよいでしょう。もしくは個人のノルマではなく、チームで売上げを作る社風であることもよいアピールポイントになります。
ノルマを設定すると、顧客との信頼やスタッフ間の人間関係の悪化につながると考えている経営者もいます。ノルマを設けないと良好な人間関係を築くことにつながり、それが求職者に対してアピールできるポイントになるかもしれません。
うちのお店ではスタッフに物販のノルマも課しておらず、基本的にはノーセールスです。これはスタッフの負担削減の意味もありますが、お客さまからみたときに、あのスタッフが良かった、悪かったという印象をなくしたいからなんです。みんなが同じサービスを提供できるというスタンスを大切にしています。
引用: モアリジョブ |3arrows株式会社 代表取締役 今井 基成さん
日々のサロンワークでは売上ノルマを課さないことも重要です。スタッフ同士でお客さまを奪い合うことにつながり、セラピスト間がギスギスすることでサロン全体の空気感が悪くなりますからね。
引用: モアリジョブ |『リラクゼーションマキ』オーナー 青木満希子さん
スタッフにも売上ノルマは課さず、提案や意見があれば伝えやすい環境を意識的に作っていて。今はオープン当初から誰ひとり欠けることなくこのサロンで働いてくれています。
引用: モアリジョブ |「facial & body care salon lampo」オーナーセラピスト 横澤美穂さん
また、1990年代後半から2010年生まれのZ世代については、ワークライフバランスを重視する傾向にあります。若年層を採用したい場合は、Z世代のニーズをつかむことも大切です。Z世代の採用については、次の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
対策2:スタッフの離職率を下げる
スタッフの離職率を下げるために、まずは従業員が仕事を辞める理由を確認しましょう。先に紹介した 厚生労働省の調査 によると、前職を辞めた個人的理由の上位5つは以下の通りでした。
▼前職を辞めた個人的理由上位5つ:男女別(※その他を除く)
|
順位 |
男性 |
割合 |
女性 |
割合 |
|
1 |
給与等収入が少なかった |
10.1% |
労働時間、休日等の労働条件が悪かった |
12.8% |
|
2 |
職場の人間関係が好ましくなかった |
9.0% |
職場の人間関係が好ましくなかった |
11.7% |
|
3 |
労働時間、休日等の労働条件が悪かった |
8.6% |
給与等収入が少なかった |
8.3% |
|
4 |
会社の将来が不安だった |
7.4% |
会社の将来が不安だった |
5.1% |
|
5 |
仕事の内容に興味をもてなかった |
4.4% |
能力・個性・資格を活かせなかった |
3.7% |
※「 厚生労働省|令和6年雇用動向調査結果の概況 」を基に作成
男女ともに給与が少ないことや人間関係が好ましくないこと、労働時間および休日といった労働条件に納得できないこと、会社の将来が不安なことで仕事を辞めるケースが共通して多いです。
それらに次いで、仕事の内容に興味がもてないことや能力や資格を活かせないなどの、仕事の配分や人事評価に関わる項目が仕事を辞める理由につながっています。
こうした理由をカバーできるような対策を講じれば、離職率が減少し、人材不足の予防・解消を実現可能です。
以下では、厚生労働省のデータをもとに、離職率を下げるための対策を紹介します。
労働条件の改善
労働条件のなかには給与や労働時間、休日などが含まれます。求職者にあった労働条件へと改善できる場合は、取り組みやすいものから実行するとよいでしょう。
たとえば給与アップが難しい場合は、就業時間を減らすように工夫するのもおすすめです。なぜなら、就業時間は休職者の企業選びに大きな影響を与えるからです。
エン・ジャパンの調査によると、残業の有無や平均時間が企業選びに影響すると答えた求職者が8割以上に上りました。
▼転職活動をする上で、残業の有無や平均時間等は、企業選びにどの程度影響しますか?

労働時間を短縮するための工夫として、選べる働き方制度を導入するのもおすすめです。リジョブ提供の資料でも実例が紹介されているので、参考にしてください。
以上に紹介されているように、働き方を選べると結婚や出産、妊娠、子育てなどのライフイベントで働き方を変えざるおえない既存スタッフの離職を防げます。
求職者へのアピールになるだけではなく、既存スタッフの引き止めにも有効な点は魅力です。
人間関係の改善
株式会社ビズヒッツの調査によると、職場の人間関係でネックになりやすいのは上司や同僚との関係です。
職場内の人間関係をよくするためには、スタッフ同士で食事に行くような雰囲気を作り、積極的にコミュニケーションをとることもひとつの手段です。
先輩と後輩の間でコミュニケーションを取る時間が減っていることも理由のひとつだと思います。私が若手の頃は、先輩によく飲みに連れていってもらい、仕事やプライベートの相談をしていました。今は、若手が飲みたがらないこともあるかもしれませんが、上手にコミュニケーションを取れない先輩も増えていると思います
引用: モアリジョブ |ヘアサロン『日と木』オーナー 梅津貴央さん
このサロンは先輩・後輩関わらず仲が良く、営業終わりにみんなでご飯に行くことも多いです。僕もそういうときは毎回断らないし、断りたいと思ったこともありません。先輩たちがフレンドリーにしてくれるので、昔ほど食事の場での礼儀は厳しくないですし、最低限の「気配り」ができれば大丈夫。
引用: モアリジョブ |美容室『GARDEN W.』 トップアシスタント 中村大海さん
リーダープログラムを作って、上司の部下に対する接し方の改善に取り組む事例もあります。
管理職向けにオリジナルのリーダープログラムを用意しています。私がこれまで勉強したコーチングの内容や、幼児教育のメソッドなども取り入れたオリジナルのものです。人間が成長する過程を理論的に理解し、現場で実践を含め3ヶ月に渡って学んでいきます。
引用: モアリジョブ |ネイルサロン「NAILsGUSH」「NAIL MAFIA」オーナー 木下さとこさん
能力評価の適正化
パーソルキャリア株式会社 の調査 によると、会社の評価によりモチベーションが下がった原因は成果と報酬が見合っていなかったことが51.3%と最も多い結果でした。他にも、評価基準の不透明さや上司に対する不満も従業員にネガティブな印象を与えています。

能力評価の適正化を進める場合はこうした不満点をカバーし、明確かつ客観的な評価基準から成り立つ評価制度を整備すれば、離職者の数を減らせるでしょう。
また、従業員数が数名程度の少ない店舗の場合は、店舗内で働くすべてのスタッフを同じ基準で評価するよりも、個別に面談してスタッフごとに評価基準を設けるのがおすすめです。
各店長と社長がしっかり面談をして、その各店長の課題っていうのをお互いに確認して、その課題を克服するために、この半年はこれとこれとこれをやろうと決めて、それに対して評価をしてあげる。全然それでいいと思いますね。
引用:【ネットラジオ】第32回 『従業員10人で接骨院を3店舗経営...|JOHSHIN PARTNERS
個別の評価基準を設けることで、従業員が評価基準を満たすための行動を取りやすくなり、高い評価につながります。高く評価されると従業員が自分の承認欲求を満たせるため、能力評価に不満を抱えにくくなるでしょう。
対策3:業務の効率化を図る
業務の効率化を図るためには、業務量を減らしたり、業務内容を標準化したりして誰にでも取り組めるようにするとよいでしょう。
業務量を減らす施策としては、ITシステムの導入が考えられます。一方で業務の標準化については、業務フローのマニュアル化や未経験者が働ける環境の整備などが考えられます。
ITシステムの導入
日本企業のデジタル化に関する遅れは先に示した通りですが、 中小企業基盤整備機構の調査 によると、DXに対する取り組み姿勢は前向きな傾向を示しています。具体的には、2023年と2024年を比較すると「既に取り組んでいる」「取組みを検討している」と答えた企業の割合が増加すると同時に、「取り組む予定はない」と答えた企業は減少しています。
▼DXの取組状況(n=1,000 単一回答)

たとえば、売上げや在庫情報を一元管理できるポスレジの導入や、店舗端末の入力情報をリアルタイムにスタッフ間で共有できるようなイントラネットの整備などが考えられます。
ポスレジを導入して売り上げを日次で把握。書類はドロップボックスで共有し、イントラネットを整備して情報網も一括管理。全店舗の予約状況はパソコンで把握できるようにしました。そして月次決算を正確に出すところまで精度を高め、パソコン1台あれば施術以外の仕事はすべてこなせる環境を整えたんです。
引用: モアリジョブ |美容室「Garland」マネージャー 真木 遊さん
さらに教育システムにもITを取り入れて、新人教育を効率化して既存スタッフにかかる負担を軽減するのもおすすめです。
教える側も教わる側も、効率がよくなることで結果時短にもつながっていると思います。このカリキュラム動画はアプリで見られるように作っていて、閲覧できる最大人数は30人くらいの設定。アシスタントだけが見られるシステムです。カットやパーマなどのコンテンツが各種あり、分かりやすくテロップを入れたりしながら解説しています。基本の技術なのでこれをベースにみんなが同じものを習得していく。多店舗展開になっていくと、教え方や内容にズレが出がちなのでその対策にもなっていくかなと思います。
引用:モアリジョブ
その他にも、顧客管理で扱う「氏名や住所、電話番号、予約状況、購入履歴」などの情報を一元管理できるツールを取り入れると従業員の業務負担を減らせるでしょう。
業務フローのマニュアル化
業務フローをマニュアル化する際は、写真や挿絵を盛り込んでわかりやすくすることが大切です。また作成後に、実際にマニュアル通りに業務を進め、さらに良いやり方がある場合は改善を加えると、さらなる業務の効率化につながります。
マニュアルがあると未経験者を雇っても、早めに戦力にしやすい点も魅力です。未経験者を雇うと、雇える人材の幅が広がるので、人手不足を解消しやすくなります。
日々の中での先輩からのサポートはしっかりしていますし、レコードブック共通のマニュアルもあるので、機能訓練が未経験でも一定の指導ができるようになっています。
引用: モアリジョブ |リハビリ型デイサービス『レコードブック八千代台』 運動指導員 渡部悟史さん
マニュアルをマスターすれば、未経験者でも95%のリピート率が見込めるコツが分かるようにしました。「本当?」と思われるかもしれませんが、実際にエステ未経験だったアイリストの方にマニュアルを元に勉強いただいた結果、研修後にはリピート率95%を達成しているんですよ。
引用: モアリジョブ |エステサロン経営者 佐々木沙織さん
教育を充実させる
未経験者を採用して即戦力として働いてもらう手段として、教育の充実も上げられます。
スタッフの教育に関しては、美容師にとって大切な技術や知識といった約30の項目があり、それらを全て数値化し、スタッフ内で順位付けをして自分の足りないところが可視化される仕組みになっています。
引用: モアリジョブ |株式会社オニカム代表 槙野光昭さん
入社後は最短1年でスタイリストデビューできるよう、独自のカリキュラムを組んでいます。これは「ALBUMアカデミー」と呼ばれ、週3日はアカデミーのレッスン、残りの2日は配属店舗での実践といった形式が取られています。実践を重視し徹底的に無駄を省いた教育制度が、これまでの常識では考えられないスピード感のデビューを可能にしています。
引用: モアリジョブ |美容室『ALBUM GINZA』店長 野出貴弘さん
教育制度を整えるためには、教育を受けた従業員を評価する仕組み作りや教育者の養成が欠かせません。
自社で教育制度を整えようとすると、スタッフにかかる負担が大きくなる可能性があります。さらにノウハウも持ち合わせていないため、教育制度自体がうまく機能しないリスクもあるのです。そのため、資金を投入して教育制度を外部委託するケースもあります。
外部委託をする場合は、人材開発支援助成金に申請して助成金を得るのもひとつの手段です。教育に資金を投入する余裕がない場合は、積極的に活用するとよいでしょう。人材開発支援助成金の詳細については、次の記事をご覧ください。
対策4:人材確保の裾野を広げる取り組みを行う
少子高齢化による労働力不足に対応するためには、「働く人の層」を広げる発想が欠かせません。以下では、具体的な取り組みを紹介します。
女性・主婦層の就労支援
産休・育休取得の徹底や、復帰後は保育園などの送り迎えができるように時短勤務が可能です。また、小学3年生までの子どもがいるスタッフには、1人当たり月1万円の手当も支給し、育児中の収入面の不安もできる限り取り除いています。
実際、弊社のスタッフは女性が8割を占めていて、子育てしながら働く方も多くいるのですが、直近5年間で育休復帰率はほぼ100%です。
引用: モアリジョブ |「BRIDGE」代表取締役 大川正博さん
シニア人材の再雇用・活用
シニア層の再雇用・活用は、人手不足の緩和や解消につながるだけでなく、積み重ねてきた知見や業務経験の継承を可能にし、若手育成や現場の安定にも寄与します。
また 高年齢者雇用安定法においても、定年後も一定年齢まで働きたい高年齢者の雇用確保が義務づけられています。
具体的には、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的としており、事業主は「65歳までの雇用機会を確保する義務」に加え、「70歳までの就業機会を確保する努力義務」があります。

こうした法律に準拠しつつも上手く活用し、自社の人手不足問題を解消に導きましょう。
外国人労働者の受け入れ
近年、日本では技能実習制度、特定技能制度、在留資格制度などを通じて外国人労働者の受け入れを進めています。
主に人手不足が顕著な介護・建設・宿泊業などで受け入れが拡大するなか、美容業界での事例もみられます。
ヘアサロン「タヤ(TAYA)」を運営する田谷は4月、日本初となる3人の外国人美容師(中国人2人・韓国人1人)を採用した。3人は国内の美容学校を卒業後、日本での美容師免許を取得。4月から池袋、吉祥寺、銀座それぞれのサロンに配属され、接客に携わっている。
引用: WWDJAPAN
外国人を受け入れる際には、在留資格の確認、雇用契約の明確化、日本語教育やオリエンテーションの提供、住居・生活支援、文化ギャップへの配慮などが不可欠です。これらを支えるべく、 公的な制度も整備 されています。
障がい者の雇用
障がい者雇用は法制度に支えられており、日本では 障害者雇用促進法 により、一定規模以上の企業に対して障がい者の雇用義務が課されています。厚生労働省が定める 雇用率制度 や 特例子会社制度 を活用すれば、障がい者が働きやすい職場環境を整備できます。
また、「 障害者就業・生活支援センター 」や「 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) 」などが支援・助成を行っており、制度を活用できるケースが多数あります。
障がいを持つ人材は、得意分野で高いパフォーマンスを発揮する可能性があり、多様性推進と企業の社会的価値を高める観点からも意義があります。
Kさんの業務は、店舗内の清掃や洗濯、お手入れ後に使用する冷やしたタオルの準備である。忙しい時期は冷したタオルがすぐになくなるが、Kさんがいる日は常に補充をしてくれるので社員が在庫を意識せずに接客に集中することができる。また、清掃においても社員の目が届かない細かい部分まで積極的に掃除を行ってくれており、店舗の床はいつもピカピカである。
人手不足の解消には「採用」の見直しが不可欠
人手不足の解消には、人手を確保するための「採用」に課題がないかを見直すことも非常に大切です。たとえば「採用ターゲットが曖昧」「求人を出しても応募が来ない」「入社しても定着しない」と感じた経験はないでしょうか。
リジョブが提供する無料資料「採用成功のための必須チェックポイント」では、採用を成功に導くための4つの観点をわかりやすく整理し、改善の具体策や成功事例も紹介しています。
- 採用ターゲット設定
- 給与相場の把握
- 求人サイト選定
- スカウト活用
「今の採用手法で効果が出ていない」「何から見直せばいいか分からない」と感じている方は、まずこのチェックリストで自社の採用状況を客観的に見直すことから始めてみてください。
関連リンク
まとめ
本記事を総括すると次のとおりです。
- コロナ禍以降は人手不足と感じる会社が増えており、半数以上の会社が人手不足に悩んでいる
- 人手不足の要因としては、スタッフ採用の難しさや離職率の高さ、業務効率の悪さなどが考えられる
- 業務の効率化を図ったり、働くための環境や条件を整えたりすることで、スタッフが離職しないようにすることが大切
人手不足対策には、さまざまな手段が考えられます。自社がどのような理由で人手不足に陥っているのかを分析して、効率的に解決を図りましょう。
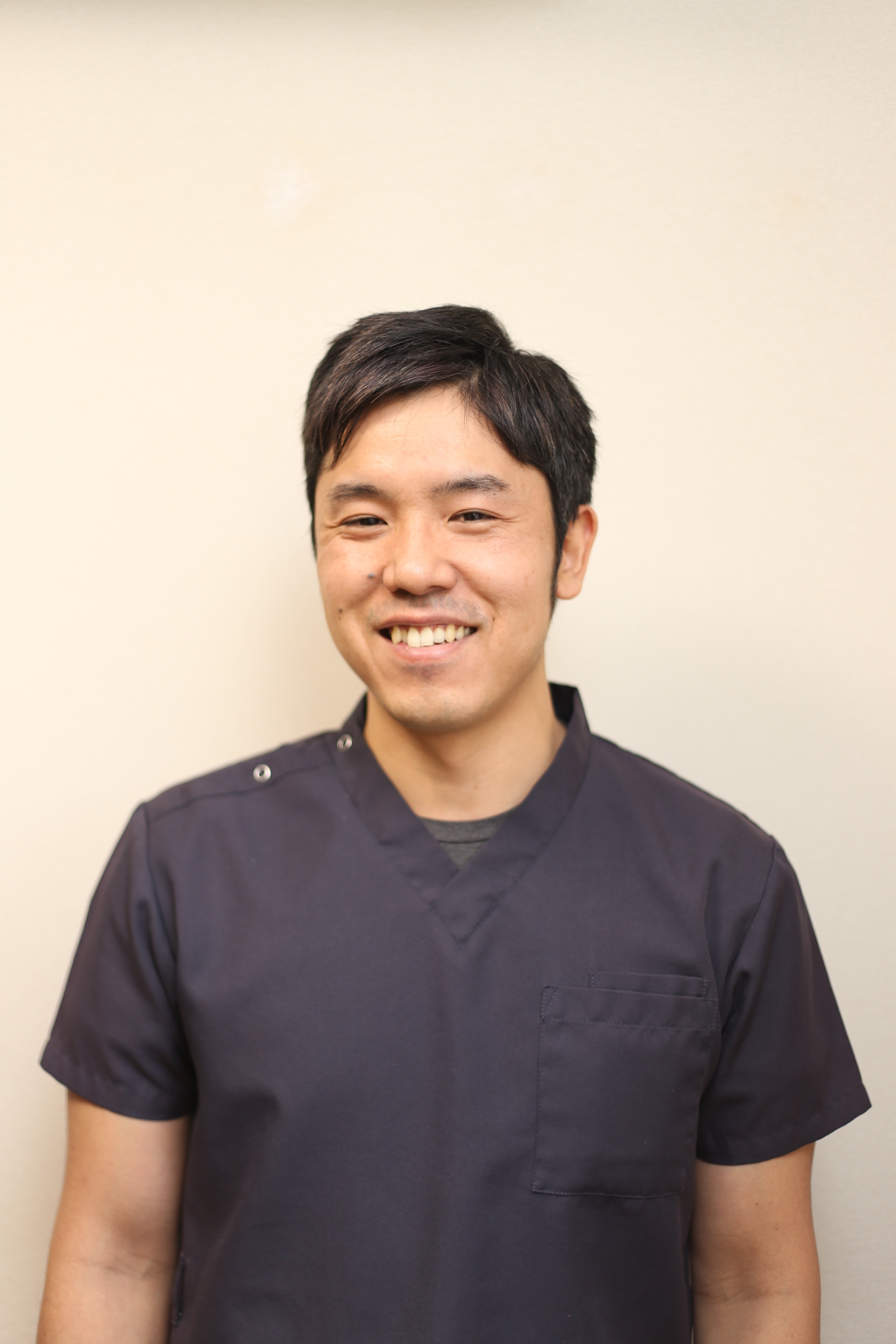
- 執筆者情報
- 東 大輔(Higashi Daisuke)
