現在の日本では、人手不足問題が深刻化しています。例えば現在注目を集める課題として「2024年問題」が挙げられます。
2024年問題とは、時間外労働における上限規制の適用に伴い懸念される人手不足問題です。建設業と物流業で2024年4月から同規制が実施されたため「2024年問題」と呼ばれており、今後も構造的な問題として深刻化する可能性があります。
また美容業界も慢性的な人手不足問題に陥る事業者が多い業界です。最近では、その解決手段として外国人美容師を雇う美容室もみられます。
ヘアサロン「タヤ(TAYA)」を運営する田谷は4月、日本初となる3人の外国人美容師(中国人2人・韓国人1人)を採用した。3人は国内の美容学校を卒業後、日本での美容師免許を取得。4月から池袋、吉祥寺、銀座それぞれのサロンに配属され、接客に携わっている。
引用:WWDJAPAN
こうした事例は一例にすぎず、人手不足は今や幅広い分野で共通する深刻な課題です。
では、なぜこれほど多くの企業が人材確保に苦しんでいるのでしょうか。そして実際に人手不足を乗り越えた企業には、どのような工夫や成功事例があるのでしょうか。
本記事では、人手不足の背景や原因を整理するとともに、実際に人手不足の解消に成功した事例11選を紹介します。さらに、企業が取り組める具体的な人手不足対策についても解説しますので、自社の課題解決にぜひ役立ててください。
人手不足の企業が増えている原因
人手不足の企業が増えている主な原因として、人材のミスマッチと労働人口の減少が挙げられます。
求職者が希望する仕事内容と企業が求める人材のミスマッチ
構造的失業が発生していることが、日本で人手不足の企業が増えている原因の1つと考えられています。
企業が人手不足の状況にあるといえる。このような状況では、失業は主に職探しや再就職に時間が掛かることによる摩擦的失業や、求人と求職の条件が一致しないことによって生じる構造的失業で占められていると考えられる。
引用:中小企業白書
構造的失業とは、雇用主が労働者に求める条件と、失業者の持つスキルや求める労働条件でミスマッチが起こることで失業者が多くなっている状況です。雇用主が労働者に求める条件項目として、スキルや年齢、学歴、勤務地などが挙げられます。
構造的失業によってもたらされる人手不足の特徴は、人手が不足する業界がある一方で、人手が余る業界も出てくることです。
厚生労働省が発表したデータによると、令和7年6月の有効求人倍率が高い業種と低い業種の差が激しいことがわかります。
【有効求人倍率が高い業種の例】
- 保安職業従事者 5.84倍
- 建設・採掘従事者 4.87倍
- サービス職業従事者 2.67倍
- 輸送・機械運転従事者 2.08倍
【有効求人倍率が低い業種の例】
- 事務従事者 0.39倍
- 運搬・清掃・包装等従事者 0.67倍
有効求人倍率が高いほど、1人の求職者に対する求人の数が多いことになります。一方で有効求人倍率が1.0倍を下回った場合は、求人に対して求職者の数が余っている状態です。
昨今はDX化による業務効率化が進んでおり、業務の機械化を進めやすい職種は人手が余りやすいといわれています。
一方で機械化の難しい職種は、人手不足を機械やAIで補えないため、職務の遂行に必要な専門スキルを持った人材が必要です。人材不足が労働市場に直接影響を与えやすいため、人手不足になりやすいと考えられます。
みずほ総合研究所調査本部の上里啓氏は、次のように述べています。
専門的な技術が必要な職業の求人倍率が全般的に高い一方、IT化や機械による労働代替が進めやすいて職業の求人倍率は低くなっている
引用:東洋経済
以上から考えると、教育訓練の実施でスキルのギャップを埋めて構造的失業を解消することが、特定の業種に偏った人手不足を解消することにつながるでしょう。実際に政府でもリスキリングを促進して、企業のニーズと求職者のスキルをマッチさせることが重要であるとの見解を示しています。
成長分野で求められるスキルニーズに合うように訓練メニューを見直していくことに加えて、主体的な能力開発を支援することを目的に、企業ニーズに合った訓練を受講する個人に費用を補助するなど、労働者のリスキリングへの支援を強化することが重要
引用:内閣府
企業が個人のスキルをアップを図り自社の人的資源として活用するためには、教育制度の充実が欠かせません。人材開発支援助成金を活用すると、公的なサポートを受けながら教育制度の充実を図れます。人材開発支援助成金については、次の記事で解説しているので参考にしてください。
労働人口の減少
労働力調査によると、日本の労働力人口は横ばいの状態が続いており、2022年は前年に比べ減少しました。
▼労働力人口の推移
また、みずほ銀行が発表した将来の見通しでは、今後労働力人口が減少すると予想されています。
以上から現在すでに労働力人口の減少が始まっており、今後も減り続ける可能性があります。
次に、労働力人口の男女差を見ていきましょう。労働力調査で男女別の労働力人口推移をみると、男性の労働力人口が減少している一方で、女性の労働力人口は伸びています。
▼労働力人口の推移(男女別)
現在は、働く女性の増加が労働力を下支えする要因の1つになっているようです。女性の働きやすい職場づくりが、人手不足を解消する1つの要素になると考えられます。
実際に、従来は男性が主体となって働いていた職種でも、人手不足解消の手段として女性の積極採用が進んでいます。
「女性には無理だ」と思われていた職場で女性にさせてみたら問題なくできるケースがほとんどだったそうです。
(中略)
調査した職場の多くは、経営トップの判断で女性採用が開始されていました。経営層がそう決断した理由は、人手不足や優秀な人材の確保のためです。労働市場の逼迫(ひっぱく)が、従来女性が参入できていなかった職場でも、男女の雇用機会均等化を推し進めたとも言えます。
引用:朝日新聞
人手不足が顕著な業界
現在、人手不足が顕著な業界は建設業や運輸業、サービス業などのブルーカラーが目立ちます。厚生労働省が調査した令和4年上半期のデータをもとに、人手不足が特に顕著な業界を深刻度が高い順番に紹介すると次のとおりです。
|
業界 |
欠員率 |
|
運輸業・郵便業 |
3.8% |
|
宿泊業・飲食サービス業 |
3.8% |
|
建設業 |
3.6% |
|
サービス業(他に分類されないもの) |
3.5% |
|
医療・福祉 |
2.9% |
|
鉱業・ 採石業・砂利採取業 |
2.6% |
|
不動産業・物品・賃貸業 |
2.6% |
|
生活関連サービス業・娯楽業 |
2.5% |
人手不足の状況や要因は、業界ごとに異なります。例えば理美容業が属する生活関連サービス業では、売上の減少よりも人手不足が原因で倒産する企業が増えています。そのため集客だけではなく、スタッフの確保に力を入れることが店舗を存続させる上で重要です。
このように、自社の属する業界における人手不足問題の特徴を踏まえて対策を講じることが大切です。次の記事では、業界ごとの人手不足問題について詳しく解説しています。
求人に応募が来ない企業におすすめの人手不足対策
人手不足をカバーしたい場合、まずは自社の求める人材の採用にコミットすることが基本です。自社にマッチした人材を採用できると、採用した人材が離職する確率が低くなり、再び人手不足に陥るリスクを抑えられます。
採用に関する基本的なノウハウはこちらの記事にまとめていますので、ぜひご覧ください。
そのうえで人材が不足する場合は、以下で紹介するような現在の日本社会の時流に沿った対策を検討してみましょう。
▼求人に応募が来ない企業におすすめの人手不足対策(分野別)
.png?width=792&height=513&name=%E6%B1%82%E4%BA%BA%E3%81%AB%E5%BF%9C%E5%8B%9F%E3%81%8C%E6%9D%A5%E3%81%AA%E3%81%84%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%81%AE%E4%BA%BA%E6%89%8B%E4%B8%8D%E8%B6%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96(%E5%88%86%E9%87%8E%E5%88%A5).png)
未経験者を募集する
現在、異業種・異職種で転職する人が増加傾向にあります。リクルートの調査によると、2017年以降は異業種・異職種で転職する人の割合が35%を超えています。
以上を考えると、未経験者を積極的に募集して異業種・異職種での転職希望者を採用すると、人手不足の解消につながります。
未経験者を採用するためには、マニュアルの整備や教育制度の充実が欠かせません。エステサロンのなかには、マニュアルを整備して未経験者が働ける環境を整えた事例があります。
弊社は「技術」「接客」「肌について」、3つのマニュアルを用意しています。これらは全て私の15年ほどの美容業経験をベースに作成しています。
総ページ数は200ページ超えとかなりボリュームがあり、読み解くのに時間がかかるのですが(笑)。マニュアルをマスターすれば、未経験者でも95%のリピート率が見込めるコツが分かるようにしました。「本当?」と思われるかもしれませんが、実際にエステ未経験だったアイリストの方にマニュアルを元に勉強いただいた結果、研修後にはリピート率95%を達成しているんですよ。
引用:モアリジョブ|ハーブピーリング専門店「エミルカ EMILUCA」 代表 佐々木沙織さん
教育制度については、入社前の内定者に店舗で練習してもらい、早く即戦力として働ける人材へと育つように工夫する事例があります。
内定者には入社前からお店に来て練習してもらっているんです。つまり、内定を出してから学校を卒業するまでの間に研修期間を設けるわけです。入社後すぐに即戦力になってくれるので双方が時間を有意義に使えますし、このシステムが一番理にかなっていて、もうずっとこのスタイルでやってきました。
引用:モアリジョブ|ボリュームラッシュ専門店「Fast Lash」 オーナー 錦織桃さん
政府も教育制度を整えるためのさまざまな助成金を準備しているので、未経験者を採用できる環境を整えるために積極的に活用するとよいでしょう。
例えば、教育制度を整える際には、人材開発支援助成金を活用できます。人材開発助成金を活用するためには、職業能力開発計画を立てて、計画に沿って職業訓練を実施する必要があります。詳細については次の記事で解説していますので、ご覧ください。
女性を積極的に採用する
現在、男性を中心に採用している場合、これからは女性の採用も進めることで人材不足の解消につながります。
現在は、以前に比べて子どもを持った女性が職業を持つことにポジティブな意見を持つ人の割合が増加傾向です。出産後に働くことに前向きな姿勢を示す女性も増えているため、以前に比べて女性を採用しやすい状況にあると考えられます。
男女共同参画局の調べによると、「(女性は)子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」と考える男女の割合が増加傾向です。
また若年層を中心に、子育てや家事は男女で協力して行うという考え方が一般的になっていることも、女性が仕事を続けやすくなった要因の1つと考えられます。
共働きであれば、お互いに仕事とプライベートの時間は限られるはず。どちらかだけが分担するという意味が分からない。女性だから家事をするという時代はとっくの昔に終わっているはず。(女性・40代/青森)
夫婦共働きが基本な世の中だと思います。子どもがいるかどうかや、夫婦の仕事の帰宅時間なども影響するかもしれませんが、基本的には誰がこれをやるべき、というのはもはやないと思います。(男性・30代/静岡)
引用:PR TIMES|株式会社ネクストレベル
以上のように結婚や出産を期に仕事を辞める社会から、結婚や出産後も女性が働き続ける社会へと変化しているといえます。社会の変化に合わせて女性の働きやすい職場環境を整えることが、人手不足の解消につながるでしょう。美容業界でも女性の働きやすい職場を目指す企業が多く、例えば次のような事例があります。
家庭を持っても、子どもがいても夢を諦めたくない。やりたいことは全部やりたい。うちではそれを「フルキャリ」と呼んでいるのですが、まさに令和の女性の働き方だと思うんです。
(中略)
オールフレックス制で、土日は自由に休んでOK。その代わりスタッフ一人でもお店を回せるように、サロンの営業時間を10〜18時にしています。もし、閉店時間を20時にしてしまうとスタッフは2人必要になりますよね。だから、スタッフの働き方を守るために雇用側が先に労働環境を変えることにしました。
出勤退勤時間や有給などは社長の私には一切申請しなくてOK。時間と休日の管理をやめ、社員同士で調整してもらうようにしました。
引用:モアリジョブ|オーガニックサロン「ORGANIC MOTHER LIFE」 代表 坂田まことさん
Umineko美容室では、子供の急な発熱での欠勤にも対応できる体制が整っています。お客様への連絡は責任もってさせていただくのですが、その際、別のスタッフでもよいとおっしゃる方にはご変更していただきます。この場合は、実際に施術をしたスタッフの売り上げになるので、欠勤するスタッフも替わりを務めるスタッフも、お互い気持ちよく助け合えるシステムになっていると思います。
引用:モアリジョブ|Umineko美容室 美容師 釜屋洋子さん
シニア層を積極的に採用する
64歳未満の日本の人口が減少するなか、65歳以上の人口が増加することを考えると、シニア層の積極採用は人手不足を解消するための有効手段の1つになると考えられます。
中小企業庁の資料によると、64歳以下の人口が減少するため、2000年以降の人口は全体的に減少傾向です。
一方で、65歳以上の人口は2040年まで増加傾向を示すことが予想されています。
※中小企業庁の資料をもとに、65歳以上の人口推移を計算してグラフ化
64歳以下の労働力人口が減少するなかで労働力を確保するためには、65歳以上のシニア層の雇用が欠かせません。
実際に労働力調査によると、2022年における65歳以上の就業率は25.2%に達しているので、シニア層の4人に1人が就労していることになります。2012年は19.5%だったことから、10年間で就業するシニア層が約5%増加しています。
シニア層を積極的に採用する具体例として、繊維工業を営む「高木綱業株式会社」の事例が挙げられます。この企業では、高度なスキルを持った人材の不足が課題でした。
そこで、既に技術を有する既存社員を再雇用して長期的に活躍してもらえる体制を構築。定年の年齢を60歳に設定していましたが、本人が希望する場合は、退職後に再雇用契約を結ぶことにしました。
再雇用者は週3日勤務や短時間勤務を選べるようにし、自分のペースで働いてもらえるように雇用条件を整えることで、シニア人材が安心して働ける職場づくりに成功しました
再雇用制度、柔軟な働き方、時間外労働削減、容易な有給休暇取得を可能にしたことにより、シニア人材自身も安心して働き続けられるようになり、業務に打ち込めるようになった。
将来の中核人材の育成も同時に進めていくため、シニア人材から社内の若手社員に対する技術指導等も積極的に行われるようになった。
シニア人材の再雇用に関する、社内における理解と協力体制の構築もできた。
引用:経済産業省 ミラサポPLUS |高木綱業株式会社(繊維工業)
外国人労働者を採用する
人手不足の深刻化に伴い、日本国内の労働力だけでは採用が追いつかない業種が増えています。その解決策として注目されているのが「外国人労働者の採用」です。
事実として日本における外国人労働者数は増加傾向にあり、 内閣府の資料 によると、2023年10月末時点で外国人労働者数が約 205万人に達し、全雇用者の約 3.4%を占めるまでに拡大しています。
例えば、技能実習生や特定技能制度を活用した外国籍人材の受け入れに加え、専門スキルや語学力を持つ高度外国人材の採用が広がっています。特にITエンジニア、製造業、介護、飲食といった分野では、海外人材の導入が現場の生産性維持に直結する事例が数多く見られます。
採用にあたっては、在留資格や労務管理体制の整備が不可欠であり、受け入れ企業側が多文化共生を意識した環境を整えることも重要です。具体的には、マニュアルや制度の多言語化、生活支援体制の充実などを行うことで、長期的な定着率が大きく向上します。
日本語が不得意な外国人社員の昇進の可否については、日本人との公平性についてなるべく配慮する必要があると考え、英語の方がより適切に評価できる場合には、昇進試験の論文・面談を英語で対応しています。結果として、コミュニケーションの行き違いによるトラブルを未然に防ぐのに役立っています。
引用: 厚生労働省 |外国人の活用好事例集
また、海外人材は新しい価値観や発想を組織にもたらし、既存の社員へも良い影響を与えます。人手不足の即戦力補充にとどまらず、組織の多様性と競争力強化につながる点も、グローバル人材活用の魅力といえるでしょう。
外国人社員も納得できる公正な人事評価基準を策定して、外国人社員も含めた全社員を対象とする職務能力の見える化を図りました。結果として、競争意識が刺激され、仕事に対する意欲や士気の向上につながっています。
引用: 厚生労働省 |外国人の活用好事例集
業務委託契約を検討する
業務委託契約とは、企業や組織が外部の事業者や個人に内部で行っている業務の一部を委託するときに結ぶ契約形態です。
現在はフリーランスで働く人材が増加しているため、人手不足を解消するために業務委託契約を検討するのも1つの手段です。新・フリーランス実態調査によると、フリーランス人口は2020年を境に急激に増加しました。
▼フリーランス人口の推移
美容業界ではフリーランス美容師の働きやすい環境を整えて、人手不足対策を講じる店舗もあります。
すべてのスタッフを業務委託契約で雇用しています。ただし、普通の業務委託とは違い、
「業務委託と教育サロンのハイブリット」が目的。業務委託というと個人でお客さまと一対一の関係を築くイメージが大きいですよね。「afrodite」はその考えではなく、すべてのお客さまはスタッフ全員の担当であるという精神を持つようにしています。
引用:モアリジョブ|美容サロン「afrodite」 代表取締役 和田光弘さん
インボイス制度の消費税の支払いを、店側が3年間は負担してくれることが決まっています。業務委託サロンで働く美容師の多くは個人事業主なので、インボイス制度のフォローは大きなメリットになると思います。また売上や集客の成果があがれば給与に反映されるので、意欲の高い美容師が多く、僕は大宮に所属しているスタイリストから学ぶことも多いです。
引用:モアリジョブ|業務委託サロン「grow大宮」マネージャー 清水愛貴さん
副業を許容する
現在は副業を希望する労働者が増えているため、副業を禁止にしてる場合は、解禁すると人材を採用しやすくなる可能性があります。
厚生労働省労働基準局提出資料によると、1992年以降副業を希望する労働者の数が一貫して増加傾向を示しています。
副業を解禁する場合は、就業規則で副業や兼業についてルールを定めることが大切です。厚生労働省が示したモデル就業規則によると、副業を許容するのと同時に、禁止できるケースについても次のように定めています。
【副業を禁止できるケース】
- 副業が原因で仕事で支障が出た場合
- 企業機密を漏洩する恐れがある場合
- 会社の名誉や信用を損なったり、信頼関係を壊したりする行為がある場合
- 競業により、企業の利益を害する場合
また副業の時間に一定のルールを設けると、副業で健康を害したり、自社の業務に支障をきたしたりするリスクを防げます。
就業時間を減らす
就業時間を減らしたいと考える従業員は多いので、業務を効率化して就業時間を減らすと人手不足解消につながります。厚生労働省の調査によると、週の就業時間が35~42時間の場合であっても、就業時間を減らしたい人が増やしたい人を上回ることがわかりました。
週休2日で働いた場合、週の就業時間35~42時間を1日の労働時間に換算すると7時間~8時間24分に相当します。つまり週休2日制で1日約8時間という一般的な働き方であっても、さらに労働時間の短縮を希望する従業員が多いことになります。
実際に厚生労働省が示したデータによると、35時間未満のパートタイマーとして働く人の数は、増加傾向を示しています。
さらに現在は、厚生労働省が短時間正社員制度を設けて、正社員がライフスタイルに合わせて働けるようにサポートしています。
短時間正社員制度は、就業意識の多様化が見られる中、自らのライフスタイルやライフステージに応じた多様な働き方を実現させるとともに、これまで育児や介護をはじめ様々な制約によって就業の継続ができなかった人や就業の機会を得られなかった人たちの就業の継続や就業を可能とする働き方です。
引用:「短時間正社員制度」導入支援マニュアル/厚生労働省
美容業界でも短時間正社員制度を導入して、雇用に役立てる事例がみられます。
あとは週30時間の勤務でも正社員になれる、短時間正社員制度を導入しています。福利厚生がまだまだ整っていない会社が多いなか、短い勤務時間でも正社員になれるのはメリットがとても大きいのではないかと思いますね。子育て中の方などにとても好評です。
引用:モアリジョブ|白髪染め専門店「Age」 代表 今井 基成さん
あるサロン様に『短時間正社員制度』の導入をおすすめしたところ、子育てのために辞めようとしていた優秀なスタッフが働き続けることになった上に、新卒の応募も増えたんです。しかも、経営者側には助成金も給付されました
引用:モアリジョブ|社会保険労務士 東久仁子さん
リファラル採用を導入する
近年注目されているのが、社員による紹介を通じて人材を確保するリファラル採用です。株式会社プロフェッショナルバンクの調査によると、75%の企業が「リファラル採用を実施したことがある」と回答しています。

さらに、そのうち80%の企業が「リファラル採用の成功確度が高い」と回答しています。既存社員が自分の知人や友人を紹介するため、通常の求人広告に比べて「企業文化との親和性が高い人材」が集まりやすい点が良い影響を及ぼしていると推察されます。

また、求人広告や人材紹介会社を利用する場合に比べて採用コストが抑えられるうえ、紹介者との信頼関係を背景にした安心感から、入社後の定着率も高まる傾向があります。制度を導入する際は、紹介に成功した社員に報酬や表彰を用意することで、社内の協力体制を強化できます。
さらに、リファラル採用は「自社の良さを社員自身が伝える」仕組みであるため、自然と社内エンゲージメントの向上にもつながります。求人を出しても反応が薄い場合でも、従業員のつながりを活用すれば新たな候補者層にアプローチでき、人手不足解消に大きな力を発揮する方法といえます。
ただし、デメリットとして「候補者が活躍しない場合の推薦者の責任が重い」「通常よりも選考基準が下がる」といった回答も挙がっているため、留意しましょう。
業務効率化・自動化で人手を補う
人材採用が難しい中で、社内リソースの有効活用も欠かせません。その代表的な方法が「業務効率化」と「自動化」です。例えば、紙ベースで行っていた勤怠管理や経費精算をクラウドシステムに移行するだけで、バックオフィス業務に割いていた時間を大幅に削減できます。
また、近年注目されているRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入すれば、請求書処理やデータ入力など反復的な作業を自動化でき、従業員はより付加価値の高い業務に集中できます。スターティアホールディングス株式会社の調査によると、実際にRPAを導入した企業のうち「大変満足」「満足」は57.38%であり、反対に「不満」「とても不満」は2.91%に留まっています。
▼RPAを導入した企業の満足度

この他にも、製造業では自動搬送ロボットやAIによる検品システム、サービス業ではセルフレジやオンライン予約システムの導入が進んでおり、これらは人手不足の解消に直結する事例として注目されています。
さらに、業務プロセスを見直す「業務フロー改革」も重要です。無駄な承認ステップを削減し、業務をシンプルにするだけでも人材不足の負担は大きく軽減されます。採用のみに頼らずとも、社内に眠る「効率化の余地」を発見し、デジタル技術と組み合わせて改革を進めることが、人材不足の解消につながるのです。
求人媒体など採用ツールを見直す
人手不足の背景には「求職者がいない」ことだけでなく、「自社のターゲットに合った採用ツール(求人媒体など)を選べていない」という問題も潜んでいます。
例えば、20代の若手層を採用したいのに、ミドル層が多く利用する媒体を使っていては応募は集まりにくくなります。同様に、専門スキルが必要な職種にもかかわらず、総合型の媒体だけで募集していると、ミスマッチが生じやすくなります。
人材不足を「応募が来ないから仕方ない」と捉えるのではなく、まずは自社の採用戦略を振り返り、ターゲットと媒体のマッチ度を見直すことが解決への第一歩です。採用力を高めるうえで「どの媒体が自社に適しているのか」を整理することは欠かせません。
その際、自社の採用要件にあう人材をデータベース上で検索して直接アプローチをかけれる「ダイレクトリクルーティング」を行える媒体であれば、よりマッチ度の高い採用を行いやすくなるでしょう。
求人媒体ごとの特徴や違いについては、こちらの記事に詳しくまとめていますので、ぜひあわせてご覧ください。
人手不足の解消に成功した事例11選
ここでは、人手不足の解消に成功した事例を11個紹介します。Yahoo!ニュースや中小企業庁発行の事例集、弊社運営のモアリジョブをもとに紹介するので、ぜひ参考にしてください。
適材適所の人材配置
美容サロン「TICK-TOCK」では、スタッフが才能を活かせるような人材配置を意識しています。仕事を分割して、得意な業務をスタッフに割り振ることが、離職予防につながっているようです。「TICK-TOCK」オーナーのSAYURI USHIOさんは次のように話されています。
私のサロンでは特に問題を感じていません。せっかく美容師になったのに、辞めてしまうのは悲しいことですよね。
仕事は分けられます。得意なことは得意な人に任せるのが一番。例えば商品開発やクリエイティブなことは私が担当。それ以外の苦手なことは他のスタッフに任せています。やりたいことをやりたい人に任せればいいんです。スタッフにも、やりたくないことはやらなくていい…と言っています。スタッフひとりひとりの才能を最大限に引き出して、活躍できる場所を提供するのが経営者の役目です。
引用:モアリジョブ|美容サロン「TICK-TOCK」 オーナー SAYURI USHIOさん
子育てスタッフが働きやすい職場づくり
美容サロン「hair Prego」は、提供するサービスの質がスタッフ個人の能力に依存しない体制を整えることで、人手不足の解消に成功しました。
体制づくりにあたって、まずは大人の女性が抱える悩みを解消するためのサロンとしてコンセプトを打ち出しました。そして、白髪や髪の衰え、ボリュームダウンなどの悩みを解決する施術メニューに絞ってサービスを提供したのです。
これらの施術サービスを提供するにあたって、比較的高度なスキルは必要ありません。そのため、子育てでブランクのあるスタッフも活躍しやすい美容室づくりを実現できました。
ママ美容師サロンにしたときから、コンセプトを大人女性の悩みを解決するサロンと設定し、白髪、髪の衰え、髪のボリュームダウンを解決できるメニューだけを提供していました。それをホームページや集客サイトにしっかり書いて、どんな価値が提供できるサロンなのかということをお客さまにきちんとアピールするようにしたんです。
引用:モアリジョブ|「hair Prego」代表 渡辺敦さん
カラーをはじめとした高度な技術力を要する施術サービスを依頼された場合は、スタッフが依頼を断ってもよいことにしています。
子育てでブランクのある女性でも活躍できるため、採用ターゲットの幅が広がり、人手不足の解消につながっています。
職場体験会の開催
運輸業界では、バスの運転手不足が深刻化しています。そのようななか、バスの運転手確保のために職場体験会が実施されました。
国土交通省の担当者も参加して、生活面や観光誘致の面でバスの運転手が重要な役割を担っていることを説明。若年層の運転手の活躍が期待されていることを伝え、実際に路線バスを運転する催しが開かれました。
職場体験会を通してバスの運転手に興味を持ってもらうきっかけになったようです。体験会に参加した大学4年生は次のように語っています。
人手不足によって廃止路線が増えれば大変だと感じました。実際に話を聞いて責任の大きい仕事だと感じ、興味が増しました
引用:NHK|バス運転手確保へ 路線バス使い職場体験会
業界自体が不人気だったり、一般的に仕事内容が認知されていなかったりする場合は、職場体験会で仕事内容を知ってもらうことも人手不足を解消するための手段として有効です。
マルチタスク化による業務の効率化
旅館業を営む株式会社下部ホテルでは、社員のマルチタスク化によって業務を効率化。従業員の負担が減少して、人手不足の解消につながったようです。
旅館業では、「中抜け勤務」と呼ばれる不規則な勤務時間により、求人募集に応募が集まらないことが、人手不足につながっています。中抜け勤務とは朝食の時間帯に勤務して、その後6時間程度の休憩を挟み、夕食時に再び出社するような勤務形態をさします。
下部ホテルは中抜け勤務を解消するために、スタッフ各人が複数の業務を兼務するマルチタスク化に取り組み、業務の効率化を図りました。その結果、早番と中番、遅番のシフト体制を構築して、勤務時間をまとめることに成功。中抜け勤務を廃止できたことで、変則勤務が解消されて社員の満足度が改善しました。
他にもマルチタスク化に取り組んだ結果、次のようなメリットがあったようです。
マルチタスク化により、繁忙期でも増員することなく顧客対応できるようになるとともに、人件費を上げることなく中抜け勤務の削減に成功した。中抜け勤務は、閑散日は0名、繁忙日でも2名程度までの対応に減少し、社員満足度改善に寄与した。
残業時間も減少し、人件費は2018年7月~ 11月までの5か月で前年比300 万円減、人件費率が1.4%低下した。マルチタスク化により、お互いの業務をカバーできる体制となったことで、年間休日は10 日程度増やすことができた。
引用:経済産業省 ミラサポPLUS|株式会社下部ホテル
教育・人材育成による定着率の向上
シグマ株式会社では、入社時・入社後の社員教育制度の見直しを実施して、社員の定着率の向上に成功しました。人材育成をバックアップするなかで、上司以外の先輩との交流時間を設けることで、さまざまな人材に相談をしたり、アドバイスを受けたりできる「三位一体教育体制」を構築しました。
その結果、社員のモチベーションが高まり、定着率の向上につながったようです。このように教育制度を改善すると、社員が定着しやすくなるため人手不足の解消につながる可能性があります。
「三位一体教育体制」を構築したことで、社員のモチベーションを高め、会社の理念を浸透させることに成功。結果、定着率の向上につながり、ビジネスモデル構築にもつながった。
引用:中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例集|シグマ株式会社(製造業)
しかし美容業界で教育制度を充実させる場合、特定の技術ばかりに偏った教育を行うと、店舗の可能性や美容師のキャリアを狭めてしまうため注意が必要です。
「カラーが苦手」「縮毛矯正は面倒くさい」といったネガティブな理由でメニューを削っていくと、結果的にお店の可能性を狭めてしまいます。本来なら、体操の内村航平選手のように全種目をハイレベルでこなせる人が、その中でも最も得意なメニューをメインに提供するというのが、専門店の理想形だと思います。
(中略)
自己ブランディングを焦るあまり、槍みたいに一点突破で1つの技術だけを尖らせたって、若いうちはともかく年齢を重ねてからのキャリアの選択肢が限定されてしまいます。
引用:モアリジョブ|美容サロン「VIF (ヴィフ)」 オーナー 田中元さん
スタッフが店舗の将来性やキャリアに不安を抱えると、離職する可能性があります。将来性のあるスタッフを育成するためにも、さまざまな知識とスキルを身に着けられるように教育することが大切です。
働き方改革とITツールの導入
株式会社OZ Companyでは働き方改革とITツールの導入を進めることで、離職率の改善と求人広告費の削減に成功しました。
働き方改革を実行するにあたり、代替スタッフを確保して残業ゼロと有給休暇の完全消化を目指しました。またITツールの活用により在宅勤務を導入して、スタッフが自分のライフスタイルに合わせて働ける環境を提供。その結果、次のような好循環が生まれました。
2012年度には44%であった離職率が2015年度にはゼロになり、さらには求人広告を出さなくても新たな人材確保が可能となった。
引用:中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例集|株式会社OZ Company(サービス業)
採用フローの見直し
株式会社あべはんグループでは、採用フローを見直して将来の幹部候補生の確保に努めています。具体的には次の施策を実施しました。
- 求める人物像を明確化と採用ターゲットの見直し
- 採用ツールとホームページをリニューアル
- 採用基準の設定
- 内定者フォローの充実化
以上の取り組みにより、社風に共感した学生を採用できるようになりました。今後は新入社員が採用活動に参加する体制を整える予定です。
内定者フォローによりエンゲージメントを高めつつ、次年度の採用活動では新入職員として採用活動に参画してもらうよう計画中。数年かけ、若手が主体となって全社一体で行う採用・定着プロジェクトに昇華することを目指す。
引用:経済産業省 ミラサポPLUS|株式会社あべはんグループ(若鶏の解体加工、飼料・初生雛の販売)
自由シフトの導入
美容サロン「CLUTCH」は自由なシフトで働ける環境を整えることで、人手不足の防止に成功しています。
うちのサロンでは正社員と業務委託が選べるのですが、正社員はこれくらい働いてほしいという最低時間だけは決まっています。それをどう分配してもいい。業務委託は何時間でもOKという形です。ママさん美容師など、正社員で勤務時間を短くしたい人は、最初にどれくらい働けるかを聞いて固定給を決めています。
引用:モアリジョブ|美容サロン 「CLUTCH」 代表 濱浩太朗さん
スタッフの総数が多いため、それぞれが自由に働いても勤務シフトに穴が空くこともないようです。
とくに大きな問題はおきていませんよ。美容師さんはある程度働く時間と収入が比例するので、効率的に稼ごうと土日に働く人は多いです。予定などがあって休む人はもちろんいますが、全員が土日に休んでしまうということはないですね。
引用:モアリジョブ|美容サロン 「CLUTCH」 代表 濱浩太朗さん
以上は人手不足が解消されて、多くのスタッフを雇えれば、職場環境にも好循環をもたらす好事例といえるでしょう。
稼働率を調整してスタッフの負担を軽減
鍼灸サロン「Warmy」は労働環境を整え、給与面などを高待遇にすることで、6年連続して離職率ゼロを達成しています。
うちのサロンでは月に9日の休日、勤務時間内の研修、有給消化率100%推奨など、プライベートと仕事をきっちり分けた働き方ができます。給与面では30万円以上を目指すことも可能です。
引用:モアリジョブ|鍼灸サロン 「Warmy」 代表 御領原圭佑さん
以上の労働条件を達成するためには、店舗設計の段階で低い稼働率でも利益を確保できるようにビジネスモデルを構築することが大切です。
スタッフの稼働率が6割から7割で、利益が十分に確保できるように設定しています。この業界では稼働率が7割を超えると離職率が一気にあがるといわれているので、稼働率が上がり過ぎない、つまり予約が入り過ぎないように注意深く見ているんです。
引用:モアリジョブ|鍼灸サロン 「Warmy」 代表 御領原圭佑さん
さらに面接の際に自社で働く場合のデメリットを伝え、採用後のミスマッチを防ぐと離職者を減らせます。
面接をするときに、うちのサロンで働くことのメリットだけでなく、デメリットもしっかり伝え、採用のアンマッチを防ぐようにしています。入社後に「想像していた仕事と違う」と思われることも離職につながる大きな原因の1つだと思うので。「HariFa」の採用時には、99%が美容鍼のお客さまなので、体の治療もしたいという人には向いていないということ、施術内容やお客さまに話す内容なども1から10まできっちり決まっているので、自分で施術内容を組み立てたいという人には不向きであることははっきり伝えています。
引用:モアリジョブ|鍼灸サロン 「Warmy」 代表 御領原圭佑さん
採用ターゲットの拡大
シグマ株式会社は、特に従来は日本人のみを対象としていた採用ターゲットに外国人を加えることで、採用母集団を広げることに成功しました。
採用方法を見直し、採用ターゲットに外国人人材を加えたことで、人材の確保に成功。
引用: 経済産業省 |中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例集
それまでは募集を行っても採用要件に沿う人材からの応募がなく、新事業進出等にチャレンジする人や海外出向などへの希望者がいない状況だったとのことです。
また外国人材を迎え入れるにあたり、同社は「共通ルールの徹底」と「業務プロセスの標準化」に力を入れました。
日本人か外国人かを問わず、社内のあらゆるルールは全社員共通で適用し、「徹底した標準化(見える化)」を基本とした。
引用: 経済産業省 |中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例集
日本人と外国人を区別せず、全社員に共通のマニュアルやルールを適用することで、誰もが同じ基準で働ける職場環境を構築。その結果、コミュニケーションの齟齬や業務品質のばらつきを防ぎ、スムーズな定着につなげています。
「採用ターゲットの拡大」と「受け入れ体制の整備」を同時に進めることで、人手不足の解消と多様性のある職場づくりを両立させた好事例といえるでしょう。
新たな採用手法の導入
Q.ENEST(キューエネス)でんき株式会社は、人材確保の難しさに直面するなかで、従来型の求人媒体に頼るだけでなく新しい採用手法を積極的に取り入れました。
リファラル採用やダイレクトリクルーティングの活用を推進している。特に前者は、自社の魅力をダイレクトに伝えられること、人柄や実績を良く知っている人にアプローチできることが大きな利点。
引用: 厚生労働省 |人材の確保・定着に成功した企業の取組事例集~採用活動のコツ~
リファラル採用では、社員が信頼できる人材を紹介するため、ミスマッチが少なく、採用後の定着率が高いというメリットがあります。また、紹介を受けた候補者も「社員が推薦している企業」という安心感から、応募への心理的ハードルが下がる傾向があります。
一方でダイレクトリクルーティングは、求めるスキルや経験を持った人材に企業側から積極的にアプローチできるため、スピーディーに採用活動を進められるのが特徴です。
こうした複数の採用手法を組み合わせた取り組みは、限られた労働人口の中で優秀な人材を確保するための有効な戦略として、他企業にも参考になる事例といえます。
まとめ
本記事を総括すると次のとおりです。
- 人手不足を解消するための主な方法として、教育制度の充実や女性雇用の促進、シニア層の再雇用が考えられる
- 多くの企業が独自の工夫で人手不足の解消に成功している
- 具体的な事例を参考にすることで、自社の人手不足を解消するヒントになる
人手不足に対する6つの対策方法と解消に成功した事例9選を紹介しました。これから人手不足の解消に取り組む際には、ぜひお役立てください
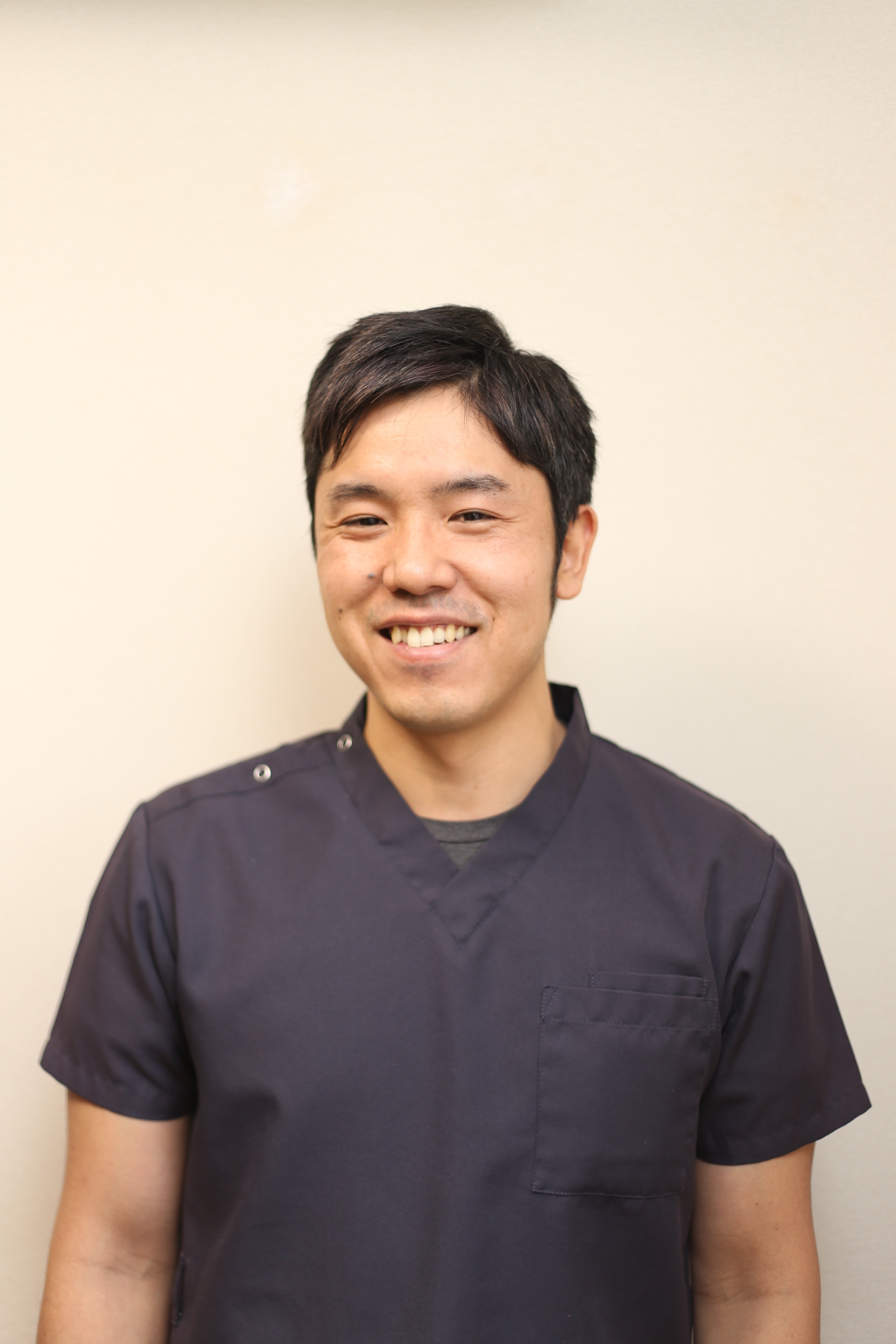
- 執筆者情報
- 東 大輔(Higashi Daisuke)

