現在、ホワイトカラーよりも労働集約型のエッセンシャルワーカーを中心に人手不足が進んでいるといわれています。
エッセンシャルワーカーが従事する仕事は自動化や機械化が難しく、人手がかかるため生産性が上がらないことが特徴です。賃金を上げづらいため、求人に応募が集まらず、人手不足になりやすいと考えられます。
また美容業界の場合、座席数やスタッフ数、営業時間で店舗売上の上限が決まります。いくら店舗が繁盛しても上限がある以上は、スタッフの賃金アップに限界があることが実情です。
客数も「席数」「スタッフ数」「営業時間」で上限が決まるんですよ。なので、自然とこの店舗での限界MAXの売上は**万円という感じで上限が決まってきます。
ということは、スタッフの給料を上げ続けても、売上は上限以上に増えないので、次第に人件費が経営を圧迫していきます。これを続ければ、最終的に赤字に転落してしまうってことです。
引用:note/シェアサロン SALOWIN 代表 阿部友哉さん
人材不足による職場崩壊を防ぐためには、安易に賃金アップができない事情を考慮した上で対策を講じることが大切です。
今回は、労働集約型の事業で人手不足による職場崩壊がおこる原因と対策について解説します。人手不足のしわ寄せによる職場崩壊に対して、政府の支援を活用して実行できる対処法がわかりますので、ぜひ参考にしてください。
人手不足の現状
ここでは日本における人手不足の現状を説明します。人手不足の企業の割合や傾向が強い業界について解説するので、参考にしてください。
人手不足の企業の割合
人手不足の企業の割合は、2009年以降上昇傾向です。2020年のコロナ禍は一旦落ち着いたものの、コロナ禍が収束に向かうに従い上昇傾向が続いています。
帝国データバンクの調査 によると、2025年には正社員の人手不足に悩む企業の割合が50.8%に達しており、日本企業の半数以上が人手不足に悩んでいることになります。

人手不足の傾向が強い業界
特に人手不足の傾向が強い業界は、建設業や運輸業、サービス業です。建設業や運輸業は、残業時間の規制による2024年問題が注目されています。2024年問題とは、2024年4月を境に年間時間外労働時間の上限が960時間に制限されたことで発生する人手不足問題です。
時間外労働時間が制限されたことで残業時間が減り、労働者の給料が減少します。給料が減少すると、労働集約型の建設業や運輸業を志望する人材や定着率が減り人手不足になる恐れが高まるのです。
また1人の労働者の労働時間が減少することで、業務遂行に必要な労働力を確保できなくなることも不安視されています。
サービス業は一部でみられる劣悪な労働環境が原因で、人手不足の傾向が続いています。例えば、美容業においては業界全体の労働環境がブラックな印象を持たれていて、人材が集まらずに人手不足が常態化していることが課題です。
美容師業界で働いている知人に話を聞いて、非常にブラックだと感じたんですね。拘束時間が長いにもかかわらず、給料が安い。それでアシスタントからスタイリストになる前に辞めてしまう人も多い。
引用:日刊SPA!/美容室「mulum」/代表取締役 亀井彰氏
昔ながらの考えを持って美容室を経営するオーナーがいることも業界がもつブラックな職場環境のイメージを払しょくできない原因と考えられます。
昔は「美容師に有給はない」といわれていた。海野さん自身、「風邪で休んだら罰金1万円」なんて職場も経験したそうだ。今はだいぶホワイトになってきたとは感じるものの、昔ながらの考え方は根強く残っている。
引用:ITmediaビジネス
次の記事では、業界ごとの人手不足の要因や状況、対策について詳しく解説しています。
人手不足が深刻化する背景
人手不足が今後さらに深刻化するといわれる大きな理由は、労働力人口の減少と少子高齢化です。
厚生労働省「高齢社会白書」 によれば、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年の8,716万人をピークに減少傾向にあり、実数値の2024年時点でも7,373万人程度まで縮小しています。さらに2030年には7,076万人、2050年には5,540万人程度まで縮小すると予測されています。
▼労働力人口・就業者数の推移

さらに、「高齢化率」は今後も高まり続け、それに応じて「65歳以上人口を15〜64歳人口で支える割合」は低下し続けます。
このように、日本の人手不足は一時的な景気変動によるものではなく、人口動態や制度改革に根差した「構造的な課題」であり、前兆や課題を放置すれば職場崩壊を招くリスクが高まっていくのです。
人手不足による職場崩壊の前兆と理由
人手不足で職場が崩壊する場合、まずは前兆として人手不足により従業員の負担が増えることが考えられます。
さらに過剰な負担に耐えられなくなった従業員が離職して、退職者数が増加。その結果、業務を遂行するために必要な従業員を確保できなくなり、職場が崩壊します。
以下で、人手不足による職場崩壊の前兆と理由をみていきましょう。
従業員の負担が増える
人手不足は従業員の仕事量を増やす一番の要因です。株式会社ビズヒッツが500人に対して行った調査によると、仕事量が多い理由として、人手不足を挙げた人の数が最も多いことがわかりました。

以上の結果を見ると、人手不足が慢性化する職場の場合、過度な業務負担に不満を抱く従業員が増えやすいと予想されます。業務に不満を抱えた従業員は、退職を考えるようになるため注意が必要です。
自分の担当の仕事が量が多すぎてキャパオーバーです。自分以外にその仕事をできる人もいなく、職場は少人数(慢性的な人手不足)でみんなも忙しくて頼めません。
休憩もろくに取れないし仕事を家に持ち帰ってやったりしてます。
(中略)
それなら辞めようかな…と思ってしまいました。私は弱くておかしいですか?好きな仕事なんですけど、こんな思いしてまで勤めないといけないのでしょうか…
引用:Yahoo!知恵袋
仕事を辞めたいと考えています。辞めたい理由としては仕事量が多いことや、給料がそれに見合っていないことなどです。人間関係にも少し悩んでいて、精神的に辛いこともあります。
引用:Yahoo!知恵袋
退職者数が増える
業務負担が増えると、残業時間が増えたり休日が減ったりして労働環境が悪化します。人手不足のしわ寄せは従業員に向かうため、退職を考える従業員がでてきます。
令和6年の雇用動向調査 によると、前職を辞めた個人的理由として労働条件を挙げた人の割合は、男性で3番目、女性で1番目に多いことがわかりました。
▼前職を辞めた個人的理由上位3つ:男女別(※その他を除く)
|
順位 |
男性 |
割合 |
女性 |
割合 |
|
1 |
給与等収入が少なかった |
10.1% |
労働時間、休日等の労働条件が悪かった |
12.8% |
|
2 |
職場の人間関係が好ましくなかった |
9.0% |
職場の人間関係が好ましくなかった |
11.7% |
|
3 |
労働時間、休日等の労働条件が悪かった |
8.6% |
給与等収入が少なかった |
8.3% |
※「 厚生労働省|令和6年雇用動向調査結果の概況 」を基に作成
昨今は、短期間で複数の従業員が離職する「連鎖退職」が問題になっています。
ある1人の退職をきっかけに退職者が続出。最悪、組織の存続さえ危ぶまれる事態に―人手不足が社会問題化する今、このような「連鎖退職」がさまざまな会社から報告されている。
引用:連鎖退職/山本 寛
連鎖退職が起こるきっかけの1つとして、業務負担の増加による労働条件の悪化が挙げられます。そのため職場崩壊を防ぐためには、人手不足のしわ寄せが従業員の仕事量に影響を与えないようにすることが大切です。
次の記事では、連鎖退職や従業員が退職する原因を詳しく解説しているので、参考にしてください。
労働災害やメンタル不調の増加
人手不足の影響は、従業員の心身にも現れます。業務の負担が増えることで、疲労から注意力が散漫になり、ヒューマンエラーや労働災害が発生しやすくなります。これらは「人が足りない」という状況が表面化したサインともいえます。
また、過重労働や終わりの見えない業務によって強いストレスを抱える従業員が増加し、うつ病や適応障害といったメンタル不調につながるケースもあります。
こうした不調は表面化しにくく、周囲が気づいたときにはすでに深刻な状態に陥っているケースも少なくありません。
厚生労働省の過労死等防止対策白書 においても、長時間労働や業務上の強いストレスが精神障害や最悪の場合は過労死につながることが指摘されています。
労働災害やメンタル不調が続発するようになると、休職者や退職者が増え、さらに人員不足が加速する悪循環に陥ります。これは職場崩壊の典型的な前兆の一つであり、早い段階で経営層や管理者が対応を講じる必要があるといえるでしょう。
人手不足を放置し、職場崩壊した会社の末路
職場崩壊を起こした会社は経営不振に陥り、やがて倒産します。ここでは人手不足を放置して、職場崩壊を起こした会社の末路を紹介します。
経営不振に陥る
人手不足を放置すると、売上の減少やコストの増大で経営不振に陥る可能性があります。
日本政策金融公庫の資料 によると、人手不足の影響として「売上機会の逸失」を挙げる企業が約4割に上りました。次に、残業代や外注費などに費やすコストの増加を挙げる企業も一定数みられます。
▼人手不足による影響

売上機会の逸失に売上の減少や人件コストの増大は、経営に直接影響を与える要因です。経営を圧迫することにつながるため、早めの対策が求められます。
なかには、自身の負担を顧みずに働くことを従業員に期待した結果、離職が増えて経営不振を招いた整骨院の事例もあります。
実際開業してみると、はじめのスタートダッシュは結構よかったんです。でも3カ月でスタッフが全員辞めて、受けた融資も底をつきました。
――スタッフが辞めていったのは、なぜだったのでしょうか?
一番大きかったのは、価値観のギャップでしょうか。僕はどちらかというとベンチャー企業のようなイメージでいたんですが、宮前平で働きたいという人は、もっとゆっくり楽に働きたい人が多かった。だから「ついていけない」という結果になってしまったんだと思います。「これはまずい」と、そこから必死で頑張りましたね。
引用:モアリジョブ/株式会社ボディスプラウト 代表 小林篤史さん
企業が倒産する
売上の機会を失ったり、残業代や外注費がかさんだりして経営不振が続くと、やがて倒産します。帝国データバンクの調査によると、人手不足による倒産は近年増加傾向です。
帝国データバンクの調査 によると、従業員の退職や採用難、人件費高騰などを原因とする「人手不足倒産」は近年増加傾向です。

また、 帝国データバンクによる別の調査によると、2024年の人手不足倒産は、2年連続で過去最多を更新して計342件に達したとのことです。
業種別では、建設業が99件で最多、物流業も46件と高い数値を示しています。「2024年問題」に直面する両業種で全体の4割以上を占めています。さらに、労働集約型の産業である飲食店や美容室、ネイルサロンなども急増したと報告されています。

人手不足による職場崩壊を回避する方法
人手不足による職場崩壊を回避するために、まずは採用に力を入れて人材を補う必要があります。さまざまな人材の募集方法があるので、やり方を整理して自社に合った方法を選ぶとよいでしょう。
次の記事では、人材募集のやり方を18個紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
また人材不足によって従業員に業務負担が生じている可能性があります。賃金に見合わない業務負担が生じると、従業員の間で仕事への不満が生じて離職者が増える可能性があります。
離職率が高い状態のまま採用者数を増やしても、人手不足の根本解決は見込めません。そのため、業務の効率化と教育制度の整備、賃金の引き上げなどを検討して労働環境そのものを見直すことも大切です。
しかし労働環境の見直しには、一定のコストがかかるためなかなか改善に取り組めないケースもあるようです。
そのような場合は、助成金の利用を検討してみましょう。人手不足の回避策について、活用可能な助成金とともに解説します。
業務を効率化する
ITを導入して自動化すると、業務を効率化でき従業員の負担を軽減できます。人手不足で低下した労働力を補う手段にもなるので、ITの導入による業務効率化を検討するとよいでしょう。
例えば、美容サロンや美容室、整骨院などの店舗ビジネスの場合、予約システムを導入すると電話対応の時間を減らせるため、少ない従業員数でも顧客対応に影響を与えずに済みます。
オープンしてから3ヶ間は2人で運営していていました。電話対応が厳しい時間帯が多くお客様にご迷惑をかける可能性もあったので、開業前に連絡先を知っているお客様にはQRコードをつけたDMを送信し、ホームページ画面から予約してもらうように促しました。
引用:reservia/美容サロン「coyoli(コヨリ)」 代表 佐々木 健一 様
また事務関連の業務をIT化して業務を効率化すると、従業員への負担の大幅な軽減が期待できます。
ポスレジを導入して売り上げを日次で把握。書類はドロップボックスで共有し、イントラネットを整備して情報網も一括管理。全店舗の予約状況はパソコンで把握できるようにしました。そして月次決算を正確に出すところまで精度を高め、パソコン1台あれば施術以外の仕事はすべてこなせる環境を整えたんです。
(中略)
バックヤードの仕事をデジタル化で圧縮すれば、仕事の質は落とさず、より効率のいいパフォーマンスが発揮できるとわかったんです。
引用:モアリジョブ/フットケアサロン「フットブルー」 オーナー 西谷裕子さん
業務効率化のためにITを導入する場合、IT導入補助金を活用できます。IT導入補助金の補助額は最大で450万円で、ITを導入するために必要な費用の1/2~4/5を補助してもらえます。
教育制度を整える
教育制度を整えて従業員のスキルアップを図ると、対応可能な業務範囲が拡大します。その結果、業務遂行に必要な人員を削れるため、人手不足による労働力の低下を下支えする効果が期待できます。
労働政策研究・研修機構の調査によると、実際に人手不足対策として教育に力を入れる企業の割合は28.1%でした。

一方で教育制度が充実していないと、事業がうまく進まないケースもあるため注意が必要です。
恵比寿店を出した時に2人目の出産と重なってしまったので、オープニングをスタッフに任せたのですが、見事にコケてしまいました。私が開店準備に必要な教育をしていなかったのが原因です。
引用:モアリジョブ/フットケアサロン「フットブルー」 オーナー 西谷裕子さん
また教育を充実させる過程で残業時間が増えてしまい、スタッフに負担をかけると離職を助長する可能性もあります。
離職率が高い点ですね。大型のチェーン店では、30人採用しても多くが途中で辞めてしまいます。一人前になれるのはだいたい5人ほど。原因は、サロンの教育法に問題があるんです。毎日深夜まで練習し、そのうえ休日は研修会があって休めない状況が続くので、耐えられず辞めてしまうんです。これでは貴重な美容師のなり手がどんどん減ってしまい、業界の発展はありません。
引用:モアリジョブ/東京美容生活衛生同業組合(BA東京) 理事長 金内光信さん
教育制度を整える際には、業務内での教育時間の設定や業務時間外に実施された教育に対する残業手当の支給も一緒に検討することが大切です。しかしすでに人手不足が深刻化している場合、教育のためにコストをかけられないケースも考えられます。
そのような場合は、人材開発支援助成金をうまく活用して、コスト負担を減らしながら教育制度を整備しましょう。人材開発支援助成金については、次の記事で詳しく解説します。
賃金の引き上げを検討する
賃金を引き上げると求人への応募者数を増やせるため、人手不足対策として高い効果が期待できます。帝国データバンクの調査によると、人手が不足していない要因として「賃金や賞与の引き上げ」を挙げた企業が半数以上に上りました。

以上の結果をみても、賃金の引き上げは人手不足を回避する手段として有効な手段の1つといえます。
賃金の引き上げを実施できるほどの経済的余裕がない場合は、業務改善助成金の活用を検討するとよいでしょう。この制度を活用すると、地域の最低賃金を満たしていない事業者が、最低賃金以上に自社の賃金を引き上げた場合に、その費用の一部を助成してもらえます。
引き上げ額ごとに助成の上限が決められていますので、詳細については厚生労働省の「業務改善助成金」特集ページをご覧ください。
柔軟な働き方の導入
人手不足を根本的に解決するには、従来の「フルタイム・固定勤務」にこだわらない働き方を取り入れることも有効です。短時間勤務や週数日の勤務、リモートワークの導入など、柔軟な働き方を認めることで、従来は働くことが難しかった人材を職場に迎え入れやすくなります。
例えば、子育てや介護と両立したい人材はフルタイム勤務が難しい場合がありますが、時短勤務やシフトの柔軟化があれば就業のハードルが下がります。
先に触れた通り、業務環境が厳しいイメージをもたれがちな美容業界でも、以下のような事例がみられます。
年齢を重ねても働きやすいように労働環境を整えています。結婚や出産などライフステージに合わせた働き方をできるよう、時短勤務などを用意しているんです
引用: モアリジョブ |株式会社KAMILLE 代表 矢口俊貴さん
自由シフト制で、土曜・日曜も休むことができるところです。売上やサロンの忙しさにもよりますが、基本的にはスタッフの申請通りにシフトを調整してくれますし、時短勤務もできます。子どもの送り迎えがしやすいだけでなく、ワークライフバランスも保ちやすいので働きやすい環境だと感じているんです。
引用: モアリジョブ |「AROMA hair room 池袋店」店長 YUKIさん
また、副業を希望する人材や、地方から都市部の企業で働きたい人材にとっては、リモートワークの導入が働くきっかけとなります。
以上のような柔軟な働き方の導入は、従業員のワークライフバランス改善につながり、離職防止の効果も期待できます。結果的に「働きやすい職場」「長く勤めやすい職場」というイメージを根付かせ、採用と定着の両面から人手不足による崩壊リスクを和らげられるでしょう。
人手不足を緩和させる現実的な選択肢
人手不足を放置すれば職場の崩壊リスクは高まる一方です。すでに人員不足を実感している企業にとっては、即効性と現実性を兼ね備えた追加の打ち手が必要です。
ここでは、経営資源を大きく割かずに取り組みやすい現実的な施策を紹介します。
外部リソースを活用する
慢性的な人手不足に直面している企業では、すべての業務を自社社員だけで賄うのは現実的ではありません。コア業務に人材を集中させ、それ以外の業務は外部リソースに任せることで、効率的に業務を回すことが可能です。
具体的には、以下のような方法があります。
-
アウトソーシング:
事務作業や経理、給与計算、採用関連業務など、定型化できる業務を専門業者に委託する方法です。社員の負担を軽減し、本来の業務に集中させることができます。
-
BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング):
単純な作業だけでなく、業務プロセス全体を外部の専門業者に委託する方法です。例えば、カスタマーサポートや請求書発行業務など、部門ごと丸ごと任せることで、自社リソースの最適化が可能です。
-
業務委託(プロジェクト単位の契約):
特定のプロジェクトや短期業務について、外部の専門家やフリーランスに業務を任せる方法です。新規事業の立ち上げや販促施策、Web制作、マーケティング施策などで有効です。
-
フリーランスや契約社員の活用:
柔軟な勤務形態でスキルを持つ人材を採用し、必要な期間だけ戦力として活用できます。繁忙期の業務量増加に対応する手段としても現実的です。
これらを組み合わせることで、少ない自社人員でも業務の滞りを防ぎ、職場崩壊のリスクを軽減できます。また、導入コストや契約条件も柔軟に設定できるため、中小企業でも取り入れやすい施策です。
非正規雇用から正規雇用につなげる
すでに社内に在籍しているパートやアルバイト人材を育成し、正規雇用へつなげることは、人手不足の企業にとって非常に現実的な施策です。単純に採用人数を増やすよりも、社内で既に働いている人材を戦力化する方が、業務理解度も高く即戦力化しやすいメリットがあります。
また、非正規から正規登用にステップアップすることで、従業員のモチベーション向上や業務スキルの定着も期待できます。さらに研修やOJTを通じて担当業務の幅を広げ、一定の評価制度やキャリアパスを示せば定着につなげられるでしょう。
厚生労働省も「多様な正社員」 として、勤務地限定や職務限定など、柔軟な雇用形態を導入することで、正社員と非正規雇用者における働き方の二極化を緩和するよう呼びかけています。
シニア人材を戦力として活用する
近年、65歳以上の高齢者の就業率は上昇傾向にあり、 「高年齢者雇用安定法」の改正 により、70歳までの就業機会確保が企業に努力義務として課されています。シニア層は豊富な経験とスキルを持つため、即戦力として活躍できる人材です。
厚生労働省の調査 によると、70歳までの高年齢者就業確保措置として、「継続雇用制度の導入」を実施する企業の割合が最も多くなっています。

上記のように継続雇用制度を導入する企業が定年引き上げよりも多いのは、企業にとって継続雇用制度が定年引き上げよりも導入ハードルが低いためです。
企業は定年年齢そのものを変更する必要がないため、既存の定年制度に手を加えず、即時性のある手段として、高年齢者の雇用を確保できる点が継続雇用制度のメリットです。
また、シニア層が経験を活かして若手社員を指導する役割を担うことで、組織全体のスキル底上げも期待できます。
このようにシニア人材の戦力化は、即戦力としての貢献だけでなく、従業員全体の定着率向上にもつながり、人手不足の長期的な緩和策として有効といえるでしょう。
業界特化の採用媒体を活用する
人手不足を解消するには、求める人材に効率的にアプローチできる採用チャネルの選択が重要です。特に専門性が求められる業界では、一般的な求人媒体よりも業界特化型の採用媒体を活用する方が効果的といえるでしょう。
業界特化の媒体は、求職者もその分野に強い関心や経験を持っているため、応募後のミスマッチを減らし、採用の成功率を高められます。また、専門業界に精通したサポートを受けられる点も、人手不足に悩む企業にとっては大きなメリットです。
たとえば、美容室・サロン・整骨院・介護施設などを対象とした求人サービス 「リジョブ」 は、業界に特化した人材を集めているため、即戦力となる人材と出会いやすい求人サイトです。さらに、求人掲載だけでなく採用に関するノウハウ提供やサポートも行っているため、人事担当者の負担軽減にもつながります。
人手不足を放置すれば、既存スタッフの離職リスクが高まり、職場崩壊につながりかねません。だからこそ、自社に適した採用チャネルを選び、スピーディーに人材を確保することが重要です。
まずはこちらから気軽にお問い合わせください。
まとめ
本記事を総括すると次のとおりです。
- 現在の日本は人手不足の企業が増加傾向で、職場崩壊して倒産に追い込まれるケースも増えている
- 人手不足を放置すると退職者数が増え、経営不振に陥り最終的に倒産するリスクがある
- すでに経営不振に陥り職場崩壊の危機にある場合は、助成金を活用して再起を図るのもひとつの手段
- 業界特化型の採用媒体の活用も人手不足解消に向けた現実的かつ効果的な選択肢
エッセンシャルワーカーが働く職場は、賃金アップを図りづらく求人に募集が集まりづらい傾向です。そのため人手不足による職場崩壊を起こしやすいと考えられます。
特に従業員数が10人に満たない職場の場合は、人手不足による倒産へと追い込まれやすいため注意が必要です。職場崩壊による倒産を回避するためにも、早めに人手不足の解消に取り組み、既存の従業員にかかる負担を軽減しましょう。
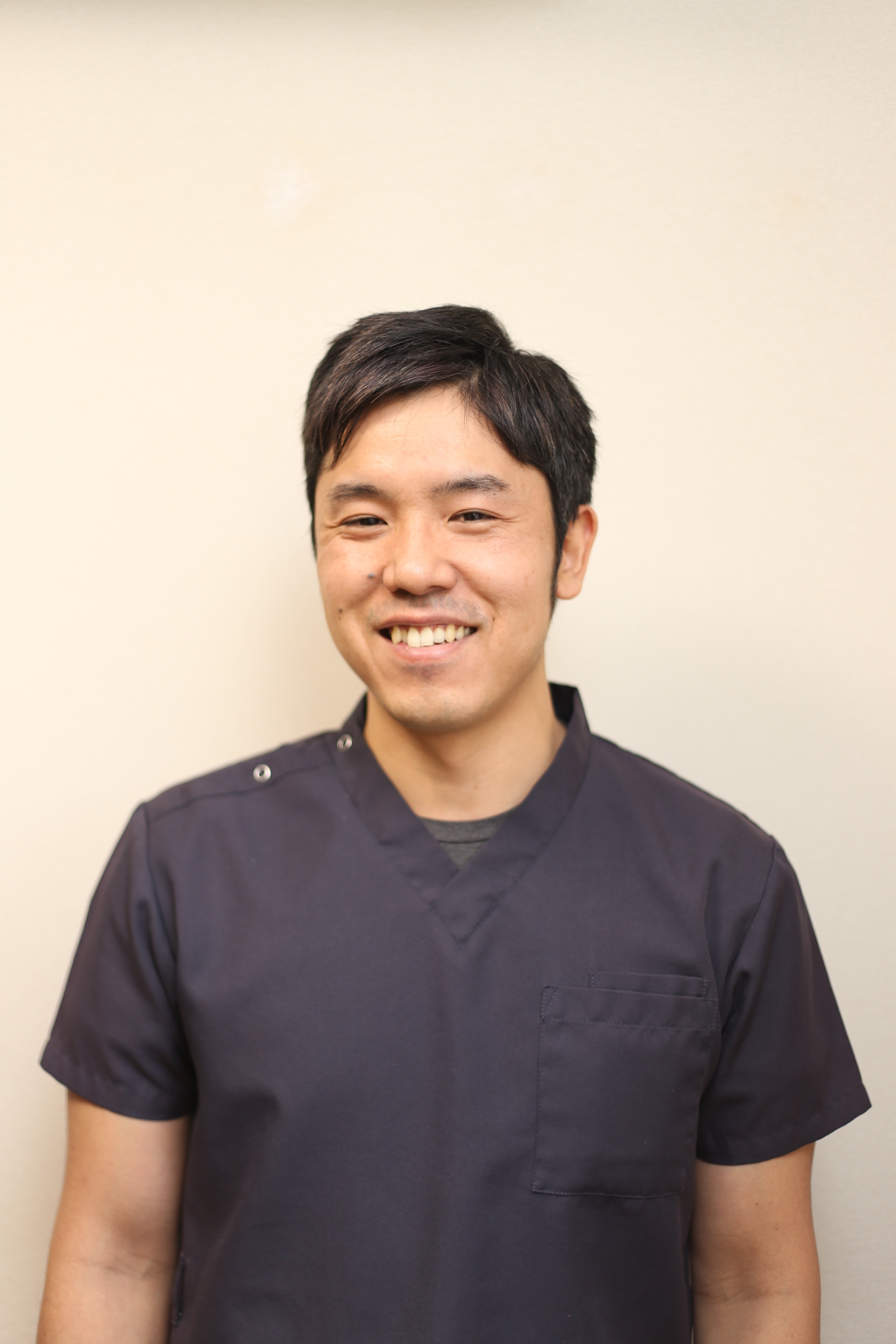
- 執筆者情報
- 東 大輔(Higashi Daisuke)

