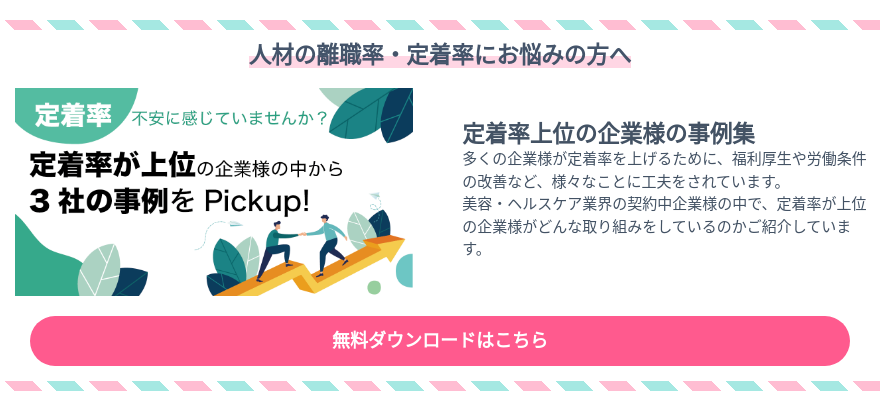帝国データバンクの調査によると、人手不足を原因とした倒産は2025年上半期で202件であり、過去最多を2年連続で更新したことが報告されています。
人手不足が深刻化するなかで企業成長を維持するためには、まずは人手不足に陥る原因を社会全体の視点で分析することが欠かせません。
さらに業界別あるいは個別企業において人手不足に陥った理由を把握することも重要です。特定した原因をもとに、人手不足の解消に向けてどのような施策を講じるべきかを検討しましょう。
本記事では、人手不足に陥る原因について社会全体の視点と、業界別・企業別の視点で分けて解説します。人手不足対策の事例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
人手不足の現状
人手不足になる理由を理解するために、まずは人手不足の現状を把握しましょう。ここでは、労働市場における人手不足の傾向と人手不足が各業界に与える影響について解説します。
労働市場における人手不足の傾向
日本の労働市場では、若手人材や専門的な職種での人手不足感が顕著です。内閣府が企業向けに行った調査によると、34歳以下の若年層について「不足」あるいは「やや不足」と答えた企業が、40%あるいは50%近くに上りました。
▼年齢別、職種別の人手不足間

さらに職種別でみると、専門・技術職について約3割の企業が「不足」と回答しています。「やや不足」と回答した企業も半数近くに上り、事務職や営業職と比べても人材不足感が強い傾向です。つまり人材を募集しても、必要とする年齢層や職種で人が集まらずに人手不足になる企業が多いと考えられます。
人手不足が各業界に与える影響
人手不足が各業界にあたえる影響は、さまざまです。たとえば運輸・物流業界では、働き方改革がきっかけで起こった2024年問題を抱えています。これらの業界では、残業規制が強化されることで、人手不足が一気に加速することが懸念されており、運転手を確保できない企業を中心に倒産が相次ぐといわれています。
また 厚生労働省の調査 によると、美容やエステティックなどが含まれる生活関連サービス業も、有効求人倍率が3倍以上と採用難度が高い状態です。有効求人倍率3倍とは3社が1人の求職者を取り合う状況で、企業間の人材獲得競争が激化している状況を示しています。人手不足は経営の根幹に関わるため、多くの業界で人手不足対策が企業の存続を左右する状況になっているのです。
次の記事では人手不足の状況と対策について業界ごとにまとめていますので、ぜひご覧ください。
人手不足を原因とした倒産の増加
人手不足を原因とした倒産が増加しています。 帝国データバンクの調査 によると、従業員の退職や採用難、人件費高騰などを原因とする「人手不足倒産」は、2025年上半期に202件発生しており、前年上半期(182件)から20件増加し、過去最多を2年連続で更新しています。

このように人手不足は各業界および企業に対して、倒産リスク増大という最も避けたい悪影響を与えているのが実情です。
なぜ社会全体で人手不足が発生しているのか?
次に人手不足が発生している社会的な要因を見ていきましょう。要因として、主に次の3つが挙げられます。
- 労働力が限られているから
- 人材のミスマッチが起こっているから
- 仕事に対する価値観が変化しているから
それぞれについて解説します。
労働力が限られているから
総務省 統計局の労働力調査によると、2019年まで上昇傾向にあった労働力人口が以降はほぼ横ばいとなっています。2022年以降は微増したものの、依然として大きな伸びは見られません。
▼労働力人口の推移

労働力人口とは、15歳以上になる人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口をさします。労働力人口が増えないのは雇用できる人材の母数が限られるのと同義のため、人手不足に陥る企業が増えていると考えられます。
また男女別にみると、男性の方が労働力人口の減少傾向が顕著であることから、今後はますます男性を採用しづらくなるでしょう。
一方で女性については、2019年まで上昇傾向でしたが、2020年は労働力人口が一時的に減少しています。それでも2021年には持ち直して以降は増加傾向にあるので、女性の採用に力を入れることは今後の人手不足対策にとって重要な取り組みになると考えられます。
▼労働力人口の推移(男女別)
.png?width=858&height=322&name=4_%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%8A%9B%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E3%81%AE%E6%8E%A8%E7%A7%BB(%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%88%A5).png)
実際に美容業界でも女性の働きやすい職場環境を整えて、雇用の安定を図る美容室があります。
うちの従業員はほとんどが女性です。入社の際、精神的にも社会的にも自立した女性になってほしいと彼女たちに伝えています。今は特に、先の見えない時代ですし、きちんと稼いで自分の生活基盤は自分で作れるようになるべきだと思います。だから僕は、彼女たちに頑張れる環境を作ってあげたいし、その頑張りが報われる職場にしたい。
引用元:モアリジョブ|アイブロウ&アイラッシュサロン「Une fleur」 代表 矢口俊貴さん
今後、人手不足を防ぐためには、いかに女性を採用できる環境を整えられるのかがポイントになるでしょう。
人材のミスマッチが起こっているから
現在の日本では、人材不足のミスマッチが課題になっています。企業と入職者のニーズにミスマッチが起こった結果、若手の早期退職が顕著になっているのです。
新卒や入社数年の若手社員の早期退職が目立っている。新入社員の4割以上が転職を検討しているという調査もある。深刻な人手不足が続く中、有望な人材をつなぎ留められなければ企業経営は揺らぎかねない。
若手が転職を検討する主な理由は、思い描いていた働き方と違うからです。つまり入職者が希望する仕事内容や働き方と、企業が提示した仕事内容や労働条件との間でミスマッチが起こり、転職を検討する人材が増えたと考えられます。
また生成AIの普及やデジタル化が進むと、幅広い職種で仕事のやり方が変わる可能性があり、それにともない企業が人材に求めるスキルも変化すると考えられます。
美容業界においてはSNSやインターネットなどの普及でデジタル化が進み、企業側が人材に求めるスキルが変化している側面が見られます。従来は施術スキルが主な採用基準でしたが、現在はSNSやインターネットで情報発信をするためのスキルを持ったスタッフを求める動きが見られます。
美容師はお客さまに来ていただいてこその仕事です。たくさんの方にご来店していただくためにも、早いうちから作品撮りに取り組んだり、ネットや本で構図の捉え方を学んだりしておくと良いと思います。
引用:モアリジョブ|「PEEK-A-BOO 原宿」 美容師 大川侑世さん
以上のように時代の流れとともに労働者側と企業側でニーズの変容と多様化が起こっています。ミスマッチを起こさないためにも、企業が自社の労働条件や求める人物像、スキルを積極的に開示する姿勢が求められるのです。
仕事に対する価値観が変化しているから
現在の若年層は、仕事に対する価値観が従来とは異なるといわれています。とくに1990年半ばから2010年代生まれの世代は一般的にZ世代と呼ばれ、1981年~1990年代に生まれたミレニアル世代とは異なる価値観を持つといわれています。
最も特徴的な点は、仕事よりもプライベートを重視する傾向が強くなっていることです。
仕事に関する価値観を問う二者択一の設問では、「仕事を充実させて生きていきたい(31.8%)」に対し、「プライベートを充実させて生きていきたい」と回答した人は68.1%でした。
また、「仕事は自分の人生を充実させてくれる」「仕事は私生活をするための資金集めの手段だ」の二者択一でも前者が36.3%、後者が63.8%と、よりプライベートを重視する傾向が見られます。
引用:Z世代の若者は仕事よりプライベート重視って本当? 昇給や昇進に興味はないのでしょうか…。|Yahoo!ニュース
以前は出世への意欲が高く仕事を重視する傾向が見られましたが、Z世代は出世よりもプライベートを重視する人材が多い点が特徴です。若年層の採用数を増やすためには、従来とは価値観が変化している点を理解する必要があります。
Z世代を採用する際のポイントについては、次の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。
デジタル化が遅れているから
日本で人手不足が深刻化する要因の1つとして、デジタル化の遅れも挙げられます。日本の場合、社会のインフラが人手に依存する傾向にあるため、外国にくらべると人手不足が一層鮮明になるといわれています。
たとえばオーストラリアは日本よりも広大な土地で、日本よりも少ない国民が暮らす国です。人口密度が低いにも関わらず、日本ほど人手不足が深刻化していない理由は、デジタル技術の普及により自動化が進んでいるためと考えられます。
オーストラリアでは低人口密度を支える技術が数多く開発されています。例えば、遠隔医療を含む効率的な医療サービス、24時間空いているジム運営をサポートする技術、農業を自動化する技術などいろいろ挙げられますが、デジタル化と自動化による効率的な社会インフラの整備によって、少ない資源で高い効率を実現しています。
各種制度や方針が異なる国の間での単純な比較はできませんが、小売店や宿泊施設、物流などを比較しても、オーストラリアは必要最小限の人手で運営するための工夫をしていることが見受けられます。
引用:なぜ日本では「人手不足」が深刻化しているのか? 海外事例から考える至極当たり前の理由|ダイアモンド・オンライン
日本の人手不足を解消するためには、デジタル技術の普及を目指し、人を介在しない労働環境を整えることも重要です。
業界や会社が抱える人手不足に関する課題
人手不足を解消するためには、ミクロな視点から業界や会社ごとの課題を理解することも大切です。ここでは、業界や会社が抱える人手不足の課題を紹介するので、参考にしてください。
企業の成長に人材採用が追いついていない
企業の成長に人材採用が追いついていないと、新規事業の立ち上げや需要増加への対応ができないため、売上を伸ばせません。慢性的な人手不足に陥り、需要を取り逃すことで機会損失が生まれます。
東京商工会議所の調査によると、企業が新たな取り組みを進めるなかで生じた課題として、人材不足や社員の能力不足を挙げる企業が最も多い結果でした。

55.4%と半数以上の中規模企業が人材不足や社員の能力不足が原因で、企業成長をストップさせています。今後は、新規事業の展開や新店舗開業など必要なタイミングで人材を確保できるように、より緻密な採用計画の策定が求められるでしょう。
採用計画の立案については、次の記事で詳しく解説しています。
働き方や待遇が悪く人材が流出する
働き方や待遇が悪いと、スタッフのモチベーションが低下して転職する可能性があります。待遇面の不満が業界全体に及ぶと、他業界への人材流出にもつながるケースもあるため注意が必要です。
しかし業界によっては、従来の慣習が依然として払しょくされずに、他業界に人材が流出しているケースが見られます。たとえば美容業界の場合、給与が安い上に労働時間が長く、カット練習の残業もつかないなどの劣悪な労働環境が業界全体の問題となっています。
アシスタント時代の手取りは約15万円。年収は200万円台だったなあ……。店の休業日が週1日。月に4~5回は休みがあったけど、ずっと立ちっぱで。体力使う仕事だよ
(中略)
アシスタント時代は、朝8時にサロンに着いて雑用を済ませ、11時から営業開始。20時に営業は終わるけど、そこからマネキンやカットモデルなどで練習をしていた。サロンを出るのは22~23時が多かったかな。残業手当? 付くわけないじゃん
引用:1日14時間以上働いても「手取り15万円」 美容師らの“苦境”|Yahooニュース
実際に劣悪な労働環境がきっかけで、美容師を辞め、ワークライフバランスを整えやすい業界への転職を目指す人もいます。
「アシスタントとして3年働きましたが、食事もまともにとれない環境だったので、健康状態はボロボロに。これ以上続けるのはまずいと思って、美容師を辞めることにしました」
転職を決意した際、「美容系の仕事に就くことは一切考えなかった」という。
引用:美容師から建設業界の作業員へ。働きやすさ重視で選んだ仕事を楽しむための心掛け「現場の雰囲気は自分でつくれる」|女の転職 type
働き方や待遇面の改善については、業改全体の課題として取り組むことが大切です。現在は、労働環境の改善に取り組む美容室も見られるようになりました。
まず、実働時間8hのフレックス制を取り入れています。「拘束時間が長い」「土日休めない」を理由に美容師を辞めてしまう人をたくさん見てきたので、そこに自由を持たせられるフレックス制を導入すれば、応募も増えるんじゃないかなと。
引用:モアリジョブ|「Vesper」オーナー 齊藤良さん
育成が不十分で業務を担当できる人材がいない
スタッフの育成が不十分な場合、特定の業務を担当できる人材が不足して人材不足に陥る可能性があります。
スタッフ育成については、OJTに関する課題を抱える企業が目立ちます。OJTとは日常の業務につきながら仕事の段取りややり方についての指導を受けることです。実地にもとづいた教育ができるため、即戦力を育成するためには有効な手段といわれています。
OJTに課題を抱える企業は多く、株式会社日本能率協会マネジメントセンターの調べによると9割近くの企業がなんらかの課題を抱えていることがわかりました。
▼OJTに課題を感じている企業の割合

さらに同調査では、OJTの課題として「指導者側に余裕(時間)がない」を挙げる企業が最も多いこともわかりました。
▼OJTで抱える課題の内容

つまり一旦人手不足に陥ってしまうと、業務を担当する人材が不足するだけではなく、育成に必要な人材までも不足して悪循環に陥る恐れがあるのです。
OJTだけで十分に指導が行き届かない場合は、外部研修で人材を育成する「OFF-JT」も併用しつつ教育制度の充実化を図る必要があります。「人材開発支援助成金」の活用も検討しつつ対策を講じるとよいでしょう。
なぜ人手不足への対策が必要なのか?
現在は業界および個別企業において、早急な人手不足対策が求められています。その理由として、将来的な人手不足問題の深刻化や顧客サービスへの悪影響などが挙げられます。
将来的に人手不足問題がさらに深刻化するから
近い将来、2030年問題により人手不足がさらに深刻化するといわれています。2030年問題とは、日本国内の総人口のうち約3割が65歳以上の高齢者となることで起こる諸々の問題をさします。高齢者の人口が維持される一方で若年層は減少するため、企業運営にさらなる打撃を与える可能性があるのです。
内閣府によると、2030年以降は若年層の減少が続く反面、高齢者の人口が維持されるため高齢化率は上昇。総人口は減少を続けると予想されています。
▼高齢化率と総人口の推移

若年層の減少が続くことで、さらに働き手が不足して人手不足が悪化する可能性があるのです。そのため若年層の減少に備えて、採用力を高めるとともに、65歳以上の高齢者を雇用できる体制づくりも求められます。
また現在は、若年層を中心に就労に対する意識が大きく変化している点が特徴です。1つの職場に留まることなく、短期間の転職を繰り返すようなキャリアが好まれる傾向にあります。労働市場における現在の傾向は人材の流動化とも呼ばれます。
実際、 総務省 統計局の調査 によると、2024年における「転職者」の数は331万人と前年比で3万人増加しました。2019年に過去最多となった後、コロナ禍にあった2020年〜21年は減少しましたが、2022年以降は再び増加に転じています。
また、今の勤務先を辞めて他へ転職したいと考える「転職等希望者」の数は8年ぶりに減少に転じたものの、前年に引き続き1000万人以上となっており、今後も人材の流動性は高いままと予想されます。
▼左図:転職者数の推移/右図:転職等希望者数の推移

このような状況下において、自社にマッチした人材を確保するためには、さらなる採用力の強化が求められるでしょう。
顧客サービスに悪影響を与えるから
人手不足になると顧客サービスに悪影響を与え、顧客離れが進む可能性があります。顧客離れは企業の売上にも大きな影響を与えるため、人材不対策を講じてサービスの維持に勤めることが大切です。
人手不足で顧客サービスの質が低下する傾向は、とくに労働集約型のサービスに見られます。
質の低下を感じているサービスとして、宅配便、病院、食堂・レストラン、小中学校教育、コンビニエンスストア、行政サービス、タクシーなどを比較的多くの人が挙げた〔図1参照〕。いずれも労働集約度が高く、人手不足の影響を強く受けるサービスである。
引用:人手不足で低下するサービスの質-統計に現れない物価上昇-|独立行政法人経済産業研究所
たとえば顧客がレジの注文を待たされたり、予約を取れなかったりすると、サービスの質が低下したと感じるようです。顧客サービスへの影響を防ぐためには、人材の確保に努めるだけではなく、デジタル化を進め業務効率化を図ることも大切です。
職場環境の悪化や更なる離職を招くから
人手不足が続くと、既存の従業員に大きな負担がかかります。長時間労働や休日出勤が増えると、心身の疲労が蓄積し、モチベーションの低下やストレスによる離職につながります。その結果、残った従業員の業務が過重になり、更なる離職を誘発するといった悪循環を招いかねません。
厚生労働省の調査 でも、前職を辞めた理由(個人的理由)として「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」が2番目に多く挙がっており、人手不足が職場全体の環境を悪化させるリスクは非常に高いといえます。
また、心身の疲労は従業員同士のコミュニケーションに影響を及ぼし、職場の人間関係の悪化を引き起こしかねません。
以上より、早期に対策を講じることが、離職防止と組織の健全な運営につながるといえるのです。
人手不足を解消するための対策事例
ここでは人手不足を解消するための対策事例として、職場環境の整備を中心に取り上げます。求職者のニーズに合うように職場環境を整えると、採用率の向上が期待できます。さらに既存のスタッフが働き方に満足するため、離職率の抑制にもつながるでしょう。
以上のように、人手不足対策を実施する際は、採用率の向上を図りつつ離職率を抑える取り組みを行うことが基本です。さらにITを導入して業務の効率化を図ると、スタッフが本業に集中できるようになるため、顧客対応の充実を図れます。
次の記事では人手不足対策の詳細について解説しているので、参考にしてください。
分業体制
「TICK-TOCK」では仕事を分割して分業体制を敷くことで、スタッフが得意な業務に従事できる体制を整えました。
仕事は分けられます。得意なことは得意な人に任せるのが一番。例えば商品開発やクリエイティブなことは私が担当。それ以外の苦手なことは他のスタッフに任せています。やりたいことをやりたい人に任せればいいんです。スタッフにも、やりたくないことはやらなくていい…と言っています。スタッフひとりひとりの才能を最大限に引き出して、活躍できる場所を提供するのが経営者の役目です。
モアリジョブ|「TICK-TOCK」 オーナー SAYURI USHIOさん
その結果スタッフが自分の才能を最大限に発揮できるようになり、働き方に対する満足度も向上しました。人手不足が深刻化する美容業界のなかで、ここでは人手の問題を抱えることなく順調にサロンを運営できているようです。
個人の能力に依存しない価値提供
ママ美容師サロン「hair Prego」は人手不足対策の一環として、スタッフ個人の能力に依存しない施術サービスを提供できるように体制を整えました。顧客にしっかりと話を聞いてコミュニケーションを重視することをコンセプトに掲げ、施術以外でも価値提供を行っています。
お客さまの話をさえぎらずに、最後までしっかりと聞くことです。スタッフには、お客さまの話の途中で割って入ったり、「あ、それはこういうことですね」とまとめたりすることは絶対にしないように伝えています。
引用:モアリジョブ|ママ美容師サロン「hair Prego」 オーナー 渡辺敦さん
さらに提供するサービスを限定することで、ブランクのある美容師でも働きやすい職場を実現。採用ターゲットを子育て中の美容師に絞り、子育てと並行しながら働ける営業時間に整えることで、人手不足解消に成功しました。
子供を育てながら美容師として時短で働きたい人はたくさんいるのに、それにこたえるお店がないということを耳にしたんです。そこで思い切って2号店の定休日を日曜、月曜、祝日にし、営業時間は17時までに変更してママ美容師にターゲットをしぼって募集をかけたところ、すぐに3名の方がパートで決まったんです。
引用:モアリジョブ|ママ美容師サロン「hair Prego」 オーナー 渡辺敦さん
風通しの良い職場環境
複数の美容室を展開する株式会社アンジーでは、 職場の先輩や上司が新入社員に積極的に話しかけることで風通しの良い職場環境を実現しています。
上の立場の人間には話しづらさがありますよね。なので、僕から積極的に話しかけます。「出身地はどこ?」、「家族は?」、「お子さんは何歳?」など細かなことをいろいろ聞き出します。そうすると相手は「自分に興味を持ってくれている人がここにいる」と思ってくれるんですよね。僕もいろいろ質問する中で、その人がいちばん興味を持っていることや目指したいことを聞き出して、彼らが夢に近づけるようにサポートしています。
引用:モアリジョブ|「株式会社アンジー」 代表 山口裕喜さん
先輩や上司が積極的に話しかけることで、スタッフの承認欲求を満たすことにつながり、入社間もない社員でも満足して働けるようになりました。
一旦職場を離れても再び戻ってくるスタッフや、友人・知人を積極的に紹介してくれるスタッフが多いため、人手不足に悩まされることがないようです。
また戻ってきてくれるスタッフや「ここで働きたい人がいる」と友人や知人を紹介してくれるスタッフが多いですね。
引用:モアリジョブ|「株式会社アンジー」 代表 山口裕喜さん
スタッフを第一に考える経営姿勢
人手不足を解消するためには、スタッフを単なる労働力ではなく「会社の財産」として大切にする姿勢が不可欠です。実際に美容業界では、人材不足が廃業や閉店の大きな要因となっており、従業員を大切にする企業だけが生き残れるという声もあります。
スタッフ1人ひとりが財産だという考え方で、スタッフと接していきたいと思っています。周囲の閉店、廃業する美容室を見ていると、ほとんどの要因が人手不足にあると感じており、今後ますます人を大切にする会社だけが生き残れるのではないかと考えています。
また美容師の仕事は、人と人との関わり合いの仕事です。もちろん技術の提供という根本がありつつも、「お客様は人につく」のではないかと思うんです。そういった点からもスタッフを大切にし、長く働いてくれることが、会社の成長には欠かせないと考えています。
引用: モアリジョブ |株式会社Ashanti サロン統括マネージャー・アカデミー講師 大澤剛志さん
このように、現場の経営者の声を引用することで、抽象的な対策論だけでなく、実際に人材を大切にして成果につなげている具体例を示すことができます。
企業が取り組むべき人手不足解消の新戦略
人手不足を単なる採用強化で補うだけでは限界があります。企業が持続的に成長していくためには、人材の能力開発や柔軟な働き方の制度整備、自社の魅力発信といった“新しい戦略”を組み合わせていくことが不可欠です。
以下では、労働力不足に直面する企業が実践すべき取り組みを3つ紹介します。
リスキリング(学び直し)による人材育成
近年注目されているのが「リスキリング(Reskilling)」です。リスキリングとは、従業員が新しい知識やスキルを習得し、変化する社会や技術に適応できるようにする「学び直し」の取り組みを指します。人材獲得が難しいなかで、既存の社員を成長させ戦力化するという手段は非常に有効です。
厚生労働省も「キャリア形成・リスキリング推進事業(厚生労働省委託事業)」 を通じて、従業員のスキルアップを支援しています。企業等の各組織や個人を対象に、キャリアコンサルティングやキャリア研修などを無料で行うものですこうした公的支援を活用すれば、企業は負担を抑えながら社員の能力開発を推進できます。
結果として、採用難の時代に「辞めさせない」「育てて活かす」人材戦略で、人手不足の解消を図れるのです。
リモートワークや柔軟な働き方の導入
労働力不足の時代には、従来の「フルタイム・出社型」だけでは人材を確保しにくくなっています。リモートワークやフレックスタイム制、副業容認、多様な休暇制度などの柔軟な働き方を導入することで、子育てや介護をしながら働きたい層、地方在住の人材、シニア層など、これまで十分に活用できなかった人材を活かすことができます。
さらに、柔軟な働き方は従業員のワークライフバランス改善にもつながり、離職率の低下やエンゲージメント向上という副次的な効果も生み出します。単なる制度導入にとどまらず、「働きやすさ」を企業文化として根付かせることが、人手不足時代の競争力強化につながります。
厚生労働省が公開している「働き方改革特設サイト」 では、リモートワークや多様な休暇制度など様々な実例が紹介されており、自社での取組みのヒントを得られます。
採用ブランディングで魅力を高める
「採用ブランディング」とは、企業理念やビジョン、従業員が働く姿などを発信し、より自社とマッチした人材の採用につなげることです。人手不足の中で優秀な人材を確保するためには、自社の魅力を正しく伝える採用ブランディングが欠かせません。
給与や福利厚生といった条件面だけでなく、企業のビジョンや社風、働く人々のやりがいなどを発信することで、応募者に「ここで働きたい」と思わせる効果があります。SNSや採用サイト、社員インタビューなどを活用して、自社の強みを積極的に発信していくことが、人材確保に直結します。
採用ブランディングについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
なぜうちは人材不足なのか? 高定着率企業の事例を無料でチェックしよう
人手不足を根本から解消するには、「採用」だけでなく「定着(社員が辞めずに働き続けること)」に目を向けることが極めて重要です。今まさに「なぜ自社では人が定着しないのか?」と悩んでいるなら、成功企業の実践事例から学ぶのが近道です。
以下の資料では、定着率が高い企業3社の具体的な取り組みを紹介しています。「選べる働き方制度で多様な人材が継続しやすい環境」「福利厚生だけでない、現場の工夫や制度設計」など、他社でも応用可能なヒントにあふれています。
ぜひこちらから資料を無料ダウンロードして、「定着率を高める施策」のヒントを手に入れてください。
まとめ
本記事を総括すると次のとおりです。
- 若年層や専門的な職種を中心に人手不足が進んでいる
- 人手不足になる理由として、労働力の減少や人材のミスマッチ、仕事に対する価値観の変化が挙げられる
- 将来的にもますます人手不足の深刻化が予想されているため対策を講じることが重要
今回は人手不足対策について事例を交えながら解説しました。将来的には、さらなる人手不足問題の悪化が懸念されています。それに対応するためにも本記事の内容を参考にして、人手不足対策を進めてみてください。
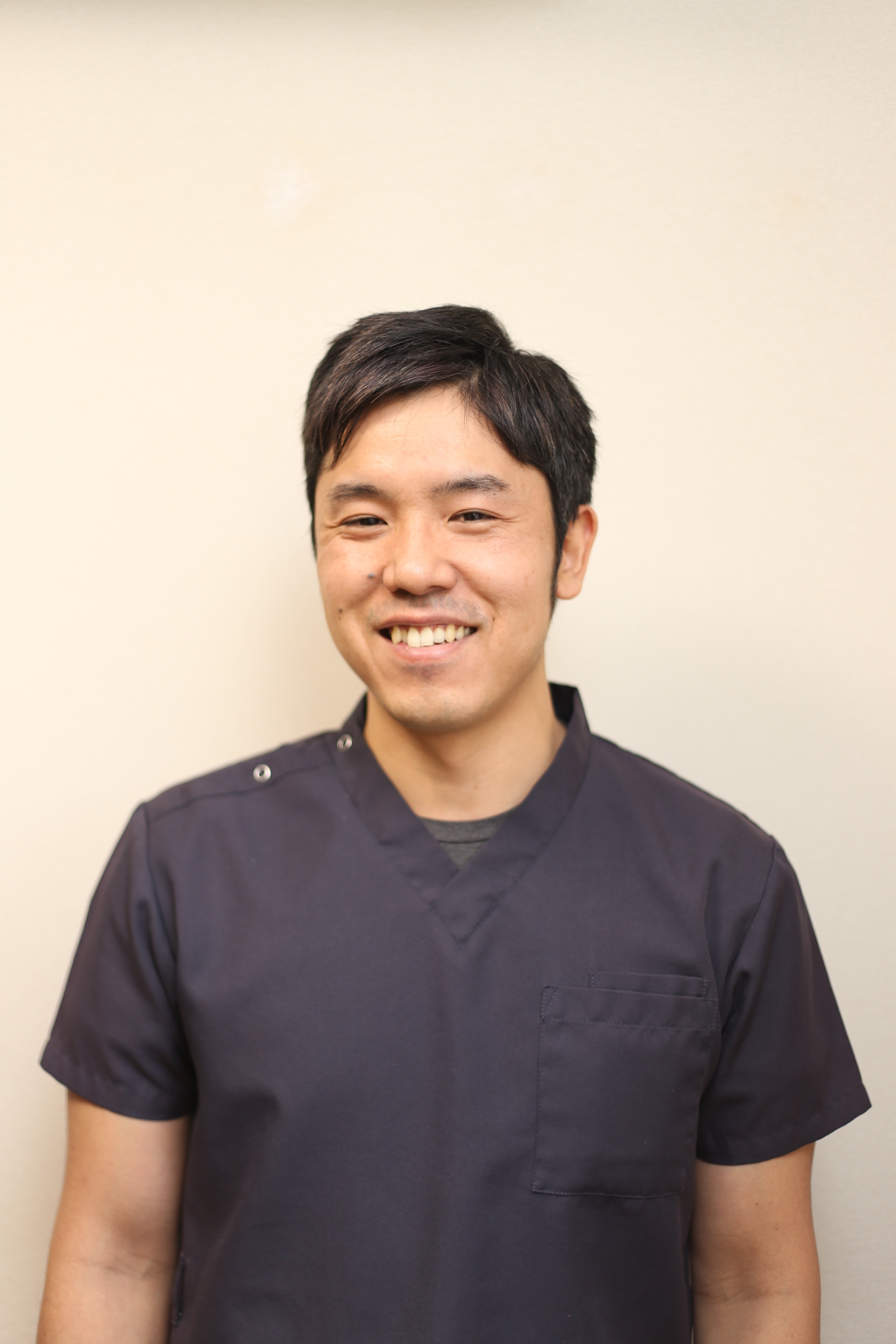
- 執筆者情報
- 東 大輔(Higashi Daisuke)